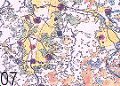ランドスケープデザインの実体
広域的なランドスケープデザイン
![]() 写真7は我々が扱う範疇で一番スケールの大きい、 広域的な緑計画です。
写真7は我々が扱う範疇で一番スケールの大きい、 広域的な緑計画です。
これは福井県の例ですが、 全県土の中でどういう緑の構成を考えていくべきか、 それを将来にどうつないでいくか、 緑の質がどうであるのか、 まちとの関係がどう構造化されているのか、 そういったようなことを考えたものです。
![]() 残念ながら我が国では国土計画というようなレベルには達していませんので、 我々ランドスケープデザインの世界で一番広域の計画はこの県のレベルにです。
残念ながら我が国では国土計画というようなレベルには達していませんので、 我々ランドスケープデザインの世界で一番広域の計画はこの県のレベルにです。
先ほどのチャート(図1)で行きますと、 当然行政よりで、 計画型の、 縦軸の一番上のあたりに近いところに位置するものです。
![]() 一方で、 緑だけではなしに、 都市活動というものと同時に進行させなければなりません。
一方で、 緑だけではなしに、 都市活動というものと同時に進行させなければなりません。
対峙する都市活動で捉えた構造を緑に視点を置いた図とオーバーラップさせてますと、 色々な構造が読みとれてくるわけです。
![]() ここに至るまでには、 当然ながら、 全県の自然の調査、 風土の調査、 文化の調査、 都市軸の調査等をいたします。
ここに至るまでには、 当然ながら、 全県の自然の調査、 風土の調査、 文化の調査、 都市軸の調査等をいたします。
また、 特に大きな問題として防災といったとらえ方もしながら組み立てます。
![]() それらを総合化しまして、 写真7のような、 県土の一つのモデルとして、 今後の保全、 開発も含めた総合図を作るわけです。
それらを総合化しまして、 写真7のような、 県土の一つのモデルとして、 今後の保全、 開発も含めた総合図を作るわけです。
![]() さらに、 計画図を作って終りではなく、 そこからランドスケープのもう一方の分野である計画の普及、 啓発活動が始まります。
さらに、 計画図を作って終りではなく、 そこからランドスケープのもう一方の分野である計画の普及、 啓発活動が始まります。
図1のチャートでは縦軸の上部と下部とをつなぐための活動です。
具体的にはシンポジウム等による緑のアピールやイベントを兼ねた緑地創造や緑と親しむレクリエーション活動の仕掛けなどです。
このページへのご意見は前田裕資へ
(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ