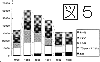移民の変遷と居住状況の変化
─国籍と居住パターン─
現在のフランスの人口は約5700万人。その4人に1人、 つまり約1400万人は、 みずからが移民であるか、 または父母あるいは祖父母の代が移民であるという。
出生地主義をとるフランスでは、 第2世代以降はフランス国籍を取得するのが容易である。
それでも19世紀半ばには総人口の約1%であった外国人数は、 今日では6%を超えている。
これらの移民は、 文字どおりの意味でフランスをつくる重要な役割を担ってきた。
彼らの多くはフランスで労働者として、 その時代時代の重要な産業と関わってきたからである。
19世紀にパリの地下鉄建設を担ったのはベルギーからの移民であり、 20世紀に入り炭坑労働を担ったのは、 ポーランドやイタリアからの移民であった。
1950年代後半から70年代前半にかけての高度成長期の労働力を提供したのは、 アルジェリア系移民とポルトガル系移民である。
もちろん、 すべての移民がフランスで労働することだけが目的で移民してきたわけではない。
イタリアやスペインからの移民は、 ファシスト政権を逃れてきた政治難民的性格が強く、 70年代にピークをむかえるポルトガルからの移民の多くは、 当時のポルトガルの植民地であったアンゴラでの戦争への徴兵を逃れてきた。
このように移民の理由はさまざまであるが、 いずれの場合も移民は労働力としてフランスにおいて重要な役割を担ってきた。
そして定住化の進行にともない、 生活者として着実に地域社会の一員となっていった。
移民の居住パターンには、 多かれ少なかれ出身国ごとに特色が見られる。
それだけではなく、 移民の居住状況のなかに、 フランスの産業化や都市化の歴史が刻印されているのを見ることができる。
つまり、 出身国や、 移民の時期、 その時期のフランスの労働力需要などさまざまな要因が、 移民の居住地や居住パターンに如実に反映されているのである。
移民は、 フランスでどのような居住環境を生き、 どのようにフランス社会のなかに居場所を見いだしてきたのだろうか。

 さて、 移民を考えるさいにフローとストック、 つまり毎年の流入者数と居住者の総数の両方の側面から見る必要がある。
さて、 移民を考えるさいにフローとストック、 つまり毎年の流入者数と居住者の総数の両方の側面から見る必要がある。
近年の傾向を概観しておこう(図1・図2)。
ストックの面では、 南欧のポルトガル、 イタリア、 スペインはいずれも外国人人口の上位6位に入るが、 出身国自体の経済発展や、 EU統合による人の移動の自由化により、 フロー、 つまり近年の流入はほとんどなく、 総数はむしろ減少傾向にある。
それに対してアルジェリア、 モロッコ、 チュニジアのマグレブ諸国はストック、 フロー両方において依然として重要である。
また、 ストックはそれほど多くはないが、 近年のフローでつねに上位にあるのがブラック・アフリカ出身者とアジア出身者である。
とくにブラック・アフリカ出身者は、 根強い黒人差別や、 一夫多妻制に対する偏見などから、 実際の人数に対し、 問題として取り上げられる頻度は不釣り合いに大きい。
以下では、 まず外国人の居住パターンの一般的な傾向を概観し、 その後に、 南欧系移民、 マグレブ系移民、 ブラック・アフリカ出身者の住宅事情についてそれぞれみていこう。
(3)フランス人の10人に4人に対し、 10人に7人の外国人が人口10万以上の都市に居住している。
(4)ブルターニュ、 バス・ノルマンディなど西部の外国人人口比率は小さい。
結果としてこの3地域圏だけで外国人全体の約58%が居住していることになる。
これらの地域圏はいずれも、 パリ、 リヨン、 マルセイユといったフランスの3大都市を擁し、 重要な産業の拠点である。
また、 南欧出身者にとってもマグレブ出身者にとっても、 出身国の国境に近い地域でもある。
これらの地域圏の中で、 イル・ド・フランスでは他の地域と比較して、 外国人人口の増加が70年代以降も継続してみられる。
しかしその他の地域圏で外国人人口が集中しているのは、 鉄工業や繊維産業など衰退産業を抱える自治体であり、 いずれも現在の人口の流動性は小さい。
外国人住宅事情の一般的傾向
出身国ごとに移民の時期が異なり、 それによって居住状況も異なるが、 一般的な傾向としては、 (1)出身国に近い地域に多く居住し、 また、 (2)移民当時のフランスの労働需要を反映して、 当時の基幹産業が立地していた地域に居住している。 具体的には、 外国人全体の36%が、 パリ市とそれに隣接する8県からなるイル・ド・フランスに、 やはり8県からなりイタリア、 スイスと国境を接する地域圏ローヌ・アルプに13%、 地中海に面しイタリアとも国境を接し6県からなるプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュールに9%居住している。
具体的には、 外国人全体の36%が、 パリ市とそれに隣接する8県からなるイル・ド・フランスに、 やはり8県からなりイタリア、 スイスと国境を接する地域圏ローヌ・アルプに13%、 地中海に面しイタリアとも国境を接し6県からなるプロヴァンス・アルプ・コート・ダジュールに9%居住している。
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ