
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
3年目の時はまだ泥沼の中を走っており、 もしかしたらまちのビジョンが何とか出来るかもしれないという状態でした。 当時は、 新長田駅北地区全体で21の協議会があり、 そのうち東部(約30ha)は12協議会あり、 私は10協議会に関わっていました。
しかし実際のところ、 全体構想や共同建替は、 各協議会の小さな枠組の中で進めるものではありません。 結局テーマ毎に幾つかの協議会が集まり、 部会で検討するという形ができ上がりました。 それがきっかけになり、 この1年間で続々と成果が出てきました。 シューズギャラリー、 アジアギャラリー構想の提案、 またいえなみ基準の締結とその基準が神戸市都市景観条例による景観形成市民協定として認定される、 というような具合です。 非常時に協議会はよく頑張りました。 また、 行政もタイミング良く対応して頂いたと思います。 その結果ギャラリーの核施設となるパイロットショップ、 また共同建替のほとんどが着工しました。 というわけで5年目の今年は、 これら構想の種火が形になる段階といえます。
ところが当地区は、 住工商混在し大小敷地が混在しているうえに、 確保しなければならない公共用地が多い。 このため鷹取北エリアへの飛換地も考慮された特に換地の難しい地区であることもあり、 仮換地に手間取っており、 またケミカルシューズ等地域産業の活力がかなり弱くなっていることなど、 課題が山積しています。 今だに協議会の役員は気の安まるところが無い状態です。2 新長田駅北地区
―土地区画整理事業久保都市計画事務所 久保光弘
震災復興3年と5年
今回のように復興事業を振り返る機会は3年目にもありました。 それは『震災復興が教えるまちづくりの将来』(学芸出版社、 98年)にまとめられており、 皆さんもご存じでしょうから、 今日はその3年目と5年目で何が違うかをお話しします。

|
| 新長田駅北地区(東部)まちづくりビジョン |
その舞台となる長田の都市構造は、 自然や歴史からみて私自身は条里制都市とか風水都市として捉えられると考えています。 この「杜の下町構想」は具体的には現在、 快適居住構想、 シューズギャラリー構想、 アジアギャラリー構想の三点がでてきています。

|
| いえなみ基準の区域 |
共同建替につきましては当初は町丁ブロックごとにあった案が徐々に集約されて、 現在5ヶ所にまとまり、 希望される方々は皆近隣の住宅へ入れることになりました。 五つの共同建替住宅の配置については、 北側に大きな道路又は公園がある位置にするなど、 周辺の環境に影響を及ぼさないよう計画的な配置がされました。
この地域は平成8年頃のデータをみますと、 50〜60m²の小さな家の件数割合が全体の5割、 6割を占めます。 一方、 敷地面積で考えると500m²以上を所有する方たちの土地が全体面積の5割、 6割あり、 これら大小の地権者が混在している状態です。 ですから換地も、 敷地が住宅地のように平均していればその後の推移で権利が動いても道路は余り変わりませんが、 ここはいろんな推移にあわせて、 区画道路等変更をせざるを得ない場合も多く、 先ほど言ったような変更提案も多く必要となってくるのです。

|
| 共同建替住宅イメージパース |
さて、 これからのまちづくりを議論していくと、 やはり住商工の共存には「景観と環境の重視」が重要であるという点に帰着します。 例えば、 店の集客にも周囲の家並みが大事になってきます。 そのスタイルとして、 先ほど触れました「杜の下町構想」が出てくるわけです。

|
| シューズギャラリー「見える工場」パース |

|
| シューズプラザ・イメージパース |

|
| 内部イメージパースとシューズプラザ平面図 |
シューズプラザの1階と2階にはメーカー直販等のアンテナショップがあり、 中央の広場は2階まで吹き抜けになっていて、 いろんなイベントができるようになります。 3階は靴のデザイナーを養成する等のラボとして使われます。 4階は二つの用途に分かれますが、 一つはアジア交流プラザとしてアジアに対する支援・交流団体や、 アジアの文化をPRしていく場、 もう一つはタウンセンターというか、 まちづくりの拠点になるような場として使っていこうと考えられています。

|
|
アジアギャラリー・パイロットショップ |

|
|
いえなみ基準の一例(戸建住宅の場合) |
図は戸建住宅の場合のいえなみイメージを示しています。 内容は、 一般的なものといえますが、 例えば傾斜屋根等については、 陸屋根での雨漏りの経験が話される等、 単に見た目の景観だけでなく、 生活に則した話し合いの積重ねの中から見えてきたものです。
店舗や工場についても、 傾斜屋根の使用を呼び掛けています。 また、 「見える工場」でも言及したように、 1階の店舗部分はできるだけ中が見えるようにと、 透明ガラスやシースルーシャッターを使ってもらうルールとなっています。 神楽町の共同化住宅の店舗や保育所等からシースルー化が始まっています。
また街なみ環境整備事業助成で外構も助成され、 木も一本から補助の対象となりますので、 できるだけいえなみの中に緑を増やしてもらおうと呼び掛けています。
いえなみ基準が円滑に活用されるよう、 「いえなみ委員会」が設けられています。 これはいえなみ基準を締結している各協議会からの代表者の集まりで、 都市景観条例に基づく景観形成市民団体の認定を受けようとしています。 再建する建築主は、 いえなみ委員会に自主的に「建築事前報告書」を提出することになっています。 いえなみ委員会は、 チェックのうえ必要なアドバイスをつけて報告書の受取通知書を返送しますが、 建築主が市から助成を受ける場合はこの受取通知書を添付するしくみになっています。


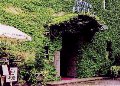
いえなみ基準の一例(小規模併用住宅(店舗やシューズギャラリー等)の場合)
いえなみ基準の一例(シューズギャラリー等の場合)
街並み環境整備事業による外構等修景助成制度のあらまし



街並み環境助成制度
助成手続フロー
建築事前報告書提出のお願い

|
|
事前報告書の書式 |

|
| いえなみ基準に合わせたチェックリスト |

|
| コミュニティ道路のテーマ |
この地域では、 条里地割による区画、 「坪」又は「町」がそのまま町丁単位のコミュニティとなっています。 地区幹線道路がこの四つの町(町丁単位)を囲む形で配置されますので、 この四つの町が「安全安心街区」、 いわば「都市の室」になります。
この安全安心街区の中央に東西、 南北にコミュニティ道路的な性格の道路ができます。 これは、 一方通行の既存道路の活用ですが、 一部は拡幅されて14mコミュニティ道路となります。 協議会の検討では、 この14m幅員のうち車道部分は3.5mにおさえて歩道をゆったりとしたものにしようとしています。 平成8年の当初まちづくり提案どおり「せせらぎ」も折り込まれています。 電柱については、 関連の協議会が関西電力へ要望に行き、 14mコミュニティ道路やJR通り(兵庫駅鷹取線)で簡易の地中化を行うことになりました。 簡易ですから、 南京町のようにポールが立つということはあるようです。
またJR新長田駅北口に接するJR通りはいつも自転車がぎっしりと詰まっていて、 駅前というより駅裏のイメージだという声が協議会から上がり、 改良に向けての提案を道路部会で検討されました。 内容は、 駐輪場の一部の移転と側道的な区画道路の歩道化です。 これによってJR通りは、 地区の玄関口にふさわしく緑豊かな安全で快適な通りとなりそうです。
駐輪施設の一部移転は、 JR線南側のJR用地(三角地)を利用する方向で検討が進んでいます。
当地区では、 震災前の世帯の6割程が借家世帯でした。 また貸工場が起業家を育てました。 このようなかつての地域産業を支えた町のしくみがほとんどくずれています。 多分、 長屋の持ち主等の換地更地が残ると思います。 「地区の活性化」がたいへん大きいこれからの課題です。
また長田では、 震災復興市街地整備事業により、 これから大きな道路と公園の整備段階に入ります。 これが20世紀型最後の開発なのか21世紀型開発として評価されるかは、 杜の下町の「杜」、 すなわち環境共生の視点で公共施設の整備を行うかどうかにかかっているように思います。



JRの駅前通り
駅前通り完成予想パース
駅前通り完成予想パース
これからの課題
このように、 3年目に見えてきたビジョンに今やっと種火が付いた状態ですが、 同時に長田の構造上の問題がこれからの大きな課題として見え始めています。
このページへのご意見は阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワークへ
(C) by 阪神大震災復興市民まちづくり支援ネットワーク
学芸出版社ホームページへ