ポレマルコスとエウテュデモス。
プラトン『国家編』第1巻に、ソクラテスと対話するポレマルコスの姿がある。彼は「三十人」政権下、非業の死をとげる(「リュシアス弁論集」第12弁論)。
『パイドロス』238D
ソクラテス「……今だってもうほとんどディテュランボスをひびかせているようなものだからね」。
リキュムニオスは、キオス出身のディテュランボス詩人で、ゴルギアスの流れを汲む弁論家。
ポロスはシケリア島アクラガスの生まれ。同じくゴルギアスの流れを汲み、リキュムニオスの弟子といわれる。弁論術の著作もものにしたらしい(プラトン『ゴルギアス』462B)。
意味するところが明らかになるような表現。(アリストテレス『弁論術』第3巻、第2章 1)
目に浮かぶような生き生きとした表現。(アリストテレス『弁論術』第3巻、第11章1-3)
聴衆の好意を得るために、発言者が「善良な市民であること(epieikes)」を訴えること。いわゆる「性格描写」とは違う。
「言論を通してわれわれの手で得られる説得には三つの種類がある。すなわち、ひとつは論者の人柄にかかっている説得であり、いま一つは聞き手の心がある情態に置かれることによるものであり、そうしてもう一つは、言論そのものによって、言論が証明を与えている、もしくは与えているように見えることから生ずる説得である。……「人柄によって」と言うのは、論者を信頼に足る人物と判断させるように言論が語られる場合のことである。つまり、人柄の優れた人々に対しては、われわれは誰に対するよりも多くの信を、より速やかに置くものなのである」。(『弁論術』第1巻、第2章4)
文の構成部分である節が、節相互にも全体に対しても、密接に関連を保持し、文全体が組織的に構成されているものをいう。節の相互関係としては、並置法と対置法(antithesis)、等長法(parisosis)、等韻法(paromoiosis)がある。(アリストテレス『弁論術』第3巻、第9章)
「散文はリズムを持たなければならないが、しかし韻を持ってはならない。そうでないと、それは詩になってしまうからである」(アリストテレス『弁論術』第3巻、第8章)
「表現が平板なものでも、不相応に誇張されたものでもなく、それ相応に似つかわしいものであるということも、〔表現の〕優秀性とすべきである」(アリストテレス『弁論術』第3巻、第2章)
「表現が適切さを保持しうるのは、それが感情と人柄をよく表し、問題とされている事柄によく釣り合っている場合である。……釣り合っているとは、荘重なことについて軽々に述べることでもなければ、とるに足らぬことについて勿体ぶった述べ方をすることもなく、また、つまらない名が修飾語で飾りたてられたりしていない場合を言う」。(同、第7章)
これらについては、アリストテレス『弁論術』第2巻、第12章-第17章で長々と論じられている。
ハーモニーとは、現代では、二つ以上の高さの異なる音が同時に響いたときに合成される音のことであるが、〔古代〕ギリシア音楽では、直列的な音(phthongos,pl.phthongoi)の相互関係を表す。
アテナイの*職業的軍人*〔時代の変化に思いをいたすべし!〕。
初め、傭兵隊長として、名にし負うスパルタの重装歩兵をコリントス近くで撃破して名を挙げる〔390年〕。その後、ヘレスポントスの海峡地域で成功をおさめたものの、アンタルキダスがペルシアとの和約を成立させたために、徒労に終わる。
387/386以降はトラキアのコテュスに仕え、その後、アテナイによってペルシアの援軍としてエジプトと戦った〔つまり、エジプトの独立闘争を抑圧〕。
帰国するや、ティモテオスに代わって将軍となった〔373/372〕が、ペロポンネソス半島を攻撃する計画は、普遍平和〔372/371〕によって出鼻をくじかれ、370/369にはスパルタのために働いた。360年代には北方へもどり、アテナイの将軍としてアンピポリス周辺で活動、その後、トラキアで軍務についた。
彼の軍人としての経歴は、エンタバの戦い〔356〕で反乱同盟軍に敗れ、この件で告訴されたが無罪となった。
彼は、重装歩兵の密集隊による従来の戦術に改良を加え、重装歩兵と散開して戦う軽盾兵との組み合わせによって戦果をあげたといわれる。
「対置法」とは、いわゆる「対句法」のことである。例えば、A Glossary of Rhetorical Terms with Examplesは、ShakespeareのJulius Caesar中の次の表現を例に挙げている。
*Brutus: Not that I loved Caesar less,
but that I loved Rome more.
「等長法」とは、節の長さをそろえる表現法、
「等韻法」とは、節のそれぞれの末端(始め、ないし、終わり)の音節を等しくする表現法である。
これらについては、アリストテレス『弁論術』第3巻、第9章に詳しい。
日本語ではわかりにくいが、原文では次のようになる。
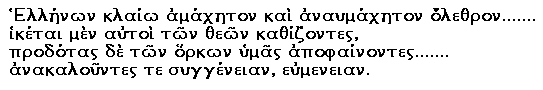
このような区分の仕方は、アリストテレス『弁論術』第1巻、第1章3。
アリストテレス『弁論術』第3巻、第14章6-8参照。
弁論術(rhetorike)が真に技術(techne)の名にあたいするには、言論が向けられる人々の心、用いられる言論、人々の心に対する言論の働きかけに関する知識がそなわっていなければならない(が、弁論家たちにはそういう知識がない!)というのが、プラトンの批判であった(『パイドロス』270E-272A)。
このプラトンの批判に応えて、聞き手が説得されるのは、「事柄のロゴス〔=論証〕が与えられるゆえに」、「聞き手が何らかの感情をいだくがゆえに」、「話し手を善良な人柄の人物と受け取るがゆえに」という、三要素を挙げたのがアリストテレスであった。(アリストテレス『弁論術』第1巻、第2章3-6)
論証(apodeiktike pistis=論証的説得立証)は、説得推論(enthymema)と例証(paradeigma)とをもって行われるが、これを構成する前提命題が、尤もらしさ(eikos)と、徴証(semeion)である。
「尤もらしさ」とは、「三角形の内角の和は二直角である」というような必然的命題ではないが、かといって、偶然命題でもない。弁論術で取り扱うのは、必然的命題はほとんどなく、たいていが蓋然命題である。
それは、弁論術の対象は人間の行為であり、為される行為はすべて他の仕方でもあり得る類のものであり、どれ一つとっても必然的なものはないからである。
ひとを説得しようとするとき、われわれはありのままの真実を言ってはならず、尤もらしいことを言わなければならないという例。――力は弱いけれども勇気のある一人の男が、力は強いが臆病な男を殴りつけて、上着あるいは何か他のものを奪い、法廷に連れ出されたとする。この場合、どちらの男も本当のことを言ってはならない。臆病な男は、自分を殴ったのは、その勇敢な男一人ではなかったと主張すべきであり、他方の男は、これを反駁して、その場には二人のほか誰もいなかったと主張し、「ごらんのとおりの力の弱いこの私が、どうして、こんな力の強い男に手出しすることなど出来ましょうや」と訴えるべきである。(『パイドロス』273B)
力の強い男が、力の弱い男を殴り倒した場合はどうすればいいのか? 「どうして、この私がそんなことをするはずがありましょうや! そんなことをすれば、尤もなことだとすぐに疑われるでしょうから」と言うのがよい。(『弁論術』第2巻、第24章)
もちろん、アリストテレスは、これを「見せかけの説得推論」として否定しているのだが……。
いくつかの前提命題から、結論命題を論理的必然によって導き出すのが「説得推論(enthymema)」であるのに対して、個別命題を前提にして、結論を導き出す(=帰納する)論法が「例証(paradeigma)」である。(アリストテレス『弁論術』第2巻、第20章参照)
論証の前提そのものを特徴づけるのが「尤もらしさ(eikos)」だとすれば、結論との関係で特徴づけるのが「徴証(semeion)」である。
結論に対して必然的な関係をもつ前提は、必然的な徴証として証拠(tekmerion)」と呼ばれる。例えば、「彼は熱が高い」(前提)は、「彼は病気である」(結論)の証拠である。しかし、結論に対して必然的でない関係をもつ前提は、徴証であっても必然的ではないので証拠にはならない。「彼は呼吸が荒い」(前提)は、「彼は熱が高い」(結論)の徴証ではあっても、証拠にはならない。(浅野楢英『論証のレトリック』)
誇張表現を意味する最も一般的なギリシア語はhyperbole 。
同じ誇張表現でも、deinosisには、恐るべきこと(deinon)を強調する意味があるようである。
hyperboleの例としては、目の下に痣をつくった人について「桑の実でいっぱいになった果物かご」という表現をアリストテレスは挙げている(『弁論術』第3巻、第11章)。
auxesisは、例えば接続詞を省略して、「私はやって来た、私は話し合った、私は懇願した、……」とすることによって、事を大きく印象づける効果のあることをアリストテレスは指摘する(『弁論術』第3巻、第12章)。
oiktosは、聞き手のあわれみを得ようとする表現法。「教示と説得とによらずして、裁判官に哀願し、そうして、哀願によって赦罪を得るが如きは」と『ソクラテスの弁明』にある(35C)。アリストテレスも、問題の事柄に直接関係しないような説得を、まやかしとして厳しく批判している。