
|
| 「幣舞橋」(釧路) |
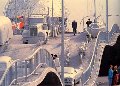
|
| 「ハイウエイ86」 |

|
| 「宿命反転の場」荒川修作 |

|
| 「今西元赤坂」高松伸 |

|
| 「青山テクニカルカレッジ」渡辺誠 |
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
ひとつは意図的に現実と芸術の境をポジティブに消すことができるなら、 人間の生活は豊かになるだろうという考え方です。 実はその発想は昔から日本人は持っていて、 利休の茶道などはまさにその考え方で生み出されたものだったろうと考えます。 利休は四畳半の茶室、 欠けた茶碗でも現実と芸術の融合した生き方ができることを示しました。
同様にポジティブな意味で現実と芸術の境を消すということを、 戦前の華道の人である西川一草亭は、 『風流生活』1932の中で「我々は実生活の他に芸術を求め、 趣味を求め、 芝居を見たり、 音楽をきいたり、 書を味わったりしているが、 毎日の生活をその侭芸術として味わひ楽しむことが出来たら、 どれほど人間は幸福だろう。 茶碗土瓶が芸術であり、 椅子卓子が芸術であり、 机硯が芸術であって、 行佳座臥、 随時随所それぞれ鑑賞して楽しむことができたら、 それほど便利なことはない」と述べています。
またこの人は都市についても触れており、 「近来の絵などは都市の前にはほとんど一顧の値もしないほどに拙い」。 都市の方が我々にとってははるかに有意義な体験を与えてくれると述べています。 芸術より現実を称揚している形ですね。
いずれにしても、 芸術が都市の中にどんどん入ってきて、 それがひとつの風景を作っていくという考え方です。 6. アートのある都市風景
生活そのものがアートになる
4番目の対応は「アートのある都市風景」です。 これは「装う都市風景」と似てるようでちょっと違います。 「装う」よりも志が高く、 芸術を目指しています。 現実と芸術の境を消すような都市風景を目指そうということですが、 これにも二つの立場があるように思います。
一方、 都市や地域のレベルで言うと熊本アートポリス、 ベルリンIBA、 ピース&クリエイト(広島版アートポリス)がアートのある都市への取り組みと言えるでしょう。
これらの手法の重要な側面は、 洗練された選択を可能にするシステムでもあるということです。 例えば、 熊本アートポリスでは競争入札をしないようにしています。
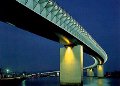
|
| 熊本アートポリス・橋(熊本県パンフレットより) |

|
| 熊本アートポリス・展望台(熊本県パンフレットより) |