
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ
ドイツ、 ハノーバー市の住環境改善活動
スプロール地区の形成史

|
|
図6 ハノーバー市とハノーバー南地区(リンデン地区) |



図7(a) 南地区の発達過程1(1854)
図7(b) 南地区の発達過程2(1854)
図7(c) 南地区の発達過程3(1854)
![]() ここには二大地主さんがいらっしゃったんですが、 その二大地主さんが区画整理をして、 土地を切り売りしていって、 工場の発達にあわせて、 家が建ち並べていきました。 最初に建っていったのは間口が狭くて、 細長くて、 後ろにバックヤードがあるような、 だいたい2階建てぐらいの戸建住宅です。 標準型の住宅といわれているものです。 1848年に条例ができ、 その条例に基づく、 標準型の住宅が並びだしたといわれています。
ここには二大地主さんがいらっしゃったんですが、 その二大地主さんが区画整理をして、 土地を切り売りしていって、 工場の発達にあわせて、 家が建ち並べていきました。 最初に建っていったのは間口が狭くて、 細長くて、 後ろにバックヤードがあるような、 だいたい2階建てぐらいの戸建住宅です。 標準型の住宅といわれているものです。 1848年に条例ができ、 その条例に基づく、 標準型の住宅が並びだしたといわれています。![]() 1870年ぐらいから、 工場の生産が盛んになって、 労働者が集中してくるのですが、 雇用に対して住宅の供給が追いつかない状況で、 公共施設や、 道路整備、 衛生関係の改善も対応できないまま、 どんどん建物が建ち始めたと言われています。 最初の頃は図(a)のようだったものが、 だんだん図(c)のようになっていきました。 3階建て、 5階建てがだんだん建てこんでいきました。 一種のスプロール的な状況のなかで、 密度が上がっていったのではないかと思います。
1870年ぐらいから、 工場の生産が盛んになって、 労働者が集中してくるのですが、 雇用に対して住宅の供給が追いつかない状況で、 公共施設や、 道路整備、 衛生関係の改善も対応できないまま、 どんどん建物が建ち始めたと言われています。 最初の頃は図(a)のようだったものが、 だんだん図(c)のようになっていきました。 3階建て、 5階建てがだんだん建てこんでいきました。 一種のスプロール的な状況のなかで、 密度が上がっていったのではないかと思います。


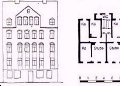
図8 初期の頃の2階建て住宅の外観とプラン
図9(a) 3階建て住宅の外観とプラン
図9(b) 4階建て住宅の外観とプラン
![]() 一番最初に建った2階建ての住宅は図8のようなもので、 真ん中に階段があって、 2戸がくっついているというタイプの住宅でした。 3階建て、 4階建てになっても、 基本的なパターンは同じだったようです。
一番最初に建った2階建ての住宅は図8のようなもので、 真ん中に階段があって、 2戸がくっついているというタイプの住宅でした。 3階建て、 4階建てになっても、 基本的なパターンは同じだったようです。![]() 図9が、 3階建て、 4階建てのタイプです。 同じように真ん中に階段があって、 両側に住戸があるという住宅です。 1880年代に、 3階建ての借家供給が始まって、 1890年代に4階建ての労働者向けの借家供給が出てきました。
図9が、 3階建て、 4階建てのタイプです。 同じように真ん中に階段があって、 両側に住戸があるという住宅です。 1880年代に、 3階建ての借家供給が始まって、 1890年代に4階建ての労働者向けの借家供給が出てきました。
南地区の改善活動
![]() 南地区(リンデン地区)は、 もともとハノーバー市とは別の村でした。 それが、 学校や道路などの公共負担が耐えられなくて、 ハノーバー市への編入の希望を出していたのですが、 断られ、 1920年にようやくハノーバー市に合併されました。 とたんに、 工場の景気がよくなくなった。
南地区(リンデン地区)は、 もともとハノーバー市とは別の村でした。 それが、 学校や道路などの公共負担が耐えられなくて、 ハノーバー市への編入の希望を出していたのですが、 断られ、 1920年にようやくハノーバー市に合併されました。 とたんに、 工場の景気がよくなくなった。![]() 1920年に市に編入されて、 ハノーバー市が整備を考えなくてはならなくなったのですが、 そのままの状況で第二次世界大戦の終戦をむかえます。 ここは戦災を受けなかったため、 戦後は、 被災した人たちが集まって、 一時ものすごい人口密度になりました。
1920年に市に編入されて、 ハノーバー市が整備を考えなくてはならなくなったのですが、 そのままの状況で第二次世界大戦の終戦をむかえます。 ここは戦災を受けなかったため、 戦後は、 被災した人たちが集まって、 一時ものすごい人口密度になりました。![]() その後、 その人たちが出ていって、 荒廃が進んでいき、 若い人たちや土地を持っていた人たちが出ていき、 家主さんも高齢化が進み、 ほとんど建て替え意欲がないままに1960年代になるという状況になりました。
その後、 その人たちが出ていって、 荒廃が進んでいき、 若い人たちや土地を持っていた人たちが出ていき、 家主さんも高齢化が進み、 ほとんど建て替え意欲がないままに1960年代になるという状況になりました。![]() その後、 非常に荒廃が進んだまま、 低所得者層と外国人労働者が集中してきたというのが1960年代でした。
その後、 非常に荒廃が進んだまま、 低所得者層と外国人労働者が集中してきたというのが1960年代でした。![]() そんな中で、 1972年にハノーバー市の調査が始まります。 その調査では、 50%の住戸にお風呂もトイレもなく、 セントラルヒーティングも13%程度の普及率で、 構造的に問題のある住宅が非常に多いことが分かりました。 居住者で見ると30%ぐらいが外国人で、 同じく30%ぐらいが年金生活者と生活保護世帯だったといわれています。 そのときの人口が1万3000人弱といわれています。
そんな中で、 1972年にハノーバー市の調査が始まります。 その調査では、 50%の住戸にお風呂もトイレもなく、 セントラルヒーティングも13%程度の普及率で、 構造的に問題のある住宅が非常に多いことが分かりました。 居住者で見ると30%ぐらいが外国人で、 同じく30%ぐらいが年金生活者と生活保護世帯だったといわれています。 そのときの人口が1万3000人弱といわれています。



図10(a) 高層高密化し人口を維持するプラン
図10(b) 従来の街区構成を尊重し、 中低層を基調とするプラン。 人口は10700人に減少後11300人までの回復を想定
図10(c) 従来の街区構成を尊重し、 中低層を基調とするプラン。 人口は9700人への減少を想定
![]() そのときに、 計画局の方で立てた案が、 この3つの案です。 図10(a)が、 高層化して1万3000人以上を維持するという案です。 図(b) (c)の案は、 どちらも既存の街区構成を残しながら、 中低層を中心にして、 人口が減って密度が下がってもいいから、 修復型の改善をしようという案です。 ただ、 図(b)の案は、 最初は密度が下がっても、 中心地区を高度利用していつかは多少は密度をのばしたいという案で、 図(c)の案は、 密度が下がったままでいいじゃないかという案です。
そのときに、 計画局の方で立てた案が、 この3つの案です。 図10(a)が、 高層化して1万3000人以上を維持するという案です。 図(b) (c)の案は、 どちらも既存の街区構成を残しながら、 中低層を中心にして、 人口が減って密度が下がってもいいから、 修復型の改善をしようという案です。 ただ、 図(b)の案は、 最初は密度が下がっても、 中心地区を高度利用していつかは多少は密度をのばしたいという案で、 図(c)の案は、 密度が下がったままでいいじゃないかという案です。![]() この3つの案で、 どうやって改善をしていくのかという議論が始まりました。 そのときに、 住宅の問題だけではなくて、 外国人の問題とか、 低所得者層の問題とか、 社会的な問題が非常に大きいということもあって、 フィジカルなプランを担当する計画局とは別に、 社会計画、 環境計画、 コミュニティ計画も含めた問題を議論する再開発局を新たに設置しました。
この3つの案で、 どうやって改善をしていくのかという議論が始まりました。 そのときに、 住宅の問題だけではなくて、 外国人の問題とか、 低所得者層の問題とか、 社会的な問題が非常に大きいということもあって、 フィジカルなプランを担当する計画局とは別に、 社会計画、 環境計画、 コミュニティ計画も含めた問題を議論する再開発局を新たに設置しました。![]() そういった中で、 週1回、 住民のフォーラムが毎週行われました。 それに対して、 市からの助成で建築家やプランナーといった専門的な人をプランニング・アドバイザーとして派遣して、 フォーラムの活動を支援しています。
そういった中で、 週1回、 住民のフォーラムが毎週行われました。 それに対して、 市からの助成で建築家やプランナーといった専門的な人をプランニング・アドバイザーとして派遣して、 フォーラムの活動を支援しています。![]() それとは別に、 市議会と住民のフォーラムをつなげるという位置づけの再開発委員会が設置されました。 市議会側と住民側のメンバーがそれぞれ半々ずつ入って、 市の計画局のプランを調整するという意味合いでの話し合いが行われました。 そういったことが、 相互に意見交換しながらやられていきました。
それとは別に、 市議会と住民のフォーラムをつなげるという位置づけの再開発委員会が設置されました。 市議会側と住民側のメンバーがそれぞれ半々ずつ入って、 市の計画局のプランを調整するという意味合いでの話し合いが行われました。 そういったことが、 相互に意見交換しながらやられていきました。

|
|
図11 最終案 |
![]() 基本的には、 街区の構成は変えていません。 ここで、 大きな問題となったのは交通問題です。 地区の西側に南北の幹線道路が通っていて、 道路によって分断されたような形になっています。 もう一つ、 東西に幹線道路が通っているのですが、 これを地下化するのかどうかということが一番もめたことでした。 それと、 地図上でTGAとかかれているのが駐車場ですが、 その配置についても問題となりました。
基本的には、 街区の構成は変えていません。 ここで、 大きな問題となったのは交通問題です。 地区の西側に南北の幹線道路が通っていて、 道路によって分断されたような形になっています。 もう一つ、 東西に幹線道路が通っているのですが、 これを地下化するのかどうかということが一番もめたことでした。 それと、 地図上でTGAとかかれているのが駐車場ですが、 その配置についても問題となりました。
![]() 基本的には、 市の方が幹線道路の地下化を検討し、 駐車場の分散配置と併せて調整していくことで、 1976年に、 日本でいうところの区画整理の事業計画図の基本となるフレームが作られました。
基本的には、 市の方が幹線道路の地下化を検討し、 駐車場の分散配置と併せて調整していくことで、 1976年に、 日本でいうところの区画整理の事業計画図の基本となるフレームが作られました。
![]() そのときに、 普通ですとできたプランを市議会にかけて法定計画にするのですが、 ここの場合にはあえて法定計画とはしないことを選択しました。 あとの細かいことは、 街区単位で決めていこうということになりました。 法定計画として一度決めてしまうと、 時間がたつにしたがって色々な修正をしていくときに、 その変更の法定手続きが必要になりますから、 もう少し柔軟にしようということです。
そのときに、 普通ですとできたプランを市議会にかけて法定計画にするのですが、 ここの場合にはあえて法定計画とはしないことを選択しました。 あとの細かいことは、 街区単位で決めていこうということになりました。 法定計画として一度決めてしまうと、 時間がたつにしたがって色々な修正をしていくときに、 その変更の法定手続きが必要になりますから、 もう少し柔軟にしようということです。

|
|
図12 ある地区のBプラン |
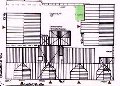
|
|
図13 改善計画例 |
![]() これまでの空間構造を残したまま、 高層化しないで行われていますから、 人口は減ります。 基本的には先ほどお見せしました3つの案のうち、 図10 (c)の案に近いもので、 人口は減ってもいいという方針です。
これまでの空間構造を残したまま、 高層化しないで行われていますから、 人口は減ります。 基本的には先ほどお見せしました3つの案のうち、 図10 (c)の案に近いもので、 人口は減ってもいいという方針です。

|
|
図14(a) 1972年の建物用途 |

|
|
図14(b) 1982年の建物用途 |
![]() 図14(a)が1972年の建物用途を示したもので、 (b)が10年後の1982年のものです。 緑が飲食店、 黄が手工業、 赤が商店です。 南北に通っている道路がお店がならんでいる通りで、 ここは比較的残っていますが、 その他は、 手工業、 お店などはだいぶ出ていっています。
図14(a)が1972年の建物用途を示したもので、 (b)が10年後の1982年のものです。 緑が飲食店、 黄が手工業、 赤が商店です。 南北に通っている道路がお店がならんでいる通りで、 ここは比較的残っていますが、 その他は、 手工業、 お店などはだいぶ出ていっています。
![]() 何故かというと、 10年も20年もかかるプロジェクトの中で、 いったい先行きはどうなるのか分からないといったようなことや、 拡張したくてもスペースがないといった問題とか、 マーケットの変化に対応できないといったことで、 多くの事業所が結局は出ていかざるを得ない状況だったからです。 ですが、 できるだけ以前に住んでいた人、 ここで働いていた人が住み続けられるということを基本に進められていた事業ではあります。
何故かというと、 10年も20年もかかるプロジェクトの中で、 いったい先行きはどうなるのか分からないといったようなことや、 拡張したくてもスペースがないといった問題とか、 マーケットの変化に対応できないといったことで、 多くの事業所が結局は出ていかざるを得ない状況だったからです。 ですが、 できるだけ以前に住んでいた人、 ここで働いていた人が住み続けられるということを基本に進められていた事業ではあります。
![]() 1992年に、 一応プログラムは完了しているのですが、 どんなものができているのかということについて、 スライドで見ていただきたいと思います。
1992年に、 一応プログラムは完了しているのですが、 どんなものができているのかということについて、 スライドで見ていただきたいと思います。