古代ギリシア案内[補説]ギリシア詩から西脇順三郎を読む
|
カリマコスの頭とVoyage Pittoresque
I
海へ海へ、タナグラの土地
しかしつかれて
宝石の盗賊のやうにひそかに
不知の地へ上陸して休んだ。
僕の煙りは立ちのぼり
アマリリスの花が咲く庭にたなびいた。
土人の犬が強烈に耳をふつた。
千鳥が鳴き犬が鳴きさびしいところだ。
宝石へ水がかゝり
追憶と砂が波うつ。
テラコタの夢と知れ。
II
宝石の角度を走る永遠の光りを追つたり
神と英雄とを求めてアイスキュロスを
読み、年月の「めぐり」も忘れて
笛もパイプも吹かず長い間
なまぐさい教室で知識の樹にのぼつた。
町へ出て、町を通りぬけて、
むかし鶯の鳴いた森の中へ行く。
重い心と足とは遠くさまよつた。
葉はアマリリスの如くめざめて
指を肩にさゝやく如く、あてた。
心は虎の如く滑らかに動いた。
あゝ、秋か、カリマコスよ!
汝は蝋燭の女で、その焔と香りで
ハシバミの実と牧人の頬をふくらます。
黄金の風が汝の石をゆする時
僕を祝福せよ。
「ギリシア的抒情詩」といっても、アビュドスにしろ、シケリアにしろ、カプリにしろ、ギリシア世界の周縁地域のはなしであった。それが、最後になって、やっと、ギリシア本土が舞台に登場する。

ejfedrismovVという遊び |
タナグラ(Tavnagra) — ギリシア本土の中心部、ボイオティア地方の古都である。詩の競演で、あのピンダロス〔前518(?)生-446以後没〕に打ち勝ったという伝説のある女流詩人コリンナの故郷。
しかし、西脇順三郎の関心は、1870年、この周辺の墳墓から素焼きの小像(terracotta)が多数発見されたことにある。この小像は「タナグラ人形(Tanagra figurine)」〔右図〕と呼ばれる。「タナグラ人形」については、「Heilbrunn Timeline of Art History」を参照。
しかし、西脇順三郎の主たる関心は、そのタナグラにもない。彼にとってタナグラは、「日本語に似ているから使った」(西脇セミナー第2回、p.37)にすぎない。
タナグラは、彼にとっては無何有郷(Utopia)の表象である。だから、そこに行き着くことは決してない。タナグラを目指しながら、途中下船せざるを得ない所以である。
先の「ガラス杯」が「天気」と呼応していたように、この詩は、西脇順三郎の詩の宣言であった「コリコスの歌」と呼応し、しかも、「ギリシア的抒情詩」を総題とする詩篇群の結びとなっている。

詩集『Ambarvalia』の冒頭 — 詩「コリコスの歌」の次頁、総題「ギリシア的抒情詩」のすぐ前 — には、カッリマコスの頭部として左図の写真が掲げられている。
カッリマコス(前310-240年頃)は、ヘレニズム期最大の学者詩人である。彼はアフリカのギリシア人植民地キュレーネー〔ここもまたギリシア世界の周縁である!〕に生まれた。苦学力行してアレクサンドレイア図書館司書となり(不思議なことに、図書館館長にはならなかった)、蔵書目録づくりに従事、『ギリシア文学総目録』(伝記資料を含む120巻)をつくりあげた。これは学問の基本図書となる。
彼はまた博学な散文作家であると同時に、著名な詩人でもあり、その詩は、ヘレニズム詩学の特色である学識と創造性の融合を示す卓越した典型であった。「彼はまた、ローマの最高の詩人たち、カトゥルス、プロペルティウス、そしてとくにオウィディウスに多大な影響を及ぼした」(ダイアナ・パウダー『古代ギリシア人名事典』)。
文学上の特徴について、高津春繁『古代ギリシア文学史』から引用しておこう。
彼は常に他の人と同じであることを好まず、彼の詩は完全な韻律を完全なしかも新奇な言葉で包まれなくてはならなかったのである。このために用いられたのが彼の人を絶した深い学識であった。<……>しかしこれらすべて頭脳の産物である。それは苦心鏤刻の結果であり、大胆な独創性にも多面性にも欠けていないが、それは石のように冷たく、感動の代わりに理性のみに訴えようとする。彼には真に燃え立つ詩神の火がない。彼は何人よりもギリシアをよく知っていたけれども、それは本の中のギリシアであった。彼の故郷はアフリカ〔キュレーネー〕であり、アレクサンドレイアであり、更にその中の図書館であった。彼のギリシアは実物ではない。これこそ正にアレクサンドレイア時代の典型的詩人を産み出すべき条件であった。詩は今や本の中以外に故郷がなかったのである。
(高津春繁『古代ギリシア文学史』p.193-194)

ところで、カッリマコスの頭部の像であるが、実際は、これは「セネカ」の名で知られた石膏デッサン用の胸像の頭部の写真である。この石膏の原型は、右図である。この像の詳細については、「Museo Archelogico Nazionale di Napoli」を参照。画家をめざしたことのある西脇順三郎にとっては、これは馴染みの石膏像であったはずだ。
研究者(例えば新倉俊一)は、西脇順三郎を故郷喪失者カッリマコスに近づけようとして、上の写真の図像を重視する。また、理知によって詩を書いたという点で、西脇順三郎とカッリマコスとの間に共通点を見ようとする研究者は多い。
しかし、理知によって詩を書いたという点では、カッリマコスと同時代人で、しかもカッリマコスとはまったく対蹠的に考えられているテオクリトス〔前3世紀前半〕も同類であって、それがヘレニズム期のひとつの時代的特徴といってよかった。むしろ、西脇順三郎がカッリマコスに見たものは、そのエピグラム詩の凝縮した表現ではなかったのかとわたしは思う。
エピグラム詩は、「物に寄せて歌う」ことを原則とする。西脇順三郎の「ギリシア的抒情詩」の大部分〔あるいは全部といってもよい〕が、物を題名にしているところにも、エピグラム詩の影響がうかがえる。
また、物に寄せて歌うことは、詩を絵画に近づけることになる。西脇順三郎がイマジストとみなされるのも、エピグラム詩の影響と考えられる。そして、今、「Voyage Pittoresque」とは、「絵画的な旅」の意にほかならない。
タナグラ、カッリマコス、アイスキュロスと、ギリシア的なものがちりばめられているが、作者の勘違いがこの詩の中にも見受けられる。例えば、「『アマリリス』というのは、僕の好きなギリシヤの野原に咲くそうです」(西脇セミナー第2回、p.37)というのは、思わず信じそうになるが、真っ黒な嘘である。
アマリリス〔学名 Amaryllis belladonna)は南米原産の観賞植物。ヨーロッパにいつごろ渡ったのかわからないが、古代のギリシア人やローマ人が知っているはずがない。
ただし、アマリリス(Amaryllis)という言葉は、ウェリギリウス『牧歌』に、牧人の娘の名前として出てくる(I-5, 30; II-14, 52; III-81,; VIII-78, 79, 102; IX-22)。ウェルギリウスの前には、テオクリトス『牧歌』に、ニンフの名前アマリュッリス(=AmarullivV)として出てくる(III-1, 6, 22; IV-36, 38)が、このニンフの詳細は不明である。この語は、ギリシア語 ajmaruvssw〔「輝く」「閃く」意〕からつくられた名前とされる。これが後世、南米産の花の名前に採用されたのであって、花が先にあったわけではない。
しかし、アマリリスはこの詩において2回登場し、しかも時間の推移を示す重要な役割を演じている。すなわち、第 I 章においては、アマリリスの咲く夏(5/6月)。そして、アマリリスはヒガンバナ科の植物であるので、花が咲き終わってから葉が出る。第 II 章は、「葉はアマリリスの如くめざめ」る時季に移る。
しかし、ありもしないアマリリスによって時間の推移を示そうとしたために、その他の小道具も季節感を鮮明にしがたい。
例えば第 I 章の「千鳥」 — 「千鳥が鳴く」とどうして「さびしい」のだろうか。それは、ひとつの文化伝統に根ざしているからだ。千鳥は、日本では、冬の渡り鳥である。
例のまどろまれぬ暁の空に、千鳥いとあはれに鳴く。
(『源氏物語』須磨の冬の段)。
第 II 章。日本における「みのりの時」は秋であり、これを表象するのは黄金なす稲穂である。ところで古代ギリシアでは、黄金なすのは麦の穂であり、季節は夏である(季語「麦の秋」。本当の秋には葡萄の収穫がある)。
〔「黄金の風が汝の石をゆする時」の出典として、西脇セミナー第2回の出席者(福田陸太郎)は芭蕉を挙げる。おそらくは『奥の細道』の「塚も動け我泣声は秋の風」を示唆したものであろう。しかし、本詩の場合、オルペウスの音楽に鳥獣はもとより木石も感動したという故事を挙げるべきであろう。
「このような歌によって、トラキアの楽人オルペウスは、森の木々や、獣たちの心を引きつけていた。岩石までもが、引き寄せられて、彼の後を慕っている」オウィディウス『変身物語』第11巻〕。
詩「雨」においては、ゼピュロス(西風)を南風に置き換えることによって、日本的な情趣と異国情調との融合に成功したが、この詩においては、歳時の違いに混乱させられる。
それにしても、この詩全体にただよう暗さは何であろうか。ギリシア世界でいうなら、冥府($AidhV)のほとりを想起させるがごとくである。
第 II 章は、後述するが、地下世界と切っても切り離せない関係にある。第 I 章の「千鳥」は、冬の鳥とは限らず、これを伝説の鳥 Charadriusだと解すれば、これは死を予兆する鳥である。また、犬は、死者の霊魂を導く代表的な霊魂導師(yucopompovV)である。
明るいだけがギリシアではない。ギリシアにも冥府はあるのだ。その意味で、この暗さは、ギリシア的ではある。
先ず、第 I 章から考える。

Circe Invidiosa(1892) |
「ギリシア的抒情詩」に対するわたしの解釈の原則は、いかなる観念連合にも包摂されない詩句を焙り出し、それを基にして全体を構想しなおす、ということであった。いかなる観念連合にも包摂されない詩句とは、第 I 章の中では、「土人の犬が強烈に耳をふつた」である。
ふざけた犬だ。尻尾を振らずに耳を振るとは!
耳を振るのは、蹄の割れた家畜のよくやる動作である。とすると、これは、尻尾を振る犬と、耳を振る家畜とを合成した西脇順三郎流のわるふざけに違いない。そう想定して、耳を振る家畜─尻尾を振る犬─煙─疲れて上陸─……と繋ぎ合わせてゆくと、見えてくる情景がある。『オデュッセイア』である。
トロイア陥落後、ギリシアの将兵はそれぞれ帰国する。オデュッセウス一行も帰国の途についたが、キュクロープス人の地に囚われ、一眼巨人ポリュペーモスにぶどう酒を飲ませて、眠っている隙にその一眼をつぶして危うく逃れたことは、「菫」の中で触れたとおりである。しかし、ポリュペーモスは海神ポセイドーンの子で、そのため海神の怒りをかうことになる(IX巻)。次いで風神アイオロスの島に着き、順風以外の風を封じこめた袋を与えられたが、まさに故郷イタケーに着かんとする時、彼の部下が袋を財宝と考えて彼が疲れて眠っている間に開いたために、たちまちにして逆風に吹き戻され、食人種ライストリューゴーン人の国で12隻の船の中で11隻を失い、次いで魔女キルケーの島に着く。
この島の海辺にまず私どもは、こっそりと船を乗りつけましたが、
<……>
そのおり此処へ船から降りて、二日と二晩ぶっつづけに、
疲労と苦悩に、ともども生命も縮まる思いで、寝ころんでいました。
en[qa d= ejp= ajkth:V nhi> kathgagovmesqa siwph/:
<..........>
e[nqa tovt= ejkbavnteV duvo t= h[mata kai; duvo nuvktaV
keivmeq=, oJmou: kamavtw/ te kai; a[lgesi qumo;n e[donteV. (X-140-143)
三日目の朝、オデュッセウスはあたりの様子を偵察するため、見晴らし場に登ってみた。すると、 —
目についたのは、遙かに道の広がっている大地から立つ煙が、
キルケーの館の内に、びっしり茂る木立や森のあいを通して見透かされる、
kaiv moi ejeivsato kapno;V ajpo; cqono;V eujruodeivhV
KivrkhV ejn megavroisi dia; druma; pukna; kai; u{lhn. (149-150)
オデュッセウスは思案した結果、まず一同腹ごしらえをしたうえ、2隊に分けて、籤引きで偵察隊を出すことにした。すると、エウリュロコスを隊長とする隊が籤に当たって、彼らは出発した。彼らがキルケーの館に近づくと。 —
その周囲には、山に棲む狼だの、ライオンだのが何匹もいた、
それらはみな魔法で彼女が人の姿を変えたものです、妖しい薬草を、
食わせまして。またこの野獣が人にはけして跳びかからず、
かえって長い尾を振り動かして、後脚で立ちじゃれるのでしたが、
その様子はまるで犬どもなどの、主人が宴会から帰って来たのを
取り囲んで尾を振るよう、主人がいつも犬の気をひく好物を持ってくるので。
ajmfi; dev min luvkoi h\san ojrevsteroi hjde; levonteV,
tou;V aujth; katevqelxen, ejpei; kaka; favrmak= e[dwken.
oujd= oi{ g= wJrmhvqhsan ejp= ajndravsin, ajll= a[ra toiv ge
oujrh/:sin makrh/:si perissaivnonteV ajnevstan.
wjV d= o{t= a[n ajmfi; a[nakta kuvneV daivthqen ijovnta
saivws=` aijei; gavr te fevrei meilivgmata qumou:` (212-217)
館の中からは、機を織っているキルケーの美しい歌声が聞こえてくる。一行は、館の内に招じ入れられ、勧められるがままに、魔薬入りのカクテルを飲んでしまう。
それから皆にこの粥を与えて、皆が飲み干すなり、即座に杖を
ふりかざして一同をうち打擲し、豚小屋に閉じこめてしまった、
その人々はもう豚に頭や、音声や、毛髪まで、姿形も
変わりましたのに、心だけは以前のまま変わらずに、確固としている
ものですから、閉じこめられてただ泣くばかり。
aujta;r ejpei; dw:kevn te kai; e[kpion, aujtivk= e[peita
rJavbdw/ peplhgui:a kata; sufeoi:sin ejevrgnu.
oiJ de; suw:n me;n e[con kefala;V fwnhvn te trivcaV te
kai; devmaV, aujta;r nou:V h\n e[mpedoV wJV to; pavroV per.
w}V oiJ me;n klaivonteV ejevrcato` (237-240)
〔キルケーの画像集は、「Circe, bebedizos inmortales.」が充実している〕。
事の次第は、ひとりあやしんで魔薬を飲まなかったエウリュロコスによって報告され、オデュッセウスはヘルメースに与えられた秘草によってキルケーの魔法をやぶり、この島で1年を過ごすことになる(X巻)。しかし、望郷の念ようやくつのり、帰郷の方途を聞くべく、キルケーの勧めで、オーケアノスの彼方なる死の国に至り、血の犠牲を捧げて死者の霊を呼び出し、預言者テイレシアースをはじめ多くの霊と語る(XI巻)。……
この詩「カリマコスの頭とVoyage Pittoresque」の第 I 章にただよう暗さと奇妙さは、かなり変容されているとはいえ、『オデュッセイア』のこの段を構図に採っている故であると考えてよかろう。
変容のひとつは、「僕の煙りは立ちのぼり」である。研究者によると、これの典拠は、ボードレール(Charles Baudelaire 1821-1867の『悪の華』の中の詩「La pipe」にみられる、「火と燃える私の口から立ちのぼる」という喫煙の煙の表現であり、ピエール・ルヴェルディー(Pierre Reverdy, 1889-1960)の詩集『風の泉(Sources du Vent』(1929)の中の詩「Nature Morte-Portrait(静物-肖像画)」にみられる「私の頭は煙草を吹かしている」という喫煙行為の表現であるという(澤正宏『西脇順三郎のモダニズム』p.154)。
しかし、ただに喫煙行為にとどまらず、第 II 章の「蝋燭の女」の「その焔と香り」と響き合い、さらに、「手」の焚香とも繋がっていることを見逃してはなるまい。
「追憶と砂が波うつ」という奇抜な表現も、宝石が海の表象であり(詩「皿」を参照)、水がかかって鏡のようになった宝石の、映像が追憶、写像が砂(浜)と考えれば、それほど難しいイメージではなかろう。〔「太陽」の註「カルモチン」参照。「太陽は我々の砂漠を照らした。我々はナポリ人のようにヒルネをした。カルモチンと神話との間に我々の心臓が波うった」とある〕。
問題は最後の「テラコタの夢と知れ」である。評者はこれを否定的表現と採るのであるが、はたして、そうか。
仮に否定表現として、「タナグラ」に何ら実体性・実在性はなく、上陸した「不知の地」も目的地ではないとき、いったい何を否定しているのか。詩「手」の中にあった「スミルナの夢」が何ら否定的な意味合いを持っていなかったことを考えるべきではないか。
夢みることは詩人の資質である、とキーツは言った(詩「手」参照)。
次に、第 II 章を考える。
初出は『尺牘』第5冊(昭和8年6月、椎の木社)であり、題名が「詩」になっていることが注目される。しかり、詩「手」の初出形の題名と同じである。両詩は、舞台が森であることにおいても等しい。既に触れたとおり、「手」の主題が焚香にあったごとく、本詩に「焔と香り」が登場している。匂いが「岩を燻ら」せたように、「黄金の風が……石をゆする」という似かよった表現をしている。
「蝋燭の女」は、オウィディウスの『祭暦(Fasti)』第3巻786に、「松明を戴く女神(taedifera dea)」と出てくる。ケレースのことである。
ケレース(Ceres)
ローマの古い豊饒の女神。その祭(Cerealia)は4月19日に行なわれ、大地女神(Tellus Mater)の祭(4月15日)と密接に関係している点から、ケレースにも地下神の性質があったことを知り得る。
エトルリア人がポルセンナPorsenna王に率いられてローマを攻めた時、大飢饉が生じ、シビュレーの本の神託によって、ギリシアのデーメーテールとディオニューソスの崇拝が前496年にローマに移入され、前493年に神殿がアウェンテイーヌスAventinus丘の麓にできあがった。この崇拝はギリシア的で、その大きな影響下にあり、ローマ古来の女神の姿は失われてしまっている。ケレースの地下神的要素は、死人の出た家では、この女神に犠牲を供することによって潔められる点にも認められる。
(『ギリシア・ローマ神話辞典』)
ケレースが「松明を戴く女神」と呼ばれる所以は、さらわれた娘のプロセルピナ Proserpina を捜し歩いたとき、アエトナ山の火口で松明に火をともし、夜も捜し続けたことにちなむ。
しかし、この添え名は、『祭暦』にしか見あたらないので、西脇順三郎はこの『祭暦』を参照したと考えられる。
『祭暦』にしか見られないものにもうひとつある。それは、娘を捜しあぐねたケレース=デーメーテールが、エレウシスにいたり、疲れてはてて腰を下ろしていたと伝えられる「悲しみ岩」(504)、ギリシア人が「笑わずの岩(ajgevlastoV pevtra)」と呼ぶ自然石に言及していることである。
ここに着いてはじめて悲嘆にくれる足を止めて冷たい岩に腰をおろしました。その岩をいまもケクロプスの子孫〔アテナエ人〕たちは「悲しみ岩(triste)」と呼んでいます。女神は青天井の下に何日間もかたくなに動かず、月夜にも雨水にもじっとしていました。 (高橋宏幸訳)
この、石と化したがごとき老女を動かせたのは、通りがかったケレウスの娘たちの思いやりのある呼びかけであった。
第 II 章15行目の「汝の石」を、カッリマコスの石像とのみ解釈するのは、単純にすぎよう。
しかし、いかに崇拝するカッリマコスとはいえ、これを女神ケレースと同一視するのは、さすがに憚られたのであろう。それが、「松明を戴く女神」ならぬ「蝋燭の女」であったのだが、これが第一義的には「SMの女王」を意味しようとは、さすがの西脇先生もお気づきでなかったようだ。
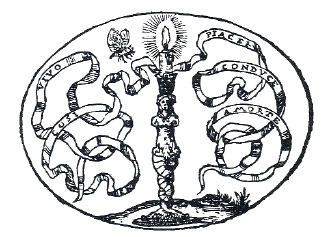
Gabriello Simeoni |
「蝋燭の女」着想のヒントは、これもまたエンブレムにあったのではないかと思う。右の図は、シメオーニ(Gabriello Simeoni)のインプレーサ〔impresa、フランス語devise、英語device。言葉(簡潔なモットー)と図像(同様に簡潔なイメージ)という二つの要素から構成される象徴的図案のこと。 — 伊藤博明〕であるが、この標題(モットー)は今は問題とするにたらぬ。問題は、この図案が「愛(アモール)のエンブレム」の中にさかんに採りいれられたことである(マリオ・プラーツ『綺想主義研究』参照)。
愛(アモール)というと、西脇順三郎から縁遠いように思うが、「コリコスの歌」を初めとして、「ギリシア的抒情詩」の諸詩篇に通底音として響いていることを忘れてはならない。そして、「カリマコスの頭とVoyage Pittoresque」は、「ギリシア的抒情詩」のしんがりをつとめると同時に、続く「拉典哀歌」の「ヴィーナス祭の前晩」への橋渡し、両者相俟って『Ambarvalia』〔穀物祭〕との統一性を保っているのである。
さて、第 II 章の細部をもう少しみてゆこう。
宝石の角度を走る永遠の光りを追つた 西脇順三郎は、「光線の美が文学の美である」という(「文学青年の世界」昭和7年10月)。次の「神と英雄とを求めてアイスキュロスを/読み」と同じく、「知識の樹にのぼ」る行為にほかならない。
その教室をすて、町をもすてて、森に入る。
その森は、「むかし鶯の鳴いた森」である。キーツの「小夜啼鶯に寄せるオード(Ode to a Nightingale)」を想起させる。
小夜啼鶯は、詩人に霊感を与える鳥である(『イメージ・シンボル事典』)。詩的霊感を与えるものの表象は、14行目の「ハシバミ」も同じである。
小夜啼鶯は、詩的霊感を与えるとともに、「小夜啼鶯に寄せるオード」においては、それは詩人が現世から逃避することをも表象する。そして、この森自体が、キーツの夢見る力が創りだしたものであった(詩「手」参照)。
しかし、それはすでに「むかし」のはなしである。詩的霊感を与えるものが、音楽的なもの=小夜啼鶯(聴覚の対象)から絵画的なもの=ハシバミ(視覚の対象)に移行していることに注目すべきであろう。
評者は、「教室」と「森」とに、「人為」と「自然」との対立をみようとする。しかし、それは性急であろう。森は、詩人の「夢みる力」がつくりだした詩的世界にすぎなかったし、今もそうである。現代の詩人が、「自然」に行き着くなど、望むべくもない。
心は虎の如く滑らかに動いた 研究者はシェリーの「Adonais」XXXIIの1行目、
A pardlike Spirit beautiful and swift —
を典拠に挙げる。そうかもしれない。しかし、なにゆえに豹ではなくて、虎でなければならなかったのか。
 虎の消息は、クテーシアス(前4世紀初期)の時代からギリシア世界に伝えられていた。しかし馴染みがないから、豹を比喩に用いる。これは旧約聖書の時代からの伝統である。
虎の消息は、クテーシアス(前4世紀初期)の時代からギリシア世界に伝えられていた。しかし馴染みがないから、豹を比喩に用いる。これは旧約聖書の時代からの伝統である。
ところが、インドまで遠征したという伝承のあるディオニューソスは、彼の乗る戦車を虎が牽くのである。
問題は、この知識が西脇順三郎にあったかどうかであるが、ローマ期のモザイク画には、明らかに虎の牽く戦車に乗るディオニューソスがある。また、オルペウスの音楽に聞き惚れる野獣の中に虎もいるのである(パレルモ国立博物館蔵、右上図)。しかも、そこでは、虎と豹とは、はっきり描き分けられている。
テキストはないかと求めれば、ウェルギリウス『牧歌』第5歌に、 —
ダプニスはアルメニアの虎(tigris)に引具をつけることを教えてくれた。
ダプニスは、バッコス祭の祭の踊りを先導し、
しなやかな細杖にやわらかな葉を巻くことを教えてくれた。
葡萄が支柱に美を添えるように、葡萄の房が葡萄の蔓に、
牡牛が群れに、作物が肥沃な畑に美を添えるように、
あなたは囲りのものすべてに輝きを与えた。
(V-29-34、河津千代訳)
ダプニスは(そしてオルペウスも)、バッコス=ディオニューソスの秘儀の先導者(祭主と言ってもよい)である。バッコス=ディオニューソスは(つまり、葡萄酒は)、豊饒祭の捧げ物である。しかし、豊饒は生殖=愛があってこそ成り立つ。ここに、豊饒の女神(ケレース=デーメーテール)、愛と美の女神(ウェヌス=アプロディーテー)、葡萄酒の神(バッコス=ディオニューソス)という三位一体が成立する。この三位一体の甘美さを現成させる者こそ、祭主としての牧歌詩人であった。このようなムーサ、葡萄酒、豊饒祭という習合の観念は、すでにテオクリトス『牧歌』第7歌に見て取れる。
パルナッソス山に住む、カスタリアのニンフたちよ、
かつてポロスの岩屋で老いたるキロンが
ヘラクレスに供した酒壺とはこのようなものだったのか。
またアナポス川のほとりで、巨岩を船に投げつけたあの荒くれ羊飼ポリュペモスを
洞窟で足取り軽い舞に誘ったのは、このような美酒だったのか。
ニンフたちよ、あなたがたがあのとき収穫の女神デメテルの祭壇のかたわらで
混ぜ合わされたのは、そのような飲み物ではなかったか。
(テオクリトス『牧歌』第7歌148-154、古澤ゆう子訳)
Nuvmfai KastalivdeV Parnavsion ai\poV e[coisai,
a\rav gev pa/ toiovnde Fovlw kata; lavinon a[ntron
krath:r= =Hraklh:i gevrwn ejstavsato Civrwn;
a\rav gev pa/ th:non to;n poimevna to;n pot= =Anavpw/,
to;n kratero;n Poluvfamon, o}V w[resi na:aV e[balle,
toi:on nevktar e[peise kat= au[lia possi; coreu:sai,
oi|on dh; tovka pw:ma diekranavsate, Nuvmfai,
bwmw/: pa;r DavmatroV aJlwivdoV; .....
ここにいうニンフたちは、葡萄酒を割る水であると同時に、ムーサたちにほかならないのである。
ハシバミの実と牧人の頬をふくらます ケレースは豊饒の女神であるから、ハシバミの実をふくらませ、牧人はそれを食べて頬をふくらませる。同時に、「頬をふくらませる」には、詩をうたう、笛を吹く意も重なっている。西脇順三郎にとってそれは、角笛を吹くことでもあった(序詩「コリコスの歌」参照)。
黄金の風が汝の石をゆする時 もしも西脇順三郎がギリシア詩に忠実であれば、ここの「黄金の風」はゼピュロス(西風)に違いない。ゼピュロスは「黄金の髪の」という添え名をもつ神であり、何よりも、孕ませる力を持った風である。そして、西脇詩において、頭=脳髄は、つねに詩を受胎する器官にほかならなかった(詩「栗の葉」参照)。さらに、西脇順三郎はこう言っている。「大理石の上に僕の頭が変な形になるというのは、僕はいつも自分の頭の形を子宮の形だというんだ」(西脇セミナー第2回、p.32)。
「石をゆする」は、詩人になろうとして虎になり、虎となってなお詩を吟ずるという奇談(「人虎伝」)の終わり — 則虎自林中躍出咆哮。巌谷皆震〔則ち虎林中より踊り出で咆哮す。巌谷皆震ふ〕 — を思い起こしたい。
神話学の教えるところでは、コレー(Kovrh)〔=ペルセポネー(Persefovnh)〕─デーメーテール(Dhmhvthr)─ヘカテー(+Ekavth)は、「あきらかに女性だけが農耕の秘術を会得していたころの同一の女神の三面相を示すもので、それぞれ処女と成熟したニンフと、老女に対応する。コレーは青い麦、ペルセポネーは実った麦の穂、ヘカテーは刈り入れを終わった麦 — 英国の田舎あたりでいう「老婆(carline wife)」にあたる」という(グレイヴズ『ギリシア神話』p.139)。つまり、それは、女の一生の「めぐり」であると同時に、四季の「めぐり」をも表象するものである。
この「めぐり」という言葉の重要性は、デーメーテールの神話伝承をみれば一目瞭然であるが、とくにウェルギリウス『牧歌』第4歌が重要に思われる。おそらくは、西脇順三郎が鉤括弧をつけて強調したのも、この語の重要性を示唆しているのかもしれない。河野千代も、この第4歌に長い解説を付している。
彼〔ウェリギリウス〕はまず、「シキリアの詩の女神たちよ、いささか大いなることをうたおう」と、彼にしては珍しく昂然たる姿勢でこの詩をはじめている。「シキリアの詩の女神たち」とは、彼がそれまで手本にしてきた『牧歌』の作者シチリア島生まれのテオクリトスに霊感を与えた女神たちのことである。つまり彼は、「わたしはこれまで牧歌的な詩を書いて来たが、そのようなひなびた詩がすべての人の気に入るわけではあるまい。これはポリオ〔前40年の執政官〕に捧げる詩なのだから、執政官にふさわしい堂々たる詩を書くことにする」と、牧歌を司る女神に断っているわけである。
次に彼は、黄金時代が戻ってくることを予言する。
<……>人間の社会は年々悪くなる一方であったが、クマエの予言集によれば、人間の歴史ほ百十年を一世紀として十世紀のあいだ悪い方へ向かい、第十世紀の最後まで来た時に再び最初の黄金時代に戻って、また新たに次の十世紀が始まるのだとされていた。そこでウェルギリウスは、すでに百年近くも続いているローマの内乱の時代を、最悪の世紀である第十世紀と見、それもブルンディシウムの協定によって終ったのであるから、黄金時代はすでに始まっているのだと、楽天的な調子でうたっているのである。
彼は、この黄金時代の支配者となるべき子を、早く、やすらかに生れさせたまえと、出産を司る女神に祈る。そして、その子によってこの悪しき世がどのように変ってゆくかをうたう。その子が生まれても、急には黄金時代の全盛期にはならない。その子の揺り籠である大地は、最初、つつましい花々を至る処に咲かせるだけである。その子が這いまわるようになれば、蛇や毒草をなくして危険から守り、香り高い木々を生えさせる。つぎにその子が青年になった時には、大地はサートゥルヌスの治世にそうであったように、耕さずとも豊かな実りを与えるようになる。ところが、その時にはまだ人間の方に第十世紀の悪徳が残っていて、大地の与える実りに満足せず、耕したり、戦ったり、冒険を試みたりする。しかしその子が壮年に達した時には、この世は全き黄金時代になる。その輝やかしい時代は、ポリオが執政官である間に始まる、とウェルギリウスはいう。そうして、まだ生まれていないその子に向かって、「さあ、早く生まれ出て両親を喜ばせておやり。それから、目が見えるようになったらまず母を見て笑いかけておやり。それがおまえにできる最初のよいことなのだから」と呼びかけてこの詩を結んでいる。
(河野千代訳『ウェルギリウス/牧歌・農耕詩』p.98-99)
河野千代は、この詩が詩人カトゥルスの第64歌『ペーレウスとテティス』からヒントを得ていることを指摘し、ウェルギリウスが夢を託した「その子」とは、ブルンディシウムの協定の果実である「平和」そのもの、あるいはその平和をもたらす神の力の象徴である、と結んでいる(p.103)。
西脇順三郎の歴史認識、政治意識が問題にされることはほとんどない。彼はひたすら象牙の塔に閉じこもっていたと考えられている。そしてこの詩においても、牧歌的な世界に後退した叙情性を指弾し、「当時、モダニズム詩運動の創作・理論の両面における中心的存在であった西脇順三郎が、この詩集刊行後、この両面における活動、とくに詩作を衰えさせていった原因」を、この詩にみようとさえする(澤正宏、p.153)。
しかし、本当にそうであろうか。彼のみが時代の閉塞感に鈍感であったとは考えにくい。彼が、詩に過大な力を夢みたとしても、不思議はない。夢見るのは、詩人の資質である。
「このような時代よ」と、運命の女神(Parca)たちはその紡錘に、
声を揃え、心を合わせて呼びかけた。「めぐれ!」と。
(ウェルギリウス『牧歌』第4歌 46-47、河野千代訳)
しかし、時代がめぐるには長い時間を要した。『Ambarvalia』刊行後、彼は詩作の筆を断つ。彼が再び詩を書き始めたのは、14年後、戦争が終わって〔昭和22年〕からであった。
「ギリシア的抒情詩」の探求も、ついに一応の終わりをむかえた。テオクリトスの『牧歌』から、詩神への次の呼びかけをもって結びとしたい。おそらくは、西脇順三郎の意にもかなうはずであるから。
決してあなたがたを見捨てることはない。それというのもカリステから離れたら、人にとって
好ましいものは何もない。私はいつまでもカリステとともにあるだろう。
(古澤ゆう子訳)
kalleivyw d= oujd= u[mme` tiv ga;r Carivtwn ajgaphtovn
ajnqrwvpoiV ajpavneuqen; ajei; Carivtessin a{m= ei[hn. (108-109)
 Barbaroi!
Barbaroi!