第47話
有翼類のエローディオス(erodios peteinos)について
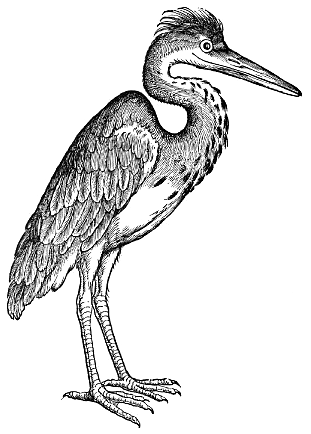
詩篇作者は言った、「エローディオスの住まいが彼らを導く」〔詩篇、第103章17〕。自然窮理家も主張した、— この鳥は多くの鳥にもましてきわめて賢い。例えば、ひとつの巣、ひとつの閨を有し、多くのねぐら(koite)を求めず、どこかに巣作りをしたら、そこで食事もし、寝みもし、死体をついばむこともなく、多くの場所に飛び回ることもない。寝床と食餌とはひとつところで行われる。
されば、あなたも、教区民の方よ、異端者たちのいる多くの場所を求めてはならない。あなたにとってねぐらは神の聖なる教会ひとつ、食事は天から降るパンひとつ、つまりはわれらの主イエス・キリストたるべし。死の日課には触れてもならぬ。それは、天上の香ばしきパンがあなたにあるためである、そして、異教徒たちのいる多くの場所を求めてはならぬ。
かく美しく、自然窮理家は鳥類のエローディオスについて述べた。
註
 ギリシア語の"ejrw/diovV"は、サギとりわけアオサギを指す。しかし「自然究理家」の編集者には、どんな鳥なのかわからなかったのであろう、わざわざ"peteinovV"「有翼類の」と付け加えた。有翼類でない"ejrw/diovV"がいるのかどうかわからないので、ここでは原語のまま「エローディオス」とした。
ギリシア語の"ejrw/diovV"は、サギとりわけアオサギを指す。しかし「自然究理家」の編集者には、どんな鳥なのかわからなかったのであろう、わざわざ"peteinovV"「有翼類の」と付け加えた。有翼類でない"ejrw/diovV"がいるのかどうかわからないので、ここでは原語のまま「エローディオス」とした。
七十人訳において、"ejrw/diovV"は3箇所(レビ記11:19, 申命記14:18, 詩篇103:17)に出て来る。このうち、最初の2箇所は、忌むべきものとして食べてはならないもののリストに入っている。ヘブライ語原語は「アナーファー」である。「アナーファー」という語が「どの鳥を指しているのかはまったく不明である。これが*サギではない*ことだけが、注釈者たちの意見が一致すると思われる唯一の点である」(『聖書動物大事典』p.209)。
"ejrw/diovV"が出て来るもう1箇所、詩篇103[102]章17のヘブライ語原語は「ハスィーダー」であるが、七十人訳ではさまざまに訳されている。 第4部 第9話の註を見よ。また、第3部 第19話、および、第4部 第4話の註をも参照せよ。
第4部 第9話の註を見よ。また、第3部 第19話、および、第4部 第4話の註をも参照せよ。
ウルガタ訳ではherodio, herodiusとされるが、不詳の鳥である。しかし、一般的には、コウノトリと訳されている。コウノトリのギリシア語は"pelargo&j"である。「七十人訳は、ヘブライ語のハスィーダーがコウノトリであることは認識していなかったようである。<……>コウノトリのように、エジプトとパレスチナ双方でよく見られ親しまれている鳥が、七十人訳で見落とされたのは不思議である」(『聖書動物大事典』p.402)。
「自然究理家」はエローディオスにキリストの姿を見る。とすると、旧約聖書において忌むべき鳥とされたサギであるはずがない。そのためであろう、ラテン語訳『ピュシオロゴス』は、エローディオスをfulica〔オオバン〕とする。しかし、確かな根拠があるわけではない。
エジプトでは、サギ(とくに青サギ)は聖鳥ベヌウである。 第7話「火の鳥」註参照。
第7話「火の鳥」註参照。
コウノトリは巣をつくる鳥の代表である。プリニウスは、コウノトリが毎年同じ巣に戻ってくる習性に注意をうながしている(『博物誌』第10巻63)。
画像出典、Konrad Gesner『Historiae Animallum』III。
博品社発行の『フィシオログス』の挿絵は、ラテン語版もドイツ語版もfulica=Blaäßhuhnとなっていることから「オオバン」(画像の出典は、Konrad Gesner『Historiae Animallum』III)である。
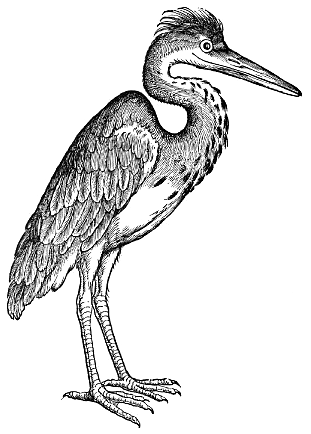
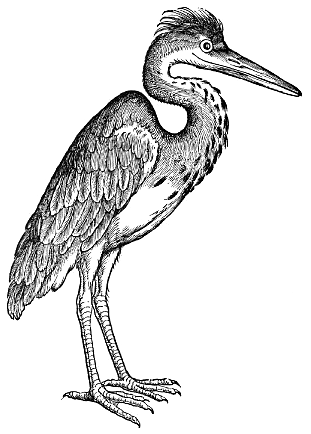
 ギリシア語の"ejrw/diovV"は、サギとりわけアオサギを指す。しかし「自然究理家」の編集者には、どんな鳥なのかわからなかったのであろう、わざわざ"peteinovV"「有翼類の」と付け加えた。有翼類でない"ejrw/diovV"がいるのかどうかわからないので、ここでは原語のまま「エローディオス」とした。
ギリシア語の"ejrw/diovV"は、サギとりわけアオサギを指す。しかし「自然究理家」の編集者には、どんな鳥なのかわからなかったのであろう、わざわざ"peteinovV"「有翼類の」と付け加えた。有翼類でない"ejrw/diovV"がいるのかどうかわからないので、ここでは原語のまま「エローディオス」とした。