古代ギリシア案内古代ギリシアの武器 |
[ 生活用具と武器]
紀元前397年、スパルタにおいて被支配階級の者を糾合して反乱を企てたキナドンは、同志に誘った男から、武器はどうするのかと尋ねられて答えている。
「人々が土地であれ木材であれ石であれ、これを加工する際に使うものもすべてが武器となりうるし、その他の技術の大部分が武器とするに充分な道具を持っている」( 第3巻 第3章 第7節)。
思いを致すべきは、次の二つの事実である。
1)武器が持てるのは、したがって、戦争に参加できるのは、貴族ないしは支配者階級の特権であったということ。
戦争が国民の義務になるのは、やっと、近代国家成立以後のことにすぎない。それまでは、戦争はまさしく、被支配者階級には「寄せてもらえない」栄誉であり特権であった。
(ついでに言えば、近代義務教育制度は、国民皆兵によって戦争に参加させてもらえるようになった有象無象を、一応はツブのそろった兵士に仕立てあげるための制度であったことを忘れてはならない。国民皆兵と義務教育とは、近代国家の二本柱である)。
2)戦争というものが、いつごろから始まったのかはわからないが、「人類」は、おそらくは、初めから戦争のための武器を手にしていたわけではあるまい。初めの人類が手にしていたのは、生活のための道具であって、武器ではなかったはずである。
しかし、動物を狩るための道具が、人間を狩るための道具に転用されるのには、それほどの時間はかからなかったであろう。こうして、射るための弓矢、突き刺すための槍、殴り殺すための道具(棍棒とか石斧とか)――これら、すべて生活のための道具が、武器との境界を曖昧にしながら、独自の発展を始めたと考えてよい。
そして、そういう戦争のための武器を独占したのが、支配者階級にほかならなかった。
以下、クセノポンあたりに登場する武器を中心に見てゆこう。
[ 攻撃用武器]
《殴る・斬るための武器》
斧は、「人間」が手にした、おそらく最も古い道具の一つであって、これが初めから武器として製造された形跡はない。しかし、後には打撃武器の代表となり、さらに後には、象徴として戦争司令官に授けられるようにもなった。(ちなみに、「王」という漢字は、大きな斧頭の象形文字である)。
戦斧(pelekys)
刃先を二つもった両刃斧。オデュッセウスはこれで木を伐る(『オデュッセウス』第5書 235行目)。
刃先が一つのものはhemi-pelekkonと呼ばれるところから見ても、両刃の斧の方が起原が古いことが知れる。〔ちなみに、クレタ島のラビュリントスの語源"labrys"は、おそらくはカリア語かリュディア語からの借用語で、両刃の斧を意味した。ラビュリントスには、この両刃の斧が祀られていたのである〕。
手斧(axine)
斧の一種であるが、はっきりしない。『イリアス』第15書 711行目では、pelekysとは異なる戦斧として登場する(呉茂一は「鶴嘴」と訳している)。『アナバシス』では、兵士が薪割りに使っている(第1巻 第5章 第12節)。
《 突き刺すための武器》
槍(enchos)の構造はきわめて単純で、柄(dory)と穂先(aichme)とから成る。doryは木材の意であるが、これが槍そのものをも意味するようになる。クセノポンでは、doryはもっぱら槍の意味で使われており、本文においては、「長柄」をこの訳語にあてた。
密集部隊による戦法では、槍はそれほど長くはなく、1.2〜2.0m(重さ0.8〜2.0kg)ぐらいなものであった。
ところが、この密集戦法を、戦車と飛び道具によって戦列を乱させる戦術がうまれた(イピクラテスの用兵など)。この戦術の対抗手段として、武器を長くして敵を威嚇し攻撃するという考えが登場し、槍は長くなってゆく。それでも、2.0〜3.0mぐらい(重さ1.5〜3.5kg)。
これ以後、飛び道具武器と長柄武器との対立は、部隊戦術の活性化につながり、さらに新たな武器の開発にもつながったという(市川定春『武器辞典』p.164)。
後に、アレクサンドロス大王率いるマケドニア軍の用いた長槍(sarissa)は、騎兵用のもので約3m、歩兵用のもので5m以上になる。ソケット式の穂先と石突が特徴で、突撃によって槍が折れても、持ち替えて使用することができるように工夫されていた。
他方、穂先を意味するaichmeもやはり槍そのものを意味したが、これは「鋭い」という語と同根で、ここからakon、これの縮小辞であるakontionという語がうまれる。こちらは、投槍を意味した。長さ70〜100cm。重さ1.0〜1.5kg。射程距離50〜100mという。りっぱな飛び道具である。
投槍の練習中に、あやまって殺傷した者の裁判の論争が Antiphonの第3弁論におさめられている。
クセノポンによれば、ペルシアの騎兵はpaltonという、やや小振りの槍を持っていて、これは投げるのにも適していたという。
ギリシアの騎兵隊とペルシアの騎兵隊とが激突したとき、ギリシアの騎兵はその槍(dory)を折ってしまったが、ペルシアの騎兵は、槍(palton)の柄がミズキの木でできていたので、折れなかったという( 『ヘレニカ』第3巻 第4章 第14章)。
《 突く・切るための武器》
刀剣は、本来は切るための武器ではなく、殴る・突くための武器であったという(わたしの敬愛する八切止夫などの説)。このことはホメロスを読んでも確認できる。
クシポス(xiphos)。
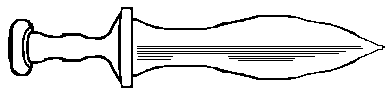
東地中海地方固有の鋭利な両刃の直刀で、束と剣身とが一体に作られ、刀身は木の葉状に中央部でふくらみ、根本では細みになっている。35〜60cm。重さ0.7〜1.2kg。
「両肩へと 白銀の鋲をうったる 青銅の両刃の剣を 投げかけて」は、ホメロスの常套句であるが、ホメロス(『イリアス』『オデュッセイア』)中65箇所に登場する「剣」は、すべてクシポスである。
xiphidion( 『ヘレニカ』第5巻 第4章 第3節)は、xiphosの縮小辞であるから、小型のxiphosを意味したのであろう。
マカイラ(machaira)。
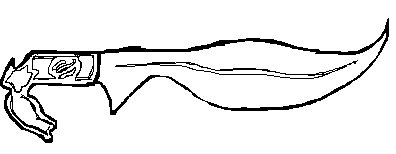
これも束と剣身とが一体に作られた剣であるが、こちらは片刃で、刀身が軽く彎曲している。
ホメロスでは、わずか3箇所にしか登場せず、しかも、クシポスに対する脇差しとして登場するが(『イリアス』第18巻 597)、実際は切ることを目的とした戦刀で、スパルタ兵が好んだといわれる。片手でも両手でも用いることができた。長さ50〜60cm。重さ1.1〜1.2kg。
歩兵や騎兵の兵種をとわず広く用いられたようで、片刃といえば、すぐにmachairaと結びつけられていた。
コピス(kopis)
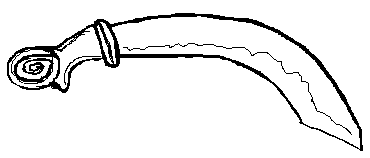
語源的には、「切る(kopto)」という動詞から派生したこの剣は、ギリシアの古刀で、これも束と剣身とが一体となった片刃剣であるが、彎曲した内側に刃先がある典型的な"S"字型の刀剣である。(画像では、下方が刃先になる)。
これの起原はギリシア独自のものではなく、度重なる侵略戦争によってもたらされた外来の刀剣であったらしい。そして、フェニキア人によって地中海世界の至る所に広められる。
《 射るための武器》
弓(toxon)。
矢(oistosまたはtox-euma)。
矢筒(pharetra)。
弓には、
1)カモシカの2本の角を握りのところで連結したものと、
2)まっすぐの木を両端でたわめたものとの
2種類があった。後者は、その作り方によって、1本の木材で弓本体をつくる単弓と、複数の材質から作る合成弓とに分けられるが、ギリシアの弓はすべて合成弓である。これは、射程をのばすための工夫であるが、いい材質の木材が欠乏していたという背景も考えられる。
弦は、編んだ馬の毛か雄牛の腸線が用いられていた。
矢は、葦か軽い木で作られた。射程距離100〜150mである。
矢筒は、背に負うのがギリシア風、左腰に提げるのがオリエント風。
弓兵は、戦場では部隊の前面に配置され、敵の気勢をそらせたり、本隊が突撃するまで、敵に損害をおわせる散兵戦に用いられた。したがって、部隊内での地位は低く、たいていはテッタリア地方からの傭兵によってまかなわれていた。
《 その他の飛び道具》
投石具(sphendone)。
石(petros)もりっぱな飛び道具である。
此方(こなた)のパトロクロスも 馬から地上へ 跳んで降りる、
左手(ゆんで)に槍をひっ抱え、片手には ぎざぎざとした角立った
石の塊(くれ)の、手がすっかり蔽いかぶさる 程のを掴んで、
しっかと身構え抛りつけたもの、長くは敵から引き退らねば、
投げた石とて徒らではなく、ヘクトールが車の手綱執りで、
音に聞こえたプリアモスの 傍腹の子の、ケプリオネースが
馬車の手綱を執るその額へ 鋭い石を撃ち当てたれば、
すなわち石は 両方の眉わのあたりを押し砕き、骨も耐らず、
両の眼が(押し出され)、地面へ、砂塵の中へと、まさしく
足の前に落ちれば、男は、筋斗(とんぼ)を切る軽業師そっくり、
立派な造りの二人乗りからどうと落ちると、命は骨肉(ほねみ)を離れた。
(『イリアス』第16書 733行目以下 呉茂一訳)
石が有用な武器であったのは、弓が貫通力をもって敵を殺傷するのと違って、弾丸の衝撃力によって敵を倒す武器であったからである。すなわち、弓(矢)は急所に貫通しなければあまり意味がなかったのに対して、石は、命中さえすれば致命傷を負わすことができたばかりか、腕や足に命中しても、その骨を砕いて戦闘不能に陥らせることができたからである。
投石の威力を増す武器が「投石具(sphendone)」であった。長さ100〜150cm。重さ0.1kg程度。形状はあたかも眼帯のごときもので、中央の石受けに石ないしは鉛弾を包み、両端を握りしめて頭上でふりまわし、加速度をつけたところで片方の端をはなす。
ロドスの投石兵は、ペルシアの弓兵の射程をも凌ぐほどだったとクセノポンは報告している(『アナバシス』第3巻 第4章 第16節)。たしかに、投石具による投石の射程は100〜150mと、弓の射程と変わらなかった。
[ 防御用武器]
防御のための武器(武具)といえば、何といっても楯がその代表である。
アスピス(aspis)
古代ギリシアの楯(aspis)は、プレ・ヘレニク時代の瓢箪形から、円形または楕円形に変化してゆくが、外側に曲面をつくり、平らな縁をつける点では一致している。丸楯は使用者の顎から膝頭までの長さ、楕円楯は口から足首までを隠した。丸楯の内側の中央に左腕を通す革輪、その先の縁に接して左手で握る握革が取り付けてあった。楕円楯は大きいので、握革のほかに、肩にかける吊革も取り付けられていた。
木製や枝編細工のものもあったが、ホメロス時代には雄牛の革を重ねて表面を板金でおおった。のちには青銅製が多くなった。
aspisから派生したaspistesという語が『イリアス』に見られるが、これは(楯を構えた)戦士の意味である。
ペルテ
こちらはトラキア起原の小型・軽量の革楯で、上部に半月形の切れ込みを入れることが多かった。これを持った兵士がpeltastes(本文では「軽楯兵」と訳した)で、 その機動力をいかして散兵戦に威力を発揮した。
軽装備のpeltastesに対して、完全武装の兵士がhoplites(本文では「重装歩兵」と訳した)で、その装備(hopla)の内訳は、
兜(kranos)
胸甲(thorax)
すね当て(knemides)
楯(aspis)
長柄(dory)
剣(xiphos)
で、総重量31Kg以上の重装備であった。
【参照】
武器の歴史については、 The Catapult Museum Onlineに詳しい。関連するページは、 Ancient Weapons、 Tension Artillery in the Greek Worldなど。
本ページでは取り上げなかったが、前400年当時の新兵器である Gastraphetesや Katapultosについては、上の Tension Artillery in the Greek World、および、 The Katapultosを見られたい。
 Barbaroi!
Barbaroi!