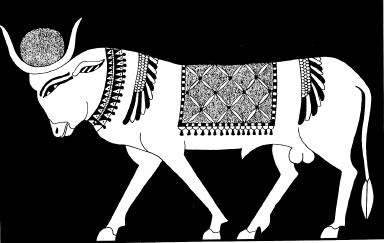
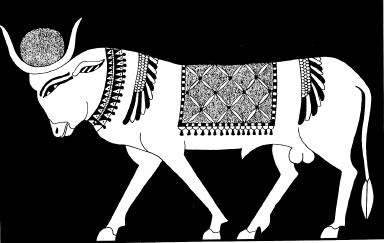
エジプトの月の雄ウシ神で、毎年、メンフィスで生贄とされた。のちにはウシル〔オシーリス Osiris〕と結びつけられて考えられ、その結果、マケドニア王朝期にはエジプトの神々は統合されて、オソラピスすなわちサラーピスとなった。さかりのついた雌ウシに月の光が射したときにアーピスが生まれ、そのためアーピスはウシの形になった。アーピスの額には三角形、横腹には飛んでいるハゲタカ、わき腹には三日月という、太女神をはっきりと象徴するしるしがついていたので、すぐにアーピスであると見きわめることができた。こうしたしるしのついた雄ウシが死ぬと、ミイラにして、雄ウシのための地下の大きな墓に埋葬した[1]。エジプトのすべての神々と同様、ミイラになったアーピスはウシル〔オシーリス〕のような存在になった。
Barbara G. Walker : The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (Harper & Row, 1983)
エジプトのメンフィスMemphisで崇拝されていた月の牡牛ハアーピのギリシア語名。
外観
アーピスは牡牛の形、あるいは牡牛の頭を持つ人間の形で表現されるが、ミイラの姿をしていることもある。
標識としては、角の間に太陽円盤をつけ、ときおり円盤の上に羽毛がそびえている(新帝国時代以降)。
アーピスの元素は土と水と火。その色は白と黒である。背中の黒い模様は羽を広げた禿鷹を思わせ、その羽が牛の横腹にたれ下がっている。
アーピスの神聖動物はもちろん牡牛である。
信仰
アーピスはメンフィスを起源とし、メンフィスでは第1王朝時代からアーピスが信仰されていたことが確認されている。
メンフィスにあるブタハ神殿の別館であるアピエイオンと、神聖雄牛のネクロポリスであるセラペウムでも礼拝されていた。
「アーピスの外出」は豊作を祈願する農耕祭儀で、王が主宰して盛大にとり行われた。
もう一つの重要な祭儀は、アーピスがヘリオポリスの牡牛ムネヴィスを訪問するというものであった。
しかし最大の祝祭は、アーピスの埋葬と、その後継者の即位のために行われた。新しいアーピスが選ばれる基準は、毛色の点も含めて、あまりよくわかっていない。
同族帥係
アーピスの母たちは特別な栄誉を受けた。この豊穣の神には単独の正妻はいなかったが、神聖雌牛たちのハーレムを持っていた。それらの雌牛は、『死者の書』に出てくる7頭の雌牛や、誕生を司るという7人の妖精や、聖書に見られる象徴的な7頭の雌牛と関連づけられる。とはいえ実際のところは、神のハーレムを満たしていたのはもっと多くの雌牛たちであったろう。
アーピスは魂と考えられ、やがてブタハの化身とみなされた。同様にして、ウシル〔オシーリス〕やセラピス、さらにアトゥムとも関係があった。
役割
アーピスはなによりもまず豊穣の神、すなわち「男女の神々の食卓を満たすもの」である。
アーピスは造物神ブタハに先んじて出現し、その魂となる。すなわち、「ブタハの先触れ」であり、「マアートをプタハに上げさせるもの」である。
プタハ=ソカル=ウシル〔オシーリス〕の結びつきを通じて、アーピスは葬儀の神々、とくにウシル〔オシーリス〕と関係を結ぶ。ウシル〔オシーリス〕は「西方の牡牛」の称号を持っている。アーピスヘの捧げ物は、殺されたウシル〔オシーリス〕のばらばらの手足と同一視される。ウシル〔オシーリス〕の手足を集めることから、アーピスは葬祭とさらに関係を深め、死者を背中にのせて墓へ運ぶようになった。
ウシル〔オシーリス〕=アーピスという神は、ギリシア時代にセラピスとなった。
のちの時代にアトゥム、ラー、ヘル〔ホルス〕と結びつけられたことにより、アーピスは太陽の側面を持つようになったが、「天の牡牛」として月とも関係づけられた。
ホルアーピスは王の近くにいて、戴冠式や聖年祭のときには、王とともに儀式に参加した。
この動物の行動を観察することから神託が生じた。
豊穣に関する非常に古い神話の数々は、アーピスをめぐる農耕祭儀の中に表現されている。
ウシル〔オシーリス〕と習合することにより、アーピスはウシル〔オシーリス〕神話群に入った。(『エジプトの神々事典』p.35。画像出典も同じ)
バーバラ・ウォーカーは、もちろん、アーピスのすがたに、細切れにされる聖王の姿を見ているのである。