
|
| 図15 桂坂地区マスタープラン(1983) |
![]() 当時アルパックには、 私より10歳ほど年長の道家駿太郎という、 今は岐阜の大学の先生をしている先輩がいました。 その人と一緒に、 京都の西にある桂坂のマスタープランを作りました。 図15がそれで、 1983年のニュータウン開発で、 私が28歳のときです。 全体の計画作りと、 1、 2号区の実施設計をしました。
当時アルパックには、 私より10歳ほど年長の道家駿太郎という、 今は岐阜の大学の先生をしている先輩がいました。 その人と一緒に、 京都の西にある桂坂のマスタープランを作りました。 図15がそれで、 1983年のニュータウン開発で、 私が28歳のときです。 全体の計画作りと、 1、 2号区の実施設計をしました。
![]() この計画を推進していたのは、 西洋環境開発で、 当時はまだ都市環境デザインという言葉もなかったのですが、 ここではまだ珍しかったコミュニティ道路を入れた住宅団地を作ろうということでスタートしました。
この計画を推進していたのは、 西洋環境開発で、 当時はまだ都市環境デザインという言葉もなかったのですが、 ここではまだ珍しかったコミュニティ道路を入れた住宅団地を作ろうということでスタートしました。
![]() 全体の計画では、 地区の真ん中の古墳を活かして「古墳の森」を作り、 バードサンクチュアリをその後ろに持ってきたのが特徴です。 後は歩車共存のコミュニティ道路を全体に取り入れたのが面白かったと思います。
全体の計画では、 地区の真ん中の古墳を活かして「古墳の森」を作り、 バードサンクチュアリをその後ろに持ってきたのが特徴です。 後は歩車共存のコミュニティ道路を全体に取り入れたのが面白かったと思います。
![]() 私が1、 2号区の実施設計を担当する中でやったことを紹介しますと、 当時京都にはなかったコミュニティ道路を住宅団地に入れるために、 維持管理をどうするかを考えたり、 関係機関の同意を得るために同じ形状の実験道路を作り、 消防車を走らせてみたりしたことです。
私が1、 2号区の実施設計を担当する中でやったことを紹介しますと、 当時京都にはなかったコミュニティ道路を住宅団地に入れるために、 維持管理をどうするかを考えたり、 関係機関の同意を得るために同じ形状の実験道路を作り、 消防車を走らせてみたりしたことです。

|
| 図16 桂坂の京風を意識した町並み |

|
| 図17 緑道(上)と中層集合住宅(下) |

|
| 図18 桂坂の中層集合住宅 |
![]() 戸建て住宅が並ぶ土地の端で変な形の土地が出て、 ランドマークになるような場所でもあったので集合住宅を建てることにしました。 建物の設計はたしか内井昭蔵さんだったと思います。 ただ集合住宅の設計が行われたときは、 私はすでに大阪に転勤になっていたので、 設計には関与していません。
戸建て住宅が並ぶ土地の端で変な形の土地が出て、 ランドマークになるような場所でもあったので集合住宅を建てることにしました。 建物の設計はたしか内井昭蔵さんだったと思います。 ただ集合住宅の設計が行われたときは、 私はすでに大阪に転勤になっていたので、 設計には関与していません。

|
| 図19 大久保開発計画(1989) |

|
| 図20 大久保の土地利用計画図 |
![]() 単にこうした計画図を描くだけでなく、 計画を実現するためのシステム作りが重要だと考えたのもこの頃です。
単にこうした計画図を描くだけでなく、 計画を実現するためのシステム作りが重要だと考えたのもこの頃です。

|
| 図21 JR大久保駅前の現況 |
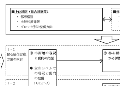
|
| 図22 用途地域の見直しの検討 |
![]() 用途地域の見直しの仕事をしたときには、 このまちでは都心居住の促進や臨海地区の土地利用転換の誘導、 住居系の用途の細分化が政策上の課題でした。 またそうした課題とは別に、 日々の生活の中で変わっていく建築活動の流れに対する見直しが必要だという4つの課題の中で方針を確立して、 新しい用途地域を指定していくわけです。 建築行為を誘導していくのも、 環境デザインの中では重要なファクターです。
用途地域の見直しの仕事をしたときには、 このまちでは都心居住の促進や臨海地区の土地利用転換の誘導、 住居系の用途の細分化が政策上の課題でした。 またそうした課題とは別に、 日々の生活の中で変わっていく建築活動の流れに対する見直しが必要だという4つの課題の中で方針を確立して、 新しい用途地域を指定していくわけです。 建築行為を誘導していくのも、 環境デザインの中では重要なファクターです。

|
| 図23 景観復興マスタープログラム |
![]() この仕事をしたときのキーワードは、 「地域景観イメージの共有」です。 規制誘導によってひとつの枠にはめるタイプの景観づくりは今までよくやってきたのですが、 景観復興の場合はいったん壊れてしまったものをどうするかからスタートしますので、 マスタープログラムでは「人の心にあるイメージの復興」が景観づくりの目的だと設定しました。 ですから、 地域景観イメージの共有(私はこの時コモンセンスという言葉を使いました)を強調した仕事です。
この仕事をしたときのキーワードは、 「地域景観イメージの共有」です。 規制誘導によってひとつの枠にはめるタイプの景観づくりは今までよくやってきたのですが、 景観復興の場合はいったん壊れてしまったものをどうするかからスタートしますので、 マスタープログラムでは「人の心にあるイメージの復興」が景観づくりの目的だと設定しました。 ですから、 地域景観イメージの共有(私はこの時コモンセンスという言葉を使いました)を強調した仕事です。
![]() この仕事は考えさせられる内容で、 私にとっても印象深い仕事のひとつでした。
この仕事は考えさせられる内容で、 私にとっても印象深い仕事のひとつでした。

|
| 図24 那覇市新都心中心地区の計画(1997、 1998) |
![]() ここの中心地区の計画作りを行っている最中です。
ここの中心地区の計画作りを行っている最中です。

|
| 図25 空間構成パターン |
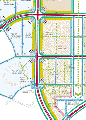
|
| 図26 外部空間形成の考え方 |
![]() 大型敷地の施主にはまとまって景観の約束ごとを作って下さいねと頼んでいますし、 小さい敷地の地主もそれなりに考えてもらいます。 お互いの敷地の中に通り抜けできるような道を作りましょうと提案しています。
大型敷地の施主にはまとまって景観の約束ごとを作って下さいねと頼んでいますし、 小さい敷地の地主もそれなりに考えてもらいます。 お互いの敷地の中に通り抜けできるような道を作りましょうと提案しています。

|
| 図27 快適な歩行者空間づくりのイメージ |
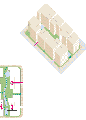
|
| 図28 共同化の提案 |

|
| 図29 那覇新都心界隈街区の誘導(1999) |
![]() それをどうやって実現するかというプログラムとして、 役所には連担建築物の指定(建基法86条)、 容積率緩和とか地区計画など、 都市計画の手法を提案しました。 また、 土地権利者には通路部分を負担していただかなくてはいけないので、 建築費用の負担減とか容積率緩和などの支援策を提案して、 共同化へのインセンティブがとれるように提案しました。
それをどうやって実現するかというプログラムとして、 役所には連担建築物の指定(建基法86条)、 容積率緩和とか地区計画など、 都市計画の手法を提案しました。 また、 土地権利者には通路部分を負担していただかなくてはいけないので、 建築費用の負担減とか容積率緩和などの支援策を提案して、 共同化へのインセンティブがとれるように提案しました。

|
| 図30 船場INSIDE-OUT(1978) |

|
| 図31 船場INSIDE-OUT(1978) |
![]() 今見ても、 そんなに悪いプランじゃないなと思います。 先ほど沖縄のプランを見てもらいましたが、 大学時代にも同じように街区の中に空間を作ることを考えていました。 ですから、 大学時代から同じようなアイデアを持って生きてきているわけで、 20年前と違うのはいろんな知恵がついてきたということぐらいです。
今見ても、 そんなに悪いプランじゃないなと思います。 先ほど沖縄のプランを見てもらいましたが、 大学時代にも同じように街区の中に空間を作ることを考えていました。 ですから、 大学時代から同じようなアイデアを持って生きてきているわけで、 20年前と違うのはいろんな知恵がついてきたということぐらいです。
![]() 結局私がやってきた仕事は、 要素技術の積み重ねとその繰り返しです。 仕事には終わりがないものだなと思います。 これから若い人が専門職を選んでいくわけですが、 仕事には終わりがないものですから、 単純に結果を決めつけないでいただきたいと思います。 これで私の話を終わります。
結局私がやってきた仕事は、 要素技術の積み重ねとその繰り返しです。 仕事には終わりがないものだなと思います。 これから若い人が専門職を選んでいくわけですが、 仕事には終わりがないものですから、 単純に結果を決めつけないでいただきたいと思います。 これで私の話を終わります。
 前に
前に  目次へ
目次へ  次へ
次へ