| ホーム | プロフィール | 間歇日記 | ブックレヴュー | エッセイ | 掌篇小説 | リンク |
| ← 前の日記へ | 日記の目次へ | 次の日記へ → |
| 98年5月中旬 |
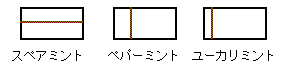 ペパーミントとユーカリミントは、直方体のケースの短辺と平行に鉢巻きのようにして破り目の帯が掛けてある。ところが、スペアミントはケースの長辺と平行に帯が掛けてあるのだ。しかも、同じように短辺と平行に掛けてあるペパーミントとユーカリミントも、よく見ると帯が掛けてある位置がちがう。最初のころは、「作っている工場がちがうのか? それとも、途中でデザインが変わったので、古いロットがまだ出回っているだろうか」などと思っていたのだが、いつまで経っても変わる気配がない。となると、これにはなにか理由があると考えるのが自然だ。
ペパーミントとユーカリミントは、直方体のケースの短辺と平行に鉢巻きのようにして破り目の帯が掛けてある。ところが、スペアミントはケースの長辺と平行に帯が掛けてあるのだ。しかも、同じように短辺と平行に掛けてあるペパーミントとユーカリミントも、よく見ると帯が掛けてある位置がちがう。最初のころは、「作っている工場がちがうのか? それとも、途中でデザインが変わったので、古いロットがまだ出回っているだろうか」などと思っていたのだが、いつまで経っても変わる気配がない。となると、これにはなにか理由があると考えるのが自然だ。
【5月19日(火)】
▼1987年の今日、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアが、寝たきりの夫を射殺してから自殺した――って、毎年書いてるような気がするなあ。死んだ作家の歳を数えるってやつだ。
思えば、当時おれはまだパソコン通信はおろか、コンピュータ業界に就職していながらパソコンを所有すらしていなかった。おれの経済状態ではとても買えないほど高かったし、おれの勤めている会社は大型汎用機とオフコンばかりやっていて、経営陣がパソコンの重要性に気づくのは恐ろしく遅かったため、仕事でパソコンに触れることすらまだなかったのだ。本格的にSFの話ができる知り合いも身近におらず(まさか同じ会社に大野万紀さんがいらっしゃるとは夢にも知らず)、作品そのもの以外のSF関係ニュースソースは「SFマガジン」と「SFアドベンチャー」くらいという状態であった。だからおれは、ティプトリーの死も、ずっとあとになってから「SFマガジン」を読んで初めて知ったのである。日本のSF関係者でこの第一報をキャッチしたのは、早くから海外のパソコン通信を駆使しておられた当時のSFマガジン編集長・今岡清さんだと知り、「すげえなあ。おれも早くパソコン通信やらなきゃなあ」などと思ったものである。
したがって、ずっと辿ってゆくと、ティプトリーが自殺したことがおれをのちにパソコン通信に引きずり込んだと言えないこともなく、その延長線上でここでこんなことをしていたり、「SFマガジン」やら「SFオンライン」やらに書いたりしているわけである。パソ通に入り浸って書評の真似事などしているうち、古沢嘉通さん、大森望さん、堺三保さん、坂口哲也さんといった方々と知り合った。
ある夜、古沢さんとチャットしていて、「(オクテイヴィア・E・)バトラーのゼノジェネシス三部作なら、持ってるから貸したげますよ。わし、当面読まないし」と言われ、お言葉に甘えてお借りした。翻訳家の先生に本をお借りするなどとはドキドキであり、汚さないようにヒヤヒヤしながら通勤電車で読んだものである。当時は暇だったから速攻で三冊読み終えて、古沢さんご自身はまだ読んでいないとおっしゃっていたのを思い出し、せめてものお礼代わりにと数枚のレジュメを付けてお返ししたところが、「読める日本語でまとめてあるのは珍しい」とお目に留まってしまい、ちょうど新体制で復活したばかりだった大森望さんの海外SF同人誌「NOVA MONTHLY」に載せてしまおうなんて話があれよあれよというまに進んでしまった。「海外SFの偉い人が大勢読んでるんだぞー」などと冷やかされながら何度かNOVAに書いているうち、これまたちょうど復活する予定だった「SFマガジン」の「SFスキャナー」レヴュアーにと、古沢さんや山岸真さんが推薦してくださったとおっしゃる。ひええええと現実感を喪失しているうちに、京都SFフェスティバルで、仮面ライダー・ブラックの役者((C)本阿弥さやか)さんのような方に紹介された。のちにSFマガジン編集長となられるのだが、当時は“編集後記で和久井映見との愛の物語を連載している人”としてしかおれは存じ上げなかった塩澤快浩さんである。いまは松たか子に乗り換えておられるのだから、月日の経つのは早いものだ。
――とまあ、こういうご縁で商業誌に書かせていただくようになったのだが、ほぼこれと同時進行していたご縁があって、こちらはSFとはあまり関係ない。おれがSFファンタジー・フォーラムやら、あちこちのホームパーティーやらパティオやらに盛んに書き込みをしていたころ、先日の日記(5月16日)にも登場した前野(いろもの物理学者)昌弘さんの奥様が関わっておられたNIFTY-Serveの「目のフォーラム」で、新しい試みがはじまることになった。一般利用者が書き込みできないリードオンリー会議室に数人のアマチュア・ライターでエッセイを連載してみようというのだ。パソコン通信を使った“電脳雑誌”の原初形態と言えよう。で、奥様がいろもの物理学者さんに「おもろいこと書きそうな人おらへんか?」(前野さんご夫妻は絵に描いたような大阪弁で会話なさる)と相談なさったところ、「おるおる」という話になり、おれに依頼が来たのだった。これも修行じゃとばかりにお引き受けし、あまりおたくな話題に走らぬよう、毎回のたうちまわるようにしてネタを絞り出しながら連載したのが、いまこのサイトに置いてある「迷子から二番目の真実」の第一期だという次第だ。「目のフォーラム」というのは、その名のとおり視力障害者の方々も多く読んでおられたフォーラムで、いろいろな意味でほんとうに勉強になったと思っている。ダウンロードしたテキストを音声に変換して読んでおられる方だっていたのだ。だから、「迷子から二番目の真実」の第一期は、そうした側面もある程度考慮して書いている。
このエッセイがまた、古沢嘉通さんはじめ、いろんな方の目に留まるようになり、見知らぬ方々からもご好評をいただいた。「このフォーラムはSFと関係ないから……」と意識して書いていながらも、フォーマットやノリは『狂気の沙汰も金次第』(筒井康隆)を拝借したに等しい。これも、じつは意外なところで意外な人が読んでいたことがあとになってじわじわわかってきて面白いのだが、その話はまたいつかすることにしよう。このときのエッセイが、いまこの日記に連なっているようなものである。
思えば、パソコン通信ではほんとうにさまざまな人とお近づきになり、知り合い、すれちがった。キー打ち合うも他生の縁だ。敬虔なる無宗教者のおれらしくない言葉遣いだが、気味が悪いほどに交友関係が広がったのは事実である。じつは、野尻抱介さんとはパソ通で何度もチャットしていたし、風野春樹さんがその膨大な読書量と蘊蓄で鳴らしていたのもよく知っている(笑)。パソ通ではお互いにハンドルや本名を使っていたりするので、インターネット時代になってから“知り合い直した”方もけっこういるのだ。あまり数え上げるとプライバシーの侵害になるおそれがあるのでやめるが、ホームページ同士の緩やかなリンク・コミュニティーの裏には、パソ通からのご縁も相当あるのである。
正体(というと化けものみたいでアレだけども)がわかって、いちばんびっくらこいたのは、なんと言っても小野不由美さんである。ある夜、シンプルなハンドルでチャットにふらりと現れた小野さんは、ちょっとおたくっぽい市井の本好きといったキャラクターで常連たちとたちまち打ち解けてしまわれた。夜っぴいて、よくバカ話をしていたものである。横浜のSF大会を機に“カムアウト”なさったときには、SFファンタジー・フォーラムのチャット常連の多くがひっくり返って驚いた。それ以前にご本名でメールを頂戴したことのあったおれは、「おや? もしや……」と思いはしたものの、珍しいお名前だが同名の人も少なからずいるだろうとさほど気にも留めていなかったのだ。メールの中でご家族のお仕事にさらりと触れた部分があり、「本好きなご家庭なのだな」と読み流していたが、いま思えば、そのメールには大きなヒントが隠されていたのだった。だが、けっして小野さんは嘘をついておられたわけではないのだ。巧妙に言葉が選ばれているだけで、書かれていることは、あとから読み直してもほんとうのことばかりだった(そのメールはまだ残っている)。まるで、男性作家だった時代のティプトリーの手紙のようである。
というわけで、めでたく話題はティプトリーに戻ってきた。もし、ティプトリーがいまあのような死にかたをしたとすれば、そのニュースには一夜のうちに――いや、一夜もしないうちに、日本中のSFファンに知れ渡ることだろう。十一年も経ったのだなあ、としみじみ思う。
【5月18日(月)】
▼“長者番付”とやらが発表されるたびに思うのだが、あれってプライバシーの侵害だよねえ。「ええーっ、小室哲哉って、十一億七千万しか税金払ってないの? 思ったより貧乏なのね」とか思われたら、大きなお世話というものである。小室氏がたまたまコンビニで98円のカップ麺とか買っていると、女子高生がひそひそと、「ほらほら、あんなのわざわざ安売りで買ってる。貧乏ってやーねー」などとほざいて、彼を指差す(それにしても、最近のガキはほんとに平気で人を指差す。おれの子供のころなんか、そんなことしたら張り飛ばされたぞ)。高額納税者を発表することに、プライバシーの権利に優先するどういう公益があるのかよくわからん。「なんであいつが載ってないのだ?」と発見させるための逆説的リストなのかもしれない。
あれが恒例行事として認められているのであれば、いっそのこと、納税者全員のランキングを発表してはどうか。紙のリストを配布しては電話帳何冊分にもなるだろうから、こういうときこそインターネットを使う。CD−ROMで配布してもよかろう。「おれは四千二百八十九万七千八百五十三位の高額納税者だ」とか、「お隣のご主人は二千六百万百三位よ」とか、みなが長者になったような気分で楽しめる――わけないか。
▼仕事で梅田地下オデッセイをしていて、ふと懐かしい人を思い出す。むかし大阪地下鉄御堂筋線梅田駅でおれはよく見かけた“草笛おじさん”である。小さなテレコをいつも片手に提げて、やたら巧い草笛を、信じられないような大音量で奏でながら悠然と徘徊していたヘンなおじさんなのだ。いったい彼にどんな目的やこだわりがあったのかは知る由もないが、殺伐とした地下鉄の駅で一服の清涼剤となって、鉄とコンクリートの風景に妙に溶け込んでいた。年齢不詳ではあったが、けっして若くはなかったから、ことによるともう亡くなってしまわれたのやもしれない。浮浪者然とはしていたけれども、飄々と、超然と、おじさんが吹く草笛は、「あんたら、なにをせかせかしてなはるか」と笑っているかのようで、賤しい姿に身をやつして地上に降り立った(地下なのだが)いたずら好きの聖霊の趣であった。きらきら、くるくると入れ代わる聖と俗を体現したような現代の周縁人が、人工物の狭間に妖気がわだかまるスポットにふらりと現われることがある。ムーミン谷のスナフキンみたいな感じだ。それが都会というものの魔的な魅力である。たとえば、三十年後にまったく変わらぬ姿で草笛を吹いているおじさんを駅で見かけたとしたら、おれは「あ、あのときのおじさんだ」とすんなり納得してしまいそうな気さえする。表現者なるものは、そうやって時を超え、何度も何度も、穢なくてきれいな“あの場所”から繰り返し湧き来たるものなのかもしれない。
【5月17日(日)】
▼おととい買ってきたワインを飲む。愛用している駅前のコンビニに突如酒が並ぶようになったのだ。免許を取ったらしい。ワインってのは厄介だ。開封したらできるだけ早く飲んでしまわねばならないから、ふたり暮らしのわが家では滅多に飲むことがない。母はビール党でワインはグラス半分程度しか飲まず、ふつうの大きさの瓶を買ってしまうと、おれが短時間でひと瓶近くを飲んでしまわねばならないのだ。それでは仕事に差し支える。小分けにして飲んでもいいのだが、開封して一日も経つと劇的にまずくなるから、それではわざわざ高い酒を買って飲む意味がない。酸化しはじめたワインを飲むくらいなら、「いいちこ」でも飲んでいるほうがよほどましである。ありがたいことに、最近は“飲みきりサイズ”の安ワインがけっこう出回っていて、先のコンビニにもたくさん売っていたので、そいつを買ってきたわけだ。ふつうの瓶入りに比べるとやはり味が落ちるけれども、酔わない程度の分量をジュース感覚で一気に飲んでしまえるのが便利だ。お値段も手ごろ。缶ビールを二缶飲むなら、ミニボトルのワインを一本飲むほうがいい。
通常サイズのボトルのデザインをそのまま真似た可愛らしいミニボトルをグラスを傾けながら眺めていると、ふと“SFバー”なるものを作ったら面白かろうという構想がやってきた。SFファンが二人以上寄ると、すぐこういうバカ話になる。
以前、堺三保さんやめるへんめーかーさんたちとチャットで駄弁っていて、「おたく同士が共同生活して老後を楽しむホームを作ろう」という話になった。資本はまったくないのであるが、SF者老人ホームという構想は非常に魅力的である。ホームの名前は“老人Zの家”とした。ただいま入居者募集中で、独身SFファン老人なら応募できる。めるへんめーかーさんはその後めでたく結婚なさり、残念ながら入居資格を失ってしまわれたが、よく考えたら夫君のほうがよほど濃いSFおたくなので、特例としてご夫婦で入居を認めることにしよう。どなたか世界的大ベストセラーでも書きそうなSFおたくをいまから仲間に引き入れておけば、実現の可能性もなきにしもあらずである。二百億くらい、ポンと寄付してくれるSFファン大歓迎だ。入居者全員の蔵書、ビデオ、CD、その他SFグッズなどを“老人Zの家”の併設ライブラリで展示・貸出しして金を取れば、雀の涙の年金でもなんとか食って行けるだろう。冗談抜きで、今後、こうした老人コミュニティーは増えてくるにちがいない。血が繋がっているというだけの薄弱な縁しかないエイリアンに疎まれながら面倒を見てもらわねばならんくらいであれば、同じ問題を抱え、趣味や世界観を共有する孤独な老人同士が助け合って生きるほうが、よっぽど豊かな老後を過ごせるであろう。
それはともかく“SFバー”であるが、カウンターには美人の女性型ロボットがいて酒の相手をしてくれなければならない。名前はもちろん“ボッコちゃん”である。酒の銘柄は、みなSF風にする。ボッコちゃんのお薦めは、清酒「星鶴」と「マイ・ウォッカ」だ。海外SFファンには、「白鹿」、大吟醸「楽園の泉」、「ブラディ・マリー博士」などが人気である。めるへんめーかー先生直筆ラベルの「めるちゃんワイン」、これもまた萩尾望都先生直筆ラベルの「美少年」なんてのもある。バーボン党は、「天才バーボン」(これは実在する)と「K・W・ジーター」(中身はただの「I・W・ハーパー」である)があればご機嫌であろう。「SFマガジン」というジンもあるし、「星雲海」なるそば焼酎もある。飲めない人のためには、アルコール分の少ない「一人で歩いていった下戸」、アル中寸前の人には「いつか下戸になる日まで」というのも用意されているぞ。仕入業者が放浪しているのでいつ入荷するかわからないのだが、運がよければ、宇宙ワイン「リースリング」が飲める。「ライスリング」と表記したラベルもあるが、同じ酒なのでご注意を。
なんだか、いくらでも新しい酒が考えられそうだ。だいたい、SFのタイトルには、そのまま酒の名前に使ってもよさそうなものがけっこうあるよね。「天の声」「夜の言葉」「完璧な涙」なんて酒があったら、いかにもうまそうだ。いいなあ。こういう酒場、どなたか開店しませんか。肝心の店の名は、やっぱり「狂乱酒場」かなあ。「タウ・ゼロ」なんてのもいいか。飲みはじめたら、止まらないにちがいない。
【5月16日(土)】
▼ひさびさにパソ通チャットをしていると、琉球大学の前野(いろもの物理学者)昌弘さんから、「あれは伸びる方が相対論的に見て健全です」とご指摘をいただいた。『ウルトラマンダイナ』に出てきた宇宙艇が超光速駆動らしきものを使う瞬間、びよ〜んと伸びるのは妙だと書いた98年5月9日の日記の話である。
いろもの物理学者さんのご指摘によれば、まずスーパーGUTSのアレは超光速駆動ではなく、“ネオマキシマ”なるパワーを用いた、あくまで亜光速(準光速)しか出せない設定のものだということだ(野尻抱介さんのサイトの掲示板でも「マキシマオーバードライブのことだろう」と複数の方からご教示をいただいたのだが、『ウルトラマンティガ』を観てないとわからないらしい)。さすが本職の物理学者(しかも、素粒子論・超ひも理論研究者)はきちんと観ておられる。でもって、「一瞬で亜光速に加速した場合、宇宙船が伸びてくれた方が相対論屋は納得する」とおっしゃるのだ。
ここまでで「なるほど」と納得した方はいいとして、おれと同じところで躓いた読者もおられるかもしれないので、いろもの物理学者さんの請け売りで説明してみることにしよう。
まず、光速に近づくと、運動している物体の長さが進行方向に対して縮むローレンツ短縮という現象は、どの相対論の入門書にも載っているし、多少なりともSFや科学に興味のある人なら「そういうものらしい」とはご存じのはずだから、ここでは細かいことは省略する(なにも光速に近づかなくとも、物体が観測者に対して運動していれば必ず縮んでいるのだが、低速では無視できるほどにごくごくわずかである)。さて、わかりやすいように極端な例として、長さが一光年もあるバカでかい宇宙船が、いま低速で飛んでいるとしよう。こいつが、一瞬で百分の一の長さにローレンツ短縮するような速度にまで、一瞬で加速したとする。宇宙船の長さは一瞬で一光年から百分の一光年になることになるが、“外から見て”そんな現象が起きたとしたら、宇宙船のどちらかの端が光速を超えて運動することになってしまうので、もちろん外からはそう見えない。長さ一光年の船は瞬時に加速しても、外から見ればまだ一光年の長さを保っているはずである。すなわち、その“瞬時に加速した”宇宙船が“外から見て”一光年の長さを保っている瞬間には、船は百光年の長さに引き伸ばされていることになる――というわけだ。なるほど、言われてみれば、じつに明解だ。こんな簡単なことに気づかないとは、おれにとって相対論はしょせん現象面だけを鵜呑みにした薄っぺらな“情報”にしかすぎないということだろう。いろもの物理学者さんくらいになると、おれが「あ、あのリンゴは熟れたら地面に向けて落ちてくるな」と思うのと同じくらいの感覚で、「あ、瞬時に亜光速に加速した宇宙船はその瞬間引き伸ばされているな」と思うのにちがいない。血肉に浸み透った“知識”になっているのだ。
「えー、でも亜光速だったらやっぱり縮むんじゃないの?」と思っている方は、おれと同じレベルである。つまり、こういうことだ。おれに対して亜光速で慣性航行(等速直線運動)中の宇宙船をおれが見ているのであれば、こいつはたしかに縮んでいる。だが、“亜光速で運動している”ということと、一瞬で“亜光速に加速する”ということとは、まったく意味がちがうのだ。特殊相対論で扱える領域の現象と、一般相対論を必要とする現象とのちがいだ。はっきり言って、特殊相対論は数学の苦手なおれにでもその骨子は十分把握できる(とおれが思っているだけかもしれない)理論だが、一般相対論となると、ほんとうに理解するには本格的に物理と数学をやらないとだめなものらしい。今回の亜光速宇宙船問題について、いろもの物理学者さんはおれにもわかりやすいように特殊相対論的な説明をしてくださったのだろうが、一般相対論に立てばよりエレガントな説明のしかたがあるのだろうと思う。こういう話が大好きな少年少女諸君は、SFファンにとっての相対論解説書の名著『銀河旅行と特殊相対論』『銀河旅行と一般相対論』(石原藤夫、講談社ブルーバックス)を読んで、明日のいろもの物理学者さんを目指していただきたい。そうすれば、おれやいろもの物理学者さんが、スーパーGUTSの宇宙艇がテレビ画面の中で伸びて“見える”ように映像表現されていること自体の苦しさを、半ばギャグ、半ば言葉の綾として棚に上げたまま話しているのがおわかりいただけるはずだ。ローレンツ短縮なるものは、あくまで物理現象として“縮んでいる”ことが数式(っつっても、中高生でわかる)から導かれるだけであって、それは光学的観察で単純に“縮んで見える”ということを意味しているのではない。じゃあ、それをほんとうに光学的に“見たら”どう“見える”のかは、先に触れた『銀河旅行と特殊相対論』をご参照ください。
さてさて、してみると、『ウルトラマンダイナ』は一見するよりハードな考証をしているのやもしれないが、この話にはオチがある。宇宙船が伸びるのはいいのだが――
いろもの物理学者「普通だと引き伸ばされたら死んでしまうから、死なないのはネオマキシマのパワーのおかげなんですなぁ」
冬樹「亜光速の等速運動に移ったら、また元の長さに戻って見えるわけですか?」
いろもの物理学者「のびきった宇宙船が現われますな。そののびきった宇宙船を元に戻すのも、マキシマのパワーのおかげっつーことで」
うーむ、ダイナはハードなのか、いいかげんなのか、よくわからない(笑)。
【5月15日(金)】
▼98年4月28日の日記で、山崎製パンの「まるごとバナナ」は、“食パンにマヨネーズを塗ってバナナをぐるぐる巻きにして食う”という、川原泉のアイディア夜食(?)のパクリではあるまいかなどと半ばギャグで書いたところ、先日尾之上俊彦さんから、ケーキで具を挟む“オムレット”形式の菓子ならむかしから定番として存在するのではないかとのご指摘をいただいた。なにしろおれはスナック菓子ばかり食っているから、本格菓子(なんてものがあるかどうかはともかく)には疎い。ああいう形のやつは、ケーキでも“オムレット”と呼ぶのか。玉子焼きのアレとどっちが先かは知らないが、なるほど、言われてみれば「まるごとバナナ」はオムレットの一種かもしれんと思えてきた。そこでネットを漁ると、「赤野パン・ケーキ教室ホームページ」の「ケーキのサンプルイメージ」に、“オムレット・オー・バナーヌ”という菓子の画像が載っていた。おお、「まるごとバナナ」に似ている――似ているが、ここでおれははたと考え込んだ。“挟んである”のと“ぐるぐる巻きにしてある”のとの決定的なちがいはどこにあるのだろう? この画像のバナナはどう見てもケーキに“挟んである”よね。ケーキでなにかを挟んであるのがオムレットなのだとしたら、「まるごとバナナ」はオムレットとは似て非なるものだということになるが、“包んである”もしくは“挟んである”のもオムレットに包含されるのならば、「まるごとバナナ」はオムレットだ。ううむ、難しい。
さらに“挟んである”と“巻いてある”とのちがいは那辺にあるものかとずっと考えていたのだが、どうも“挟んである”と“巻いてある”には明確な境界がないのではないかと思えるのだ。円盤状もしくは板状のケーキの片面をA面、もう片面をB面としよう。そのケーキでなにかをくるんでみる――
(1)ケーキの終端同士が触れ合わない場合、これは“挟んである”のか“巻いてある”のか? 一概に決定できない。中に入っているものが平ためのものか丸めのものかによって、印象が変わってくる。ケーキの大きさも関係してきそうだ。
(2)閉じようとする終端でA面同士あるいはB面同士が密着する場合、これはなぜか“挟んである”という感じが強くする。餃子のような閉じかたである。餃子の皮は具を“挟んでいる”か“包んでいる”のであって、“巻いている”と思っている人は少ないのではないか。前述の“オムレット・オー・バナーヌ”は、画像を見るかぎりではこのタイプだ。
(3)閉じようとする終端でA面とB面とが重なっている場合、俄然“巻いてある”と感じられる。「ケーキさえ大きければ、これからさらに二重、三重に“巻いて”ゆくつもりだぞ」という未来への展望と発展への意志が垣間見えるからであろうか。
今日コンビニで「まるごとバナナ」をじっくり観察して確認したのだが、「まるごとバナナ」は(3)なのだ。はたして、これはオムレットや否や?
さて、くだらない謎はともかくとして、おれは“オムレット・オー・バナーヌ”を見て、どうもこいつはフランス菓子らしくない印象を受けた。おれの偏見かもしれんが、フランス料理や菓子というやつは、素材を原形を留めぬほどに“加工”してしまう傾向があるように思われるのだ。なんでもかんでもペーストやらソースやらにしてしまう(話半分ですよ)。そのフランス人が、バナナを“まるごと”ケーキで挟む(巻く?)挙に出るのは意外ではないか。そこでおれは考えた。もしかすると、こいつはおふざけから発明された菓子なのではあるまいか。“オムレット・オー・バナーヌ”をじっと見ていると、「はて、なにやら、どこかで見たような光景であるな……」と妙な連想をしてしまわないか? 極悪なセンスの居酒屋などで、そのものずばりの卑猥な盛りつけをしたソーセージ料理や貝料理をギャグとして出していることがあるが、ひょっとして、“オムレット・オー・バナーヌ”もそれらと同じような“艶笑ギャグ菓子”だったのではなかろうか(フランス菓子の先生、怒らないように)。フランス人は艶笑小話などを大いに好むようだし、この手の料理の下ネタも苦笑いして楽しむ余裕があるような気がする。めちゃくちゃいいかげんな推測にすぎないけれども、「じつはこの菓子の起源は……」などと、したり顔でスナックの女の子にでも話してやったら鵜呑みにしてもらえるかもよ。調べればわかるのだろうけど、正解を知るよりバカな空想をしているほうが楽しいこともあるよね。
▼フランク・シナトラが亡くなった。おれはシナトラの北島三郎的親分イメージが好きじゃないが、歌手としての仕事は大好きである。大往生ではあるにしても、惜しい人を亡くした。あの声はすごい。声なんて空気の振動にすぎないと頭ではわかっていても、生身の人間の身体からあのような歌声が出てくることが、感覚的にはいまだに信じられない。晩年はさすがに声の艶が落ちていたのがおれですらわかったけれど、オリジナルの肉体は滅びても、その歌声はずっと聴き継がれてゆくにちがいないのだから、じつにしあわせな人である。かく言うおれも、カラオケのレパートリーから Strangers in the Night を外すことはないだろう。
| ‘To be is to do.’― Socrates. | ‘To do is to be.’― Jean-Paul Sartre. |
| ‘Do be do be do.’― Frank Sinatra. |
| ―― Deadeye Dick by Kurt Vonnegut |
【5月14日(木)】
▼おっと、例の“水の検査男”(98年4月17日、19日、21日の日記参照)たち、ちゃんと捕まってますな。5月7日付の毎日新聞ニュース速報によれば、『「アトピーに効く」と称して浄水器を高額で訪問販売していたとして、神奈川県警生活経済課などは7日、静岡市の浄水器販売会社社長ら8人を訪問販売法違反(不実の告知)と薬事法違反(承認前医療用具の広告禁止)容疑で逮捕した。同社は1995年から昨年9月までに、静岡、神奈川、長野、大分の各県を中心に、約2600人から8億円を売り上げていた』とのことである。『水道水の検査を名目に家庭を訪れ、水道水に含まれている塩素と反応する試験薬を入れて変色するのを見せた後、「この水は健康に良くない。浄水器をつければ大丈夫」などと勧誘していた』――というから、手口もいままでおれのところに寄せられた情報や風野春樹さんの証言と合致する。五万円で仕入れた浄水器を、二十万から三十万円で売りつけていたそうだ。おいしい商売やねえ。静岡、神奈川、長野、大分を中心に跋扈していたとあるが、大分だけずいぶん離れてるな。大分からの帰りにでも、京都のおれのところにやってきたのだろうか。もっとも、こいつら以外にも同じようなことをやってるやつがあちこちにいるにちがいないから、これで安心していてはいけない。おれには、これが最後の“水の検査男”だとは思えないのだ。人類が分を忘れて驕れるとき、必ずや第二、第三の“水の検査男”が、宇宙の彼方から……。
▼おれの子供のころは、インド人というやつは、なにかと言えばびっくりしていたものだが、さすがにびっくりするばかりでは損な役回りだと気づいたのか、昨今は世界をびっくりさせることに専念しているらしい。やれやれ。歴史はぶり返すのか。いまに「バイオもあるでよ」とか言い出すんじゃあるまいな。“In Gandhara, Gandhara, they say it was in India. Gandhara, Gandhara, 核の国、Gandhara.”――などとつまらん鼻歌が出てしまうが、ガンダーラって、いまで言えばパキスタンに位置するはずだよね。次はパキスタンかなあ……。“The dragon's come alive.”とか“It's the Asiatic Fever, burning, burning through. ”とか、ゴダイゴ・メドレーで鼻歌を唄ってると、なにやら縁起でもない展開ばかりが連想されてしまう。“What a cocky, saucy monkey this one is! All the gods were angered and they punished him...”おいおい、縁起でもない。人類ってのは進化の Dead End に突き当たってるのだろうか。“It's all in your decision. It's all in your decision...”
【5月13日(水)】
▼[NEWS FLASH]――ピー、ピピッピッ、ピーピー、ピピッ―― We take you now to Kermit the Frog for another fast-breaking news story.
「Hi ho, セサミストリート・ニュースのかえるのカーミットです。今日、私は火星に来ております。いま私が立っているこの通りは、デソレインション・ロードと呼ばれておりまして――いてて、あ、失礼――おい、AD、ちゃんと人払いしないか――えー、デソレイション・ロードと呼ばれておりまして、かつて“冬の時代”などと揶揄されていたのが嘘のように大勢の人々で賑わっております。デソレイション・ロードと申しますのは、この町の名でもあるわけですが、その奇想天外な歴史については、イアン・マクドナルドという作家がその名著『火星夜想曲』(ハヤカワ文庫SF)に詳しく記しております。太陽系のどの教科書にも載っておりますから、敢えて私が能書きを垂れるまでもないでしょう――あ、これです。こちらの銅像をご覧ください。えー、まちがってもハナ肇の銅像でないことは一目瞭然です。パソコンのキーボードに指を置いたまま、苦悩を湛えた顔で宙を睨んでいるこの銅像の人物こそ、『火星夜想曲』を日本語に翻訳するという偉業を成し遂げた、かの有名なヨシミチ・フルサワなのであります。フルサワの格調高い文体による紹介なくしては、日本の多くの人々はついにこの名作の香気に触れることはなかったでありましょう。1998年、フルサワはこの偉業によって、株式会社バベルが主催する第八回 BABEL 国際翻訳大賞新人賞を受賞しております。ご覧ください、この知性溢れる表情を! かつて水玉螢之丞画伯は、おのずから威厳の迸り出るフルサワの偉容を“マペット顔”と評し、われわれの文化に於ける最大級の賛辞を惜しまなかった、とはSF史の伝えるところであります。フルサワによって、日本語の小説として新たな命を得た『火星夜想曲』は、その後の日本のSFシーンにも大きな影響を与え、新たなる“夏の時代”へと……」
――というわけで、古沢嘉通さんから公開のお許しを得たので、おれも大いなる喜びと共にSFファンのみなさんにお伝えする。古沢さんが『火星夜想曲』の翻訳で BABEL 国際翻訳大賞の新人賞を受賞なさることになった。SFでである。すばらしいことだ。表彰式は5月30日とのこと。いやあ、めでたいめでたい。
え? なんですとっ! まだ『火星夜想曲』を読んでない!? あの、SFマガジン「ベストSF1997・海外部門」でダントツの一位に輝き、森下一仁さん主催の「ベストSF '97」投票・海外部門でぶっちぎりの一位に輝いた名作をまだ読んでいないですと? うむむむむ、ここはひとつ野田大元帥流に「死ね」と言いたいところだが、死なれては読んでもらえないので、万が一未読の人はすぐ本屋に走って、店になければ注文しよう。
1997年の大晦日、いかにも貧しげな母子三人が、ふらりと「冬樹書店」に入ってくる。
店主「いらっしゃい。ご注文は?」
やつれた女性「あの……文庫本を一冊ください」
店主「一冊……でいいんですか?」
女性「はい。945円しかないんです。三人で分けあって読みますから」
店主「…………」
女性「97年の翻訳SFを一冊だけ薦めてくださるとすれば、なにがよろしいでしょう?」
冬樹店主、店員に向かって明るく叫ぶ。
店主「はい、『火星夜想曲』一丁!」
みなさんは回し読みしないで買いましょうね(笑)。
古沢さん、ほんとうにおめでとうございます!
【5月12日(火)】
▼例によって、会社の昼休みに喫茶店で飯を食っていると――って、書き出しがいやに多いような気がするが、事実、喫茶店はネタの宝庫である。おれにとって喫茶店という場所は、女性とお茶を飲んだりするところではなく(たまにはそういうこともあるが)、人間ウォッチングを楽しむ場所にほかならない。面と向かって人と喋るよりも、赤の他人の話を盗み聞きするほうが得るところは大きい。われながら品のない趣味ではある。
おれがレジのそばの席で食後のコーヒーを飲んでいると、おっさんの三人連れが次々と金を払って出てゆこうとした。「三百円になりますぅ」と店の女性。最後のおっさん、財布の中の小銭をまさぐりながら、さらりとひとこと――「さんびゃくまんえんね」
どっしぇえええ。いまだにこんなことを言うおっさんが棲息していたのか! さすが大阪だ。嘉門達夫も歌のネタに使っているように(「アホが見るブタのケツ」)、小銭を勝手に一万倍するおっさんは、たしかにおれの子供のころはあちこちにいた。パン屋などで、駄菓子や菓子パンを買い食いするとしよう。「おっちゃん、これなんぼ?」「さんじゅうまんえん」――と、まさに嘉門達夫の歌のとおりの会話が交わされていたものだ(しかし、当時は三十円で菓子パンが買えたんだよなあ)。どうも関東の人は、初期の嘉門達夫のネタを“ギャグ”だと思っているらしいのだが、関西の子供にとってはあんなものギャグでもなんでもない。日常そのものであった。まあ、多くの人が成長と共に心の片隅に追いやってしまう少年少女時代のくだらないことどもを、重箱の隅をつつくようにして歌詞に保存した点は、彼の大きな功績であろう。彼の仕事は、一種の関西考現学と言ってもよいかもしれない。昭和三十年代生まれの人間が子供だった時代にたしかに存在した日常を、テクストとして記録しているのだ。五十年もしてごらんなさい。そういえば「アホが見るブタのケツ」なんてことを子供のころ言っておったなあと、おれたちの世代は懐かし涙にかきくれることであろう。メジャーになってからは、嘉門達夫のネタも全国的に通じるものに洗練されてきたが、おれは初期のやたら関西ローカルな歌詞がけっこう好きである。
それにしても、ひさびさに生で聞いたぞ。この“勝手に一万倍”は、あまり高額の支払いの際には用いられない。「五千六百七十円です」「ごせんろっぴゃくななじゅうまんえんね」などと言っているおっさんはあまりいない。十円単位、百円単位の、主に少額決済に適用される風習である。断わっておくが、「さんびゃくまんえんね」のおっさんは、けっしてギャグを言っているつもりではないのだ。ほとんど反射というか、挨拶というか、本能というか、第二の天性というか、こういうときには一万倍しなければならないのは社会人としての常識だとばかりに、さらりと言っているにすぎないのである。関西圏、とくに京阪神で育つと、なんらかの超自然力によって、この反射行動がイントロンにでも書き込まれるらしい。ブルドッグソースを媒介に感染するレトロウィルスが、キダ・タローのメロディーで活性化されるのだろうか。
この「さんびゃくまんえん」だが、あくまでなにごともないかのように絶妙のイントネーションで言ってのけなくてはならない。さらに、聞くほうもまちがってもギャグ扱いして笑ったりしてはならないのだ。「さんびゃくまんえんね」「はい、三百万円です」と、西に陽が沈むがごとくに受け流すのが正しい作法である。これをこなすには関西弁を完璧にマスターしなければならないので、関東人がウケようと思って真似したりしないように。下手にやると、ただの変なおっさんだと思われます。もっとも、かなり廃れている風習であるから、関西人がやったってやっぱり変なおっさんだと思われるかもしれないが……。
【5月11日(月)】
▼おれは腹の底では民主主義を信じていないところがある。建前としての戦後民主主義教育にどっぷりと浸かって、みずからも自分をそのように教育してきたが、親の教えは全然民主主義的ではなかったし、ふと社会を見渡すと、なるほど親の言うことももっともであると思えるほどに、ちっとも民主主義的でない世界が広がっていた。おれの親はまったくの無学であるがゆえに、建前としての民主主義教育の欺瞞をそれと知らずに見破っていたのだろう。彼らはみごとなほどにものを読まないから、彼らにとって自分の経験のみが唯一絶対の真理なのだった。おれの父親だった人物は勤め人であったから、さすがに“外の世界”を否応なしに見ざるを得ず、学のないなりに社会の建前と本音を知っていた。が、母親となると、これはもう“自分に知らないことがあることを知らない”というレベルであって、ある意味で非常にしあわせな人物である。彼女にとっては“なにが言われているか”はどうでもよいことで、“誰が言っているか”がすべてなのだ。およそ力というものを持たない彼女はそういう処世法で生きてきたし、怖ろしいことに、ただ生きてゆくというだけであれば、この方法はこの国で非常にしばしば実際に最も有効な処世法なのである。大愚は大賢に通じるとでも言おうか。そこには民主主義など成立する余地はない。おれは両親のそういう“愚かな正しさ”が子供のころから大嫌いで、両親を憎むと同時に日本社会を憎み、その反動として言葉の力と価値観の多様性の正義に憧れていった。しかし、現実はやっぱり現実なのである。言葉の非力さに打ちひしがれるとき、民主主義の理念を人類が生み出した最良の次善策(例によって“最善”なんてものはどこにもないのだ)と一応は信じている自分がバカみたいに思われ、プラグマティズムとしてのマキャヴェリズムに興味を覚えたりした時期もあった。
だが、厄介なことに、おれはマキャヴェリストには絶対なれないとわかったのだ。自分より知能の劣る者をうまく“操作”し得たときにおれが感じるものは、爽快感でも満足感でもなく、ただただ嘔吐でしかないと思い知った。おれのいちばん嫌いな諺は“嘘も方便”である。“嘘も方便”という考えかたの中にあるのは、胸の悪くなるようなエリート意識でしかない。おれは小沢一郎という人物が基本的に好きであるにもかかわらず、彼の方法論には不快なものを覚えるのは、このあたりに根がある。おれの大の宗教嫌いも、つまるところここに端を発するのだろう。嘘で円く収まることがわかっていても、王様は裸だとほざいて争うほうがいくらか健全だ。お互いにバカだ無能だと罵り合いつつ、お互いが発言する権利は崇高なものとして尊重し合うしかあるまい。人類にテレパシー能力がないからには、不完全な言葉で不完全なコミュニケーションを図ってゆくきわめて効率の悪いやりかたが、おれには最も快適だという結論に達し、いまに至っている。おれに唯一信仰らしきものがあるとすれば、それは“多様性は長期的には必ず勝つ”と信じていることくらいだろう。あの、いいかげんで非効率的で猥雑で薄っぺらいアメリカ合衆国という国におれが軽蔑と同時に敬意や羨望を抱いているのも、少なくとも理念の上では、あの国は多様性の力を信じているからだ。
とはいえ、ときどき民主主義の効率の悪さにつくづく厭になることがないでもない。「ええい、このバカどもめが!」などと、自分もそのバカのひとりであるのを棚に上げて、悪態をつきたくなるときがある。「ガイア!」とひとこと叫んで、バカ猿どもの醜い文明を地球ごと吹き飛ばしてしまいたくなるときがある(『マーズ』横山光輝・参照ね)。フィリピンのなんでもありの大統領選挙を見てると、かすかにそんな気持ちになるよね。これがほんとうにフィリピン革命のときに、あれだけのことを成し遂げた民衆なのであろうか。
思い出した。あれはマラカニアン宮殿陥落数日前のことであったかと思うが、おれは昼休みに客先で新聞を読んでいた。忘れもしない「修道女ら戦車を阻止」という見出しが目に飛び込んできたとき、驚くべきことが起こったのだった。不意に涙がこみ上げてきたのだ。危うく鳴咽を漏らしそうになるほどの不可解な感情の波が襲ってきたのである。これはおれらしからぬことだ。まったく、おれらしからぬことだ。おれはあわてて読むのをやめ、呆然とした。この奇ッ怪な感情はなんだろう? 目に涙を浮かべながらも、「これは危険だ」とおれの頭の中に赤信号が灯り、おれは即座に分析を開始した。たいていの感情というやつは、それ自身の正体をあきらかにできずとも、その来歴を分析することはできる。他人の感情は分析しにくいが、自分の感情であればかなり細かく切り刻んで標本にしてしまうことが可能だ。正体不明の感情に身を委ねることは非常に危険である。それはなにものかに操られる危険を孕むし、おれの大嫌いな宗教への第一歩でもあるからだ。「修道女ら戦車を阻止」――この平凡な見出しのどこに、おれの深層に働きかけるなにがあるというのか。キーワードは、おそらく“修道女”と“戦車”だろう。「銀行員ら戦車を阻止」ではなにも感じない。「修道女ら兵士を阻止」でもたいしたことはない。なるほど、物理的には無力で言葉に身を捧げている者の象徴として“修道女”があり、その対極に位置する存在の象徴として“戦車”がある。このレトリックのパワーが、たぶんおれの深層に潜むなんらかの幼児体験に作用したのだろう。この見出しをつけた記者は、単に事実を述べたにすぎないのだろうが、図らずも言葉の持つ象徴のパワーを増幅する組み合わせを作ってしまったのだな。この効果を意図していたのだとしたら、この記者はコピーライターになったほうが出世するだろう。
おや、いったい今日はなにが書きたかったのかな。どうやらおれは、「修道女ら戦車を阻止」体験を通じて、民主主義の危うさの正体をちらりと垣間見たような気がしていたらしい。まだ明晰に分析できるだけの準備が整っていないようだ。うまく言語化できないのだが、多様性を否定して成立する民主主義があり得るのではないかという疑念がおれの中に引っかかっているところまでは、うすぼんやりと確認できている。いつかこいつをおれの意識の明るいところに引きずり出し、切り刻んでホルマリン漬けにしてやりたいものだ。
| ↑ ページの先頭へ ↑ |
| ← 前の日記へ | 日記の目次へ | 次の日記へ → |
| ホーム | プロフィール | 間歇日記 | ブックレヴュー | エッセイ | 掌篇小説 | リンク |