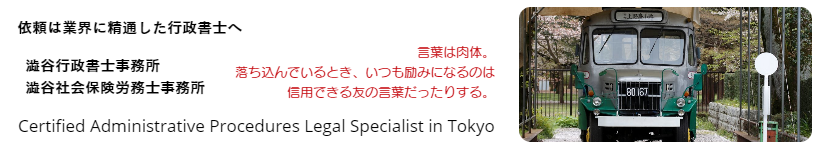応仁・文明の乱に見る京都の激変
平安遷都以来、時代の大転換をもたらした事件がぼっ発した。一四六七(応仁元)年に生じた応仁・文明の乱だ。室町幕府八代将軍足利義政の跡継問題が契機となり、十年にも渡る戦闘が展開されたが、その背景は少々複雑だ。将軍を補佐する管領家の畠山・斯波両氏の家督争いに、もう一方の管領家の細川勝元と四職のひとつである山名宗全の権力争いが絡み、事態は深刻を究めた。
細川方と山名方との抗争は、一四六七年の正月に畠山義就が上御霊神社の境内にこもっていた畠山政長を襲撃したことから始まった。その後、両軍合わせて二十七万人もの兵力を繰り出すまでに発展し、両軍は堀川を挟んで対峙する。その位置関係から細川方を東軍、山名方を西軍と称すようになった。なお、山名方が陣取った一帯が後に西陣と呼ばれるようになったのは有名な話だ。
戦いは西国の有力守護大名である大内政弘の大軍が上洛し、西軍に加担したことにより拡大の一途をたどった。とりわけ京都の焼亡はすさまじいものがあった。実に上京を中心に京都の三分の一ほどが戦火で焼かれている。
「汝や知る 都は野辺の 夕雲雀 上るを見ても 落つる涙は」
応仁・文明の乱を題材に書かれた「応仁記」にて、焼け野原と化した都を嘆き悲しみ歌われたものだ。
やがて抗争は膠着状態に陥った。さらに両軍の総大将であった勝元と宗全が相次いで死去したため、戦意を喪失した両軍の大名はそれぞれ領国へ戻ることになった。戦乱の最中、国内の国人や守護代などが守護大名の地位を脅かし始めたことも影響している。同時に下克上の風潮が強まり、それはやがて始まる戦国時代の前兆ともいえた。
さて、応仁・文明の乱はいわば中央の権力闘争であったため、中心的な戦場となったのは武家や公家が集住していた京都の北方である上辺だ。戦乱が始まったと同時に、人々は京の都から避難し始め、公家や有名な僧侶たちも京都を離れたことも、この乱の隠れた特徴でもある。公家による全国各地での小京都建設や、宮中文化の地方への普及をもたらしたからだ。
一方、商工業者が多く住んでいた京都南方の下辺はどのような被害を被ったのだろうか。残された史料からは特に焼亡したとの記事は見つかっていない。さほど大きな被害を受けることなく、京都における経済活動は維持されてきたようだ。でなければ、乱後の急速な復興は果たせなかったに違いない。それでも乱が生じる以前のような暮らしは不可能だったはずだ。
現在、京都の各地にて応仁の乱の遺跡を見ることができる。上御霊神社、鳥居の南側には「応仁の乱勃発地」の石標が建てられ、相国寺には義政の墓がある。さらに西陣の一角の路地には宗全邸跡の石標があり、町名を山名町としている。