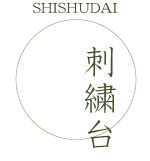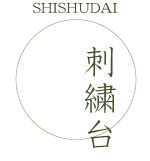
刺繍台について
刺繍台の形体ですが
江戸時代の職人尽くし絵の中にも
刺繍をしているところがでています。
それと比べても現在と少しも変わってないようです。
これから紹介します刺繍台は
「アトリエ森繍」特製の刺繍台です。
1)掛け糸を使いません。
2)帯用と着物用で、刺繍台の幅を変化さす事が出来ます。
生地の縦横のテンションを均等に張ることは
それなりに経験が必要です。
刺繍台から生地を外した時の生地の縮み具合を計算しながら
手加減をしなくてはならないからです。
例えばの話ですが、ダイヤルの目盛りを合わせ
ハンドルを回しながら生地を張ることが出来る
初心者もすぐに綺麗に生地が張れる。
そんな便利な刺繍台は無いものでしょうか。
ミシン刺繍の世界は進歩しているのですが・・・
▼刺繍台を分解したところです。貫き板に着物用をつければ着物、帯用をつければ帯に使えます。

- ▼かまちに脚をつけたところです。



- 仕様木材
別名カナダ桧とも呼ばれる北米産(カナダやアラスカ)の「ひば」です。表面は黄白色で、針葉樹の桧よりも硬めです。とにかく耐朽性が非常に高く、木の収縮も少ないです。肌目もかなり精密です。そしてこの米ひばの大きな特徴として、腐朽菌に対する殺菌作用や、特にシロアリに対する抵抗力を備えた「ヒノキチオール」と呼ばれる物質を含んでいますので、シロアリやゴキブリを寄せ付けません。またひばは「香りの木」とも呼ばれ、ひばの放つ自然の芳香は、アトピーや喘息を鎮める効果があり、さらにストレスを緩和する作用があると言われています。また防ダニ効果もありますので、赤ちゃんやお年寄りの健康にもとてもいいです。48mm×35mmの角材仕様
高さ 41.5cm
長さ 121cm
ひい棒からひい棒まで 81cm
布張り用金具の長さ 67.5cm
幅は、帯用が34cm、着物用が39cmです。
ぬきの長さ 73cm
ひい棒の長さ 73cm
生地幅52cmまで張る事が出来ます。右のひい棒から左のひい棒までが81cmありますので上前の柄がほぼ入ります。移動しなくても(張りなおさなくても)すみます。プロも使える仕様になっています。 75cmの刺繍台がありますが、これでは人間の体がひとつ入るほどです。少し狭すぎます。「ぬい紋」用でしょう。着物の刺繍には不向きと思います

- 着物地などの柔らかい生地はこうして直接生地を掛けていきます。金具部分にはキャップが付いていますので作業中はキャップをすると安全です。

- 帯地など生地の厚いものは針と針との間に糸を掛け其の糸を針に掛けるようにします。こうすると何回張り直しても、生地は痛みません。針から外すだけですので生地の脱着は素早くできます。