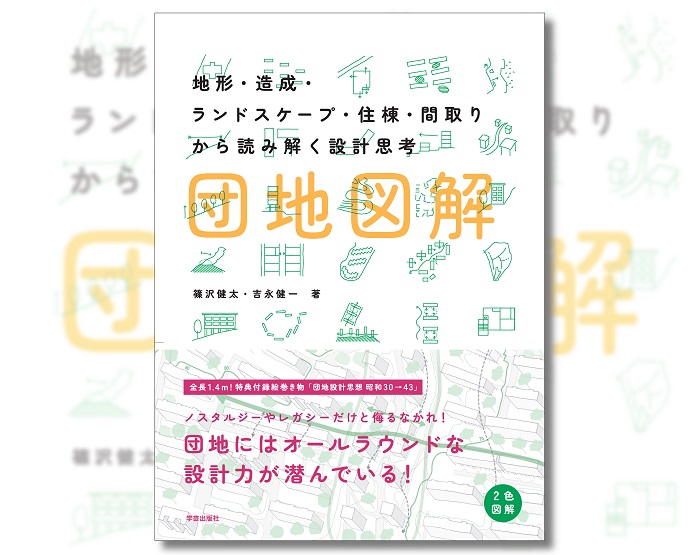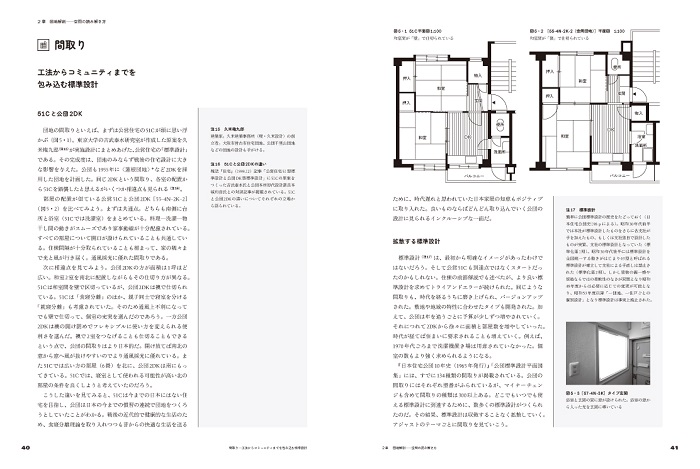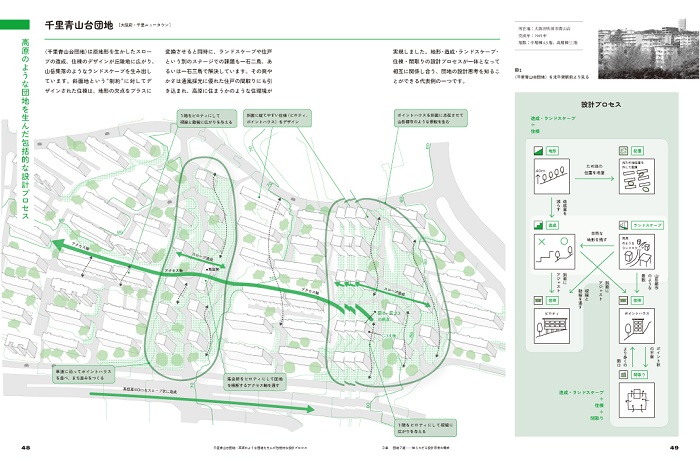団地図解
地形・造成・ランドスケープ・住棟・間取りから読み解く設計思考
篠沢健太・吉永健一 著
団地はどれも同じ…だなんて大間違い。地形を生かしたランドスケープ、コミュニティに配慮しつつ変化に富む住棟配置、快適さを求め考案された間取りの数々。目を凝らせば、造成から植木一本まで連続した設計思考が行き届き、長い年月をかけ育まれた豊かな住空間に気づくはず。あなたも知らない団地の読み解き方、教えます。
篠沢健太・吉永健一 著
アートディレクション:水内智英/デザイン:仲村健太郎
B5変判・140頁・本体3600円+税
ISBN9784761532352
2017/10/10
| ツイート |
評 : 藤村 龍至 (建築家・東京藝術大学准教授)
「拡大の時代としての戦後」を積極的に読む本
本書では団地を2つの観点で読んでいる。ひとつは団地をアノニマスなアーキテクトによる「設計物」として、そしてもうひとつは「歴史」としてである。
「団地」といっても本書が着目するのは「公団(日本住宅公団)」の整備した」団地である。公団が設立した1955年から宅地開発公団と合併し「住宅・都市整備公団」と名前を変える1981年以前の26年間、挙げられている事例はその前半に実現したものが多い。社会的にはいわゆる「55年体制」の確立以後、オイルショックまでの高度経済成長期にあたる。
本書によれば、同じ千里ニュータウンのなかでも大阪府営住宅の団地と公団の団地とでは設計思想が異なるそうだ。大阪府企業局の団地が新しい海外事例をそのまま取り入れるように設計されたのに対し(p.125)、公団の団地は漁村の集落のように、規範を守りながら徐々に進化するという(p.127)。新しいものを設計するというより、いわば「永遠の微調整」を続け、種を保存しながら進化するように漸進的に設計するのである。したがってプロジェクトひとつを取り出してもその意図するところがうまく見えないが、群として比較しながら読み解くことで設計者が何を改善しようとしたのか、何と闘っていたのか、背景が見えてくる。
巻末のURのOB中田雅資氏へのインタビューはそのような「寛容で創造的な設計組織像としての公団」という仮説の検証として読める。社内向けとはいえ「設計思想」として自社の設計物を自己分析しプレゼンテーションをしていたという点や「団地係」が細分化した専門家を繋いでコーディネートしていたという点など、「官僚的」と呼ばれる設計組織像とは大きく異なり、開放的で活発な協働がなされてた創造的な組織像が垣間見える。「官僚的」「均質」という紋切りの批判が見えなくしたかつての実態を再評価する視点は素晴らしい。
団地の設計に関して、社会的に記憶に新しいのは建築家による実験集合住宅だろうか。「公団」以後、1980年代から2000年にかけては建築家の起用が盛んだった。吉永氏も関わった「くまもとアートポリス」(1988-)や岐阜県営北方住宅建替(2000)などの例では「コミッショナー」あるいは「コーディネーター」という建築家を推薦する役割を任命された磯崎新が「目利き」として建築家を推薦する、というプロセスを経て山本理顕や妹島和世が起用され、それまでの規範に全く則らない革新的なプランの集合住宅が実現した。
これらの試みは団地の持つ均質性に対する批判から多様性に対するニーズに応えようとしたものだが、トップダウンのプロセスで実現されることもあって成果がむしろ均質に見え、むしろ標準設計をもとにして個別のプロジェクト毎にアレンジしていた時代のほうが却って多様性が感じられるのではないかという批評が本書の根底に感じられる。ポスト実験集合住宅の世代とも言える現在から見ると2つ前の世代の試みは新鮮に映るのは事実である。
ただ、1960年代の公団が組織として素晴らしかったのは事実だとしても、美化は危険だろう。1980年代に建築家が盛んに起用されたのは次第に硬直化した公団を含む諸組織のテクノクラシーに対するカウンター、過剰に構築されたシステムに対する破壊者として、建築家への役割が期待されたからであった。どんな素晴らしい組織でも時間が経てば硬直するし、それへの反省抜きに過去の実績を美化し過ぎると学ぶべきことを見失う。
そのように考えると、この本からの「学び」は私たちの何に活かされるのだろうか。団地設計の成功事例はこれから急成長する新興国の住宅整備の現場ではある程度活かされるかも知れない。またあるいは長らく続くデフレ経済状況の中でローコストへの追求が進み、高層板状の単調な中高層マンションの建設が相次ぐ日本では、1960年初頭より住宅設計のレベルが下がっていると言えるかも知れず、案外身近なところですぐに役立つのかもしれない。
しかし本書のような試みからの学びは、もっと大きなスケールで活かしたいものだ。我が国においてこれからの世代が考えなければいけない超高齢化社会や人口減少、都市の縮小とはつまり、団塊の世代が住空間とし、団塊ジュニア世代が育ってきた公団の作ってきた住空間を大胆に消去し、他の用途へ積極的に転換することを含む。前例のない状況に対し、緊急に、分野横断的に手法を再構築しなければいけないその状況は、本書が扱う公団の初期によく似ている。
団地だけでなく、1968年の霞が関ビルに端を発する巨大開発や、公団以後の戸建て住宅による1970年代以後の民間開発による郊外ニュータウンなど、日本には人工的な「設計物」として見なされていない「歴史的な」遺産がたくさんある。「縮小の時代としての今」の参照として「拡大の時代としての戦後」を積極的に「読む」作業は今後、活発化するのではないだろうか。その意味で、本書は他に先駆けて、「団地」という切り口からいち早く日本の戦後の建築史を批判的に再評価しようとした、先駆的な試みであると言えるだろう。