随想 平成10年9月 10月 11月 12月 平成11年1月 2月 3月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
11月 12月 平成12年1月
2月 3月分
4月分 5月分 6月分
7月分 8月分
9月分 10月分 11月分 12月分
平成13年1月 2月分
正月も過ぎ,二月ともなると寒いながらも,時たま春を思わせる日も訪れる。
でも政治の世界は真冬の観がする。
ドン底である。次から次へと不祥事が相次ぎ報道されている。まず森首相の原潜事件での不手際,
相変わらずの議員達の汚職が連日報道されている。
三月から新しく成立した「あっせん利得罪」が施行されるが抜け穴だらけの法律では
今の政治を変えるような威力にはほど遠い。
もっと厳しい法律でなければ,利権を欲しいままにする連中を取り締まる事は出来ない。
「あっせん利得罪」があるから,議員に成っても唯シンドイだけで自分の利益に全くなんにもならぬから議員を止めたいと
利権目的で議員に成っている人達が止めてゆくような法律を作るべきである。
政治家,官僚は公僕といわれているが「公僕」は全くの死語になっている。
今の世間は政治家が威張り官僚が威張りして,国民はオロオロしながら世の中が動いている。
国民の7%の支持率しかない首相が健在であること自体,世の中が間違っている事を如実に示している。
人材は日本にいないのだろうか。?そうではないと思う。
「地盤」 「看板」 「鞄」が無いから議員になれない有能な人たちが沢山いると思う。
解決方法はいくらでも見つかるのだが,潜在的な利権を欲しいままにしている強い勢力が依然として健在である。
二月と言う季節は丁度春への移行期でもある。世の中,徐々にでもあるが春になってゆくのを期待したいものです。
一歩一歩の尊さ
松下幸之助の言葉より
--------------------------------------------------------------------------------
仕事はいくらでもある。あれも作りたい。これもこしらえたい、こんなものがあれば便利だ、あんなものもできるだろう、と次から次へと考える。
そのためには人が欲しい、資金が欲しいと願うことには際限がないが、一歩一歩進むよりほかに到達する道があろうか。
それは絶対にない。やはり、一歩一歩のつながり以外に道はない。坦々たる大道を一歩一歩歩んでゆけばそれでよい。
策略も政略も何もいらない。
一を二とし、二を三として一歩一歩進んでゆけばついには彼岸に到達するだろう。
欲しいと願う人も一人増え、また一人増えてついには万と数えられよう。一歩一歩の尊さをしみじみ味わわねばならぬ。
判りきったことだがこのように書かれると説得力がある。始めの一歩の方向が誤らない事も大切である。
同行二人
松下幸之助の言葉より
--------------------------------------------------------------------------------
弘法大師さんが開かれた高野山にある霊場に詣でる人びとの菅笠には、みな一様に“同行二人”とかいてある。
どこにいようと、どこに行こうと、自分は一人ぼっちではない、いつもお大師さまと二人という意味である。
つまり、これら信仰三昧の人びとの心の中には、いまもなお大師は生き生きと存在しておられるのである。
もちろん、大師の生身の身体が、そのままここにあるというわけではない。
しかし、大師はいまもなおここにおわすと感じること、また感じようとつとめるところに、大師の教えが永遠に生きてくることになる。
真理は永遠に生きるというのは、こんな姿を言うのであろうか
いつもお大師さんと一緒,信仰が違えば同行する人が違うだけである。 「いつも見てござる」の妙好人の言葉もある。
だから人が見ていないからとても,悪い事は出来ない。キリスト教の三位一体も同じような意味が込められている。
常に正しい道を歩んでいる人には先人,又現在常に共に歩む人達が沢山に見えない所で同じ方向に一緒に歩んでいるものだ。
森さん,貴方は日本の国の最高責任者「首相」ですよ!
2月12日,2月15日の天声人語より
高校の漁業実習船が米海軍の原潜に沈没させられた事故を、森喜朗首相は横浜のゴルフ場で知らされた。
が、そのままプレーを続け、午後1時前になって出発。東京・瀬田の私邸に寄ったあと、官邸に着いた。その間、4時間弱。
「私自身が右往左往したら命令できないし、報告も受けられない」と首相は説明した。その通りだ。
人間、大事のときにうろたえるとロクなことはない。
しかし、そうした状況で泰然自若として遊んでいられる神経も相当なものである。
よほど修養を積んでいるのだろうが、ふつうはこれを無神経と呼ぶ。
首相の対応については、容認論もある。
たとえば「今回の事故の一次的な責任者は外相であって、首相の官邸到着が数時間遅れたとしても許される範囲」
(佐々淳行・元内閣安全保障室長)というように。
ただしこの場合、遅れた理由は何か、といったことも重要なはずだ。
ゴルフの相手は「知人」だったそうだ。
ゴルフ場内で問いかけた記者に、首相は「どうして、ここまで入ってくるの。ここはプライベートですよ」と、とがめた。
私的な場所での私的な楽しみ。
心身をいやすには大切なことだが、官邸に駆けつけるのを遅らせる理由になるとは、とうてい思えない。
ゴルフ場でも情報は受けとれるし指令も出せる、要は実質。と、そんな意見もあるかもしれない。そうだろうか。
官邸などしかるべき場所で、いち早く陣頭に立って指揮するのとしないのとでは、内外に及ぼす印象も大変に違う。
いのちをどれほど尊重しているか、事態をいかに重大視しているかが、そこににじむ。
最高責任者として、それは重い振る舞いだ。なのに首相は、そういう状況判断をしなかった。そして、批判を浴びている。
自身の危機管理ができない人に国の危機管理をゆだねるのは、なんとも心もとない。
「待合とゴルフにはいっさい行かない」。もう40年も前のこと、首相になった故池田勇人(はやと)氏は、そう約束した。
待合とは、簡単にいえば料亭みたいなもの。政治家が談合する「待合政治」の弊害が指摘されていた。
ゴルフも庶民生活とは縁遠かった。
官僚出身の池田氏は、高飛車な態度もあって首相就任前の評判は必ずしもよくなかったが、在任中の4年余、かたくなに約束を守った。
きのう、福田康夫官房長官は「個人としては、そもそもゴルフに行くべきではなかったと思う」と森喜朗首相を批判した。
「行くべきでなかった」論は、連立与党の公明党幹部らからも出ている。
首相自身も党首討論で、渋々ながら「場所がご批判をいただく場所であったとすれば、甘受しなければならない」と述べた。
ただし、官房長官の発言に対しては「ゴルフは私の場合、健康管理ということもある」と、かたくなだった。
そうかもしれない。これも首相が好む毎夜の料亭通いに比べれば、体にはいいだろう。
それに、今回の問題の核心はゴルフをしていたことではない。
漁業実習船が米軍の原潜に沈められたとの報告を受けながら、なお長い時間クラブを離そうとしなかった、
その弛緩(しかん)した姿勢が批判されているのだ。
報告を受けるには「この場所にいることが間違いがないだろう」と判断したとも、首相は言う。
ならばグリーンにとどまらず、クラブハウスに直行すべきだった。
私的な時間に遊ぶのをとがめようとは思わない。が、その際に秘書官を連れず、車には背広もネクタイも用意していないとなると、
首相としての心構えを疑う。
遊んでいる場から公的な場へ急行しなければならぬ事態など、いくらでも想定できるではないか。
きのうの株式市場は、首相退陣論を「好感」して上げる場面もあった。こんな国が、どこにあろうか。
森首相の資質については以前から言い尽くされているが,それでも尚且つ首相でいられる日本の不思議さが感じられる。
一説には適当な後継者がいないとか。もし小渕さんのように突如倒られればどのようになるのたろうのか。?
後継者がいないと言うのは森さんを支えて来た人たち,森さんに首相になってもらっていると
都合の良い人達だけが言うだけのことではなかろうか。世論調査ではずーと以前から見放している。
人事を尽して天命を待つ
松下幸之助の言葉より
--------------------------------------------------------------------------------
「人事を尽して天命を待つ」ということわざがある。これは全く至言で、私はいまも自分に時どきその言葉を言い聞かせている。
日常いろいろめんどうな問題が起きる。だから迷いも起きるし、悲観もする。仕事にも力が入らないことがある。
これは人間である以上避けられない。
しかしそのとき私は、自分は是と信じてやっているのだから、あとは天命を待とう、成果は人に決めてもらおう……こういう考え方でやっている。
小さな人間の知恵でいくら考えてみても、どうにもならぬ問題がたくさんありすぎる。
だから迷うのは当たり前である。
そこに私は一つの諦観が必要だと思うのである。
古くから言い尽くされていて良く使う言葉だが解説の仕方により深みが増してくるものだ。
首相 自らが利権の恩恵を蒙る「我が日本の国」
2月18日の天声人語より
退陣へ、退陣へ、と草木もなびく。非難のあらしの中にある森喜朗首相の、ここではゴルフ会員権問題を整理しておこう。
以下は、ベテラン税理士の話。
明らかになった2件のうち、ひときわ問題なのは最初に報じられた戸塚カントリー倶楽部(横浜市)だ。
知人の社長が4000万円で買った会員権を「森喜朗」名義にしていた。
森事務所は「名義は森だが所有者は社長とする文書を交わした上での貸与」と説明する。
しかし専門家によれば、文書など関係ない。名義人イコール所有者なのだ。
「名義人でない人が実は所有者、という言い分が通るなら、贈与税や所得税逃れのヤミ贈与がいくらでもできることになる。むちゃです」。
首相は、むちゃを通した。
この場合、会員権を社長個人が購入したとすれば、社長から首相への贈与とみなされ、首相は贈与税を払わねばならなかったはず。
社長の会社が買って贈ったのなら、所得税を払う義務が首相にはあった。
16年前の会員権価格は4000万円。贈与税は1200万円余の計算になるが、国税徴収権の時効は5年。すでに時効だ。
首相は名義を返すと申し出た。と、今度は返された社長の方が贈与税を払わねばならぬ。
現在の会員権価格が2500万円なら、贈与税は660万円になる。首相は「税法上、何ら問題ない。税務署、税理士に相談した。
『こんな例はいくらでもある』と言われた」と弁明した。
「問題にならないわけはない」と、本欄が話を聞いた税理士は断言する。
「仲間とも検討したが、首相の言い分が通る余地はない。通るとすれば、税務署がわざと見逃した場合でしょうか」。もしそうなら、ますます問題だ。
これに加え、千葉のゴルフ場の一件がある。首相に望む。(1)相談した税務署、税理士の名を明かすべし(2)逃れた税金と同額を国に納めるべし
議員並びに官僚の利権国家「日本国」を象徴する首相による利権構造がよく描かれている。
何処の政党であろうとも政権を長く担当していると必ずに起こりえる現象である。又大小を問わず何処の社会にでもある話だ。
利権目当てに議員に成る人を防ぐ以外に予防法は無い。「あっせん利得罪」に関連した法律を厳しくし,
利権目当てで議員になる人達の意欲を無くす。改善への第一歩はこれ以外に無いのではなかろうか。
本当に国民のために国家のためにさらには世界のためになるような人たちを育てことのできる法律を
作るべきである。今の世の中,本当に世の中に役に立つ政治家になりたい人達にとって政治家への道が完全に絶たれている。
大阪城築造の秘訣
松下幸之助の言葉より
--------------------------------------------------------------------------------
豊臣秀吉は、あの豪壮華麗な大阪城を、わずか1年半で築造したというが、どうしてそんなことができたのか今日なお不思議に思われる。
しかしその大きな原因の一つは、築造に当たって彼は「功ある者には莫大な恩賞を与えるぞ」と約束した。
そのかわり「過怠ある者は牢に入れるだけでなく、容赦なく首を斬ってしまうぞ」と宣言した。
首を斬られてはかなわんから、みんな必死になって働くが、その上に莫大な恩賞が約束されているから、より一層はげみがつく。
そこにあの大阪城築造の秘訣があったとも言えよう。“信賞必罰”は、昔も今も、人間の存在する限り必要なものであり、
永遠の真理を喝破した貴重な教えではなかろうか。
この話には賛成しかねる。以前書いた「飴とムチ」の話と同じである。
古くから立身出世者,支配者と言われる人たちがよく使っている手段だが,一方視点を変え使われている側から
するならば,命がけの話である。ムチはたまらない。
指導者が率先して範を示し,それに啓発され皆が頑張る。頑張ったものには賞を与える。それで良いのではなかろうか。
「信賞必罰」「飴と鞭」は指導者側からの一方的な一人勝手な言い分だけであって,従されるものにとってはたまったものではない。
威勢のいい政治家,村上正邦氏
2月24日の天声人語より
1カ月ほど前の本欄で、大正時代にはやった「ノンキ節」に触れた。
政治や世相を鋭く風刺して、最後は♪ア、ノンキだね、と突き放す。
演歌師の添田唖蝉坊(あぜんぼう)が得意とした。彼には、ほかにも風刺歌の傑作が数々あって、
たとえば「金々節(かねかねぶし)」では♪金だ金々 金々金だ/金だ金々 此世(このよ)は金だ……学者、議員も、政治も金だ、
とやけ気味に歌う。
「へんな心」は、ベルディの「女心の唄(うた)」の替え歌。
♪株がさがる 株がさがる/小気味よくも 株がさがる、に始まり、♪小気味よくも さがるよ あーあ、さがるよ、と歌いおさめる。
こうした歌が、昨今もほとんどそのまま通用するのは情けない。
多彩な唖蝉坊の活動のうちノンキ節を継承、発展させたのが石田一松だ。
敗戦後も活躍、♪闇肉(やみにく) 闇酒 闇のお米で/生きてるおかた 欲にめがくらみ/
配給の食糧で生きてる奴(やつ)は/栄養失調で目がくらむ/ハハ、ノンキだね、などとバイオリンを弾きながら権力、権威を皮肉った。
石田は1946年の総選挙で、一人一党の「日本正論党」を名乗って当選。国民協同党、民主党と所属を変えながら、連続4期、代議士を務めた。
ノンキ節の系譜どおり反骨精神が盛んで、金には無縁。安保条約などに反対し一時政党を離れたこともある。
KSD問題で参院議員の辞職願を出した村上正邦氏も、威勢のいい政治家として知られた。
日の丸・君が代法制化で働き、憲法改正を唱えて参院憲法調査会会長に就き、
例の密室の談合では「森さんでいいじゃないか」と推薦の先頭に立った。
威勢はいいけれど、中身は石田とはほぼ対極。
金とか権力をめぐる話が、あれこれ絶えなかった。しかし、村上氏にも歌ごころはあって、趣味の一つは俳句。
〈強東風(つよごち)や黙して済まぬこと多し〉。まったくその通りだが、本人はこのところ黙したままだ
威勢の良い政治家には色いろとあるということか。
「金々節(かねかねぶし)」では♪金だ金々 金々金だ/金だ金々 此世(このよ)は金だ……学者、議員も、政治も金だ、とやけ気味に歌う。
♪株がさがる 株がさがる/小気味よくも 株がさがる、に始まり、♪小気味よくも さがるよ あーあ、さがるよ、と歌いおさめる。
こうした歌が、昨今もほとんどそのまま通用するのは情けない。
人間は昔も今も人間としては一歩も進歩はしていないし,又するものではない。
人間の一生は短い,でも人間は所詮欲の塊と言ってしまえばそれで終わりである。
でもその時代に生き偉人と言われている人たちも多くおられたのだから,そのような人たちに一歩でも
近ずくように努力して生きてゆきたいものです。
ほんとうの勇気
松下幸之助の言葉より
--------------------------------------------------------------------------------
私は一般的に、ほんとうの勇気というものは一つの正義に立脚しないことには、また良心に顧みてこれが正しいと思わないことには、
湧いてこないと思うのです。
だから、勇気が足りないということは、
何が正しいかということの認識が非常にあいまいであるところから出てきている姿ではないかという感じがします。
人びとがそれぞれに自問自答して何が正しいかということを考える。
そして、この正しさは絶対譲れない、この正しさは通さなければいけないという確固とした信念を持つならば、
そこから出てくる勇気は、たとえ気の弱い人であっても非常に力強いものとなる。そういうような感じを私は持っているのです
本当の勇気ある人になりたいものです。
「ペンは剣よりも強し」,でも使い方次第で凶器ともなる
2月 2日の天声人語より
〈近来は……とかく西洋流でなくては、らちがあかず、日新日新と申して、蒸気伝信など、色々新発明がありますが〉
と書くのは福沢諭吉だ(原文のカタカナをひらがなにしてある)。
1874年というから、維新からあまり時日を経ていない明治7年の文章。〈……人情新しきに奔(はし)ればふるきを忘るゝものと見へて、
ここに世の人の、あまり気の付かぬ、ふるい器械がございます〉と続く。
新しい便利な品がつぎつぎ登場する文明開化の世に、福沢があえて紹介する古い器械とは、使いやすく、値段も百文程度で大変に安い。
しかも、その性能たるや奇々妙々、まことに素晴らしいのだという。
〈……死んだ人と話もでき、生れぬ子供と談判もでき、馬鹿者を利口者にしたり、利口者を馬鹿者にしたり、
世の中を治むる事もあれば、世の中を乱る事もあり、人の喜怒哀楽を自由自在に取扱ひ〉 どんな難しいことでも、できないことはない。
そもそも鉄道も電信も、みなこの器械を使って作ったもの。
いつの時代にこの器械が発明されたのかは知らないが、ずいぶん昔のことだから「新発明」と称するわけにはいかない。
などと読者をやきもきさせておいて、種を明かす。〈御存じなくば申しましょう。筆と紙でございます〉
福沢が亡くなったのは20世紀の最初の年、1901年2月3日だった。
没後100年を記念して、東京・銀座の「和光」で展覧会が開催中だ(慶応義塾主催、10日まで)。
右の文章を記したパネルの下に、愛用の筆とすずりが展示されている。3本の筆もすずりも、存分に使い込まれた跡がある。
IT(情報技術)、ITと騒がしい現代でも十分通用する発想だ。機器・道具を使いこなせなければ、何の意味もない。基本は「人間」。
日航機同士のニアミスでも、「人間」の問題があった疑いが強い。
日本の第二次大戦中の世の中, 片寄った報道しかされていない世界で例えば専制主義の北朝鮮人民共和国 イラクなどの言論が
統制されている国々閉ざされた閉鎖社会では誤った道具ともなりえる。
書く人 読む人が理性をもって書き 読んでやはり基本的には磨かれた人間の存在が大切である。
インターネットが社会を変える
学術面におけるインターネットの利用方法は急速に進歩してきた。これからまだまだ進歩は続けるものとと思う。
社会を,世の中を良い方向に変化させる手段としてはまだまだの感はある。
効果は徐々にだか出てきている。コソコソと悪い事は出来ずらい社会になろうとしている。
今まではマスコミ ミニコミに頼っていた情報が個人で簡単に出す事ができるようになってきた。
インタ−ネットに接続する人も日本でもかなり増えてきている。2000万人とも言われているが個人での
接続は少ない。会社から与えられたアカゥト名で接続して,会社の仕事以外には使わないように
制限されている。故にインターネットが社会を変えてゆくのはこれからのことかと考える。
介護保険の運用は今のままで良いのか?
理想として始めに目指していた介護保険とは違った形で動いている。要介護者並びにその家族の為に
出来た制度が,公正であり且つ公平であるべき介護支援専門員が所属する事業者の言うがままに動いて
その尖兵として働いている。
要介護者並びにその家族は又その言うがままになってしまっている。保険者もそれを黙認或いは事業者と連携するような
傾向が見られる。誰のための介護保険制度かわからなくなって運用されている。
弱い立場の要介護者並びにその家族を救うための制度が事業者の利益を出すため為に運用されてきている感を受ける。
理想と遥かに違った方向に進みつつある。相手が老人で有るが為にその影響は深刻である。
介護保険が立ち上がって,正しい軌道に乗るまでの一時的な現象であってほしいものであると願う。
Homeへ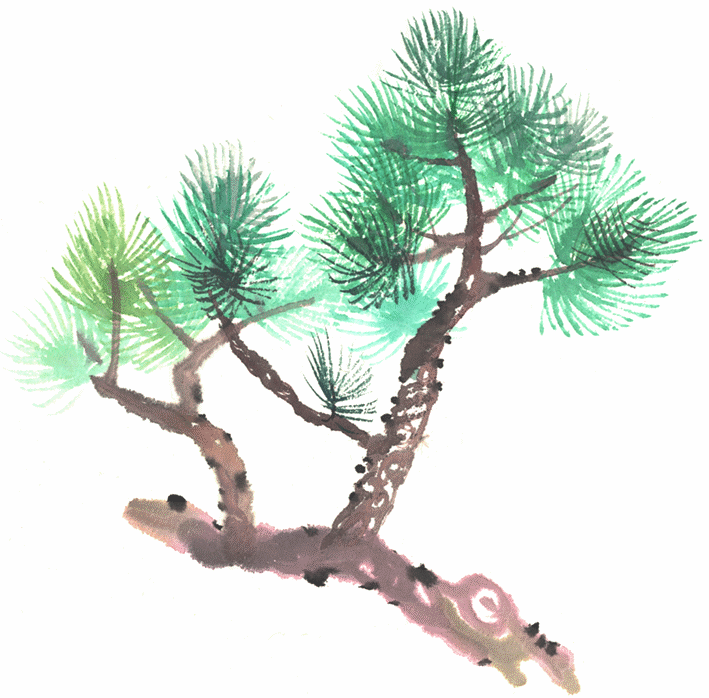
1月 2月 3月