古代世界ではヘビは他の動物のように年を取って死ぬことはなく、定期的に脱皮して新しく生まれ変わる、もしくは別の生命となって再生すると広く信じられていた。ギリシア人はヘビの脱け般を「老年J gerasと呼んだ。中国人は死者の復活を、人聞がヘビのように古い皮を切り裂いてその中から再び若者となって現れるものとして想像した。メラネシア人は、「皮を脱ぎ棄てる」ことは永遠の生命を意味すると言う。ヘビに関する原初の神話は、生と死の2面を持つ月女神が最初の人聞を作った、と述べている。月女神の輝ける相は、ヘビのように皮を脱ぎ棄てることのできる不死の者として人間を作ったことを暗示した。しかし月女神の闇の相は、人聞は死なねばならず、大地に埋められるべきことを主張している[1]。現在でもイタリア語の表現の「ヘビよりも年を取っている」 aver piu anni d'un serpenteでは、永遠の生命とヘビの特質が等しいものとして考えられている。
不老のヘビは本来は太女神自身と同一視されていた。ヒンズー教の「無限なる者アナンタ」は、「死」の相にあるときのヴィシュヌやその他の神々を抱擁する「ヘビ-母神」であった[2]。彼女はまたヘビの姿となって男性の内部に宿る女性の霊魂クンダリニーでもあった。クンダリニーは骨盤の中でとぐろを巻いているが、ヨーガの行を適切に行うことによってとぐろを解き、無限の知恵を帯ぴて、脊柱のチャクラchakras(中心輪)を昇り、頭部に達する。ヘビ-女神はカンボジアのアンコール・ワットにある有名なクメール人の神殿に住んでいて、この神殿で女神は夜ごとに王を抱いた。女神が姿を見せない夜があると、それは王が殺され、新しい王が選ばれなければならないというしるしであった[3]。
ネグリート(東南アジアの小柄字黒人種)は、シノワ(中国人)と呼ばれる神の民はマト・シノワ(中国人の母)という名の強大なヘビ-女神の子孫である、と言った。ヘビ-女神の腹部には死者の霊魂を受け取る美しい天使たちが住んでいた。彼女の子宮が楽園であったため、シャーマンはヘビの腹の中に入って、死と再生の入信儀礼を受けた[4]。
古代のエーゲ海文明世界は最初女性とヘビを崇拝した。男性はのちの青銅器時代になるまで宗教的儀式に参加しなかった。青銅器時代に初めてクレータ島の王が雄ウシ-神の祭司となることを許された。それでもなお、祭司自身が「ヘビ」の添え名を名乗るようになるまでは、祭司の役割は巫女のそれより一段下に置かれた[5]。古代アッカド人の間で「祭司」に当たる語は字義的には「ヘビ使い」を意味した[6]。
インドのヘビ-女神カドルーはすべてのナーガ(コブラ族)を生み、自らの聖なる月の血で育てて彼らを不死とした[7]。バビロニアでカドルーに相当する女神がカディ・オブ・デルであり、女性の頭と胸を持つヘビとして崇拝された[8]。ナーガと似た彼女の子供たちは、腰から上が人間の、人魚のような水ヘビとして描かれた。ナーガは「水底の宮殿にある莫大な財宝や宝石を守護していた」[9]。
同様のヘビが水底の宮殿に隠されている不思議な『トートの書』*を守護していた[10]。トートと瓜二つのギリシアのへルメースのように、トートもしばしば、ヘビに化身して、自分の持っている魔術の知恵を示した。最初のヘビは太母神自らのトーテムとしての姿であると述べた点で、エジプトもインドと軌をーにしている。エジプトの古い「創造女神」はヘビであり、ペル-ウアチェトあるいはプトーと呼ばれた。エジプトのウラエウス-ヘビUraeusは、「女神」を示す象形文字のしるしとなった[11]。余り適切とは思えないが、「ウラエウス」はのちに『魔術パピルス写本』*や中世の魔術の書に挙げられている最も一般的な「神の秘密の名」の1つとなった。
『トートの書』
伝説上のエジプトの魔術の本で、神トー卜によって書かれ、サトニ・ハームスという名の若い王子によって、メンフィスの共同墓地から発見された。
『魔術パピルス写本』
初期キリスト教時代に広く流布していた祓魔術、祈祷、まじない、呪文を集めた書。のちに魔術や錬金術の書物の底本として用いられた。
エジプトのヘビ女神もまた、クンダリニーあるいはアナンタと同じく、「包み込む者メへン」の添え名を持っていた。夜ごとメへンは、雄ヒツジの頭を持つ神アフ-ラー(ラーの男根)が子宮-冥界に逗留しているときに、彼を包みくるんだ。これは王が女神と性的結合するときの神話的なイメージで、アンコール・ワットの風習を想起させるものである[12]。
ファイリー島(エジプ卜・ナイル川上流の島)では、ヘビ女神はanq (囲む、抱擁する)を語源とする「アンケト」という添え名を持っていた[13]。「ナイルのヘビ」は、クレオパトラの添え名だったばかりでなく、エジプ卜の女王は、すべて「ナイルのヘビ」という添え名を持っており、国家と、王を抱擁する女神を象徴していた。
生誕と死の女神のアセト〔イーシス〕とネフティスは、生と死後の世界という二重の意味を持つヘビ母神と同一視されるようになった。彼女たちだけが、ナーガのエジプト版であるヘビ神たちの住む冥界において、霊魂を助けることができた[14]。
『マハーバーラタ』Mahabharata は、「ヘビの都市」と呼ばれる冥界で、不死を探し求める英雄を描いている。そこでは二重性を持つ「生と死の母神Jが、黒と白の糸で、夜と昼を表す織物を織り、それを生命の赤い糸で綴じ合わせていた[15]。
『マハーバーラタ』
インドの叙事詩。 4世紀 から10世紀の間に集められた歴史および伝説上の資料から形成され、有名なパガヴァッドーギーターはこの一部である。
アッカドの女神ニンフルサグ(「死者に生を与える女性」)もまた、カドルーあるいはカディの別の姿であり、「ヘビの女王」と呼ばれた[16]。この女神のバビロニア版では、彼女は天界の女神イシュタルの双子で、閣を司る女神とされ、ラミアーあるいはラマシュトゥ(「偉大なる女神、天界の娘」)と呼ばれた。円筒印章には、彼女が、ヘビのペニスを持つ夫神パズズの上に、カーリーのようにうずくまっている姿が示されている[17]。パズズは他の「死の王」と同じく、女神に食い尽くされるために我が身を与えた。
女性に巻きつかれ食い尽くされる男性のヘビ神のイメージは、プリニウスが記録したヘビの性交についての迷信的な考え方を生むことになり、この考え方は20世紀にいたるまで西欧では真面目に信じられていた。つまりヘビの雄は頭を雌の口の中に入れて、我が身を雌に食べさせることによって雌を妊娠させるというものである[18]。
男性のヘビ神は太母神の男根としての夫となり、また母神の最初の相手であったという理由から、ときには種族の「父祖」となった。いくつかの神話では、ヘビ神は、女神が自分の性の愉しみのために創造した、単なる生きた男根に過ぎなかったという。他の神話では、女神は、ヘビ神に、創造の仕事に参加したり、あるいは世界を生み出す彼女の子宮を妊娠させることを許している。ヘビ創造神が倣慢になり。 1人で世界を作ったと偽って主張をしようとしたとき、女神は彼を罰し、かかとで傷つけて、冥界に追放した[19]。
創造に関する神話のこの変形にもとづいてユダヤ人は、イヴの子孫、がヘビの頭を打って傷つけるという考えを抱き、またヘビはイヴの最初の愛人であって、カインの真の父親であるという、ユダヤの律法学者の見解が生じた[20]。
実際にヤハウェ崇拝が起こるずっと以前に、パレスティナではヘビが崇拝されていた。初期のヘブライ人は、当時の人々がみな崇敬していたヘビ神を受け入れた。ユダヤの祭司族であるレピ族は。「大いなるヘビの息子たち」すなわちレヴィヤタン(うごめく者)の息子たちであった[21]。レヴィヤタンは彼の女神である月と組み合わせて崇拝された[22]。聖書は、ヤハウェがヘビのレヴィヤタンの敵意に満ちた競争者であったことを示している。 2人の神は互いに戦い(『詩篇』74 : 14 ; 89 ; 10、『イザヤ書』51 : 9)、さらに終末の日に最後の一戦を交えることになっている(『イザヤ書』 27 : 1; 『ヨハネの黙示録』 12)。
「大いなるヘビ」に対するもう1つのユダヤの名は、モーセの神として描かれているネホシタンである。へプライ語のnahash(ヘビ)は古代のヴェーダのヘビ王ナフシャNahushaを起源としている。ナフシャはかつては「天界の至高の支配者」であったが、のちに敵対者によって冥界に投げ落とされた[23]。ネホシタンはモーセが像を造った神と同じ神で、『民数記』第21章8節によれば「火のヘビ」であった。イスラエル人はこの神を崇拝していたが、ヒゼキア(紀元前8-7世紀のユダヤの王)の治世になると、新しい祭司職が「高き所を除き、モーセの造った青銅のへぴを打ち砕いた」(『列王紀下』 18: 4)。
それでもなおイスラエルではヘビ崇拝が続けられた。聖なる「火のヘビ」に対するへプライ語のseraphは、かつては大地を豊穣にする稲妻-ヘビを指したが、のちに天使を意味する語となった[24]。「大いなるヘビ」であるへルメースが創始し、モーセ伝承によって模倣されたへルメースの杖(カドケウス)がヘビの精であったように、織天使 seraphimも本来はヘビの精であった。ギリシア人の彫った「ヘビの尾を持つ風」と同じく、紀元前1、 2世紀のユダヤの円形浮彫は、エホヴァをヘビ神として表している[25]。
小アジアのユダヤ人は、彼らの崇拝するエホヴァはプリュギアのヘビ神ゼウス・サバージオスと同じ神であると言った[26]。キリスト教時代の初期に、グノーシス派のユダヤ人のある者たちは、バビロニア捕囚(紀元前597-538)後のエホヴアはもはや神ではなく悪魔であり、原初の「知恵のヘビの王国」を纂奪した者であると主張した[27]。
多くのグノーシス派文学は、人類を無知の状態に置こうとする暴君的な神の意志に反対して、人類に知識という「光」をもたらしたという理由から、エデンの園のヘビを礼賛した[28]。エデン神話に対するこの見方はシュメール-バビロニア人の資料にまでさかのぼることができる。
それによると、人聞は大地母神によって泥から作られて、神々のために「これ(エデンの園)を耕させ、これを守らせ」るようにエデンに置かれた(『創世記』 2: 15)、なぜならば神々はたいそう怠惰で農耕をしようとせず、植え、穫り入れ、自分たちに捧げ物をする奴隷が欲しかったからである[29]。神々は奴隷たちが自分たちより偉くなって働こうとしなくなるのを恐れて、神々の持つ不死の秘密を決して彼らに知らせてはならないことを申し合わせた。したがってギルガメシュ叙事詩(シュメール・バビロニアの叙事詩。ギルガメシュはその主人公)が述べるように、神々は人類に死を与え、「生は自分たちの手に確保しておいた」のであった[30]。
混交した創世の物語の1つでは、神は1人ではなく数人の神々(elohim)、すなわち神々と女神たちであった[31]。エデンの神は、同僚の神々に向かつて言った。「見よ、人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るものとなった」。したがって彼は「命の木からも取って食べ、永久に生きるかも知れない」ので、ただちにエデンの園から追い出さなければならない(『創世記』 3: 22)。ヘビの教えは、人聞を、死を征服し神のような存在にしたであろうに、これは神々elohimの意志に反することであった。
『支配者たちの本質』Hypostasis of the Archons (3世紀頃に書かれたグノーシス派の福音書。アダムとイヴの神話の変形の1つを取り上げている)は、ヘビは女神のトーテムとしての姿であることを示している。ヘビは明らかに、女神の創造した死ぬ運命を持った生物を憐んて、永遠の生命に到達する方法を教示しようとした。「女性の霊的原理が『教示者-ヘビ』の中に入り、ヘビは彼らに教示して言う。『あなたがたは死ぬことはないであろう。神がそう告げたのはあなたがたを嫉妬したからである。それどころかあなたの目を大きく開きなさい。そうすればあなたは善悪を識別して神のようになるであろう』」。そこで「倣岸な支配者(神)」はヘビと女性を呪ったのである[32]。グノーシス派の一部の信者は、ヘビと女性が人類のために尽くした努力ゆえに、この両方を崇拝していた[33]。
聖書の物語の現在の型は、太女神とヘビの本来の話を明らかに大幅に改訂したものである。バビロニアの図像は、ヘビにかしずかれ、人間に不死の食物を捧げている女神の姿を描いている。ピラミッド・テキストは、永遠なる生命の食物を提供したのはヘビである、と述べている[34]。
オピーオーンあるいはオビとして、このヘビはアフリカのヘビ神オビの祖となった。オビの名は現在もヴードゥー教の呪術の組織を指すobeahという語の中に残っている[35]。聖書はヘビの名のへプライ語訳obhを「エンドルの魔女」の使い魔に対して用い、ウルガタ(ラテン語訳)聖書はこの語を「ピュートーン」と訳している[36]。ダオメ(アフリカ西部)では、原初の「創造母神」マウウは「大いなるヘビ」の助けを借りている[37]。
エデン神話に関するグノーシス派の記述はイヴ、教示する者、ヘビの3者を結びつけるアラム語の語呂合わせを用いた。すなわちHawah (「万物の母」)、 hawa (教示する)、 hewya (「ヘビ」)である[38]。アラビア語のイヴの名は現在でも、「生命」hayyatの概念とヘビの名Hayyatを兼ねている[39]。
ヒッポリュトスはヘビは女性のロゴス、「イヴの賢い言葉」であると考えた。「これはエデンの園の神秘であり、エデンの園から流れ出す川である。これはまたカインにつけられたしるしでもある。この世の神はアベルの血にまみれた生贄を受納し、カインの俸げ物は受納されなかった。なぜならばこの世の神は血を喜ばれるからである。この『ヘビ』は後年へロデの時代に人間の姿をとって世に現れた者である」[40]。
アラビアの伝承は不死の食物を、「王の紫」の色をした女性の子宮の血と同一視し、母神の子宮にある園をシバSheba(アラビア南西部)のマリブにある月の神殿と同一視した。伝説はシバにいるヘビは神の本質で彩られて紫色をしており、木に住むと伝えている。シバの人々は二岐に分かれた舌と大いなる知恵を持ち、長命で、ヘビに似ていた[41]。ギルガメシュ叙事詩の中の、シバshibaと呼ばれる神秘的な生命を生む物質は、シバShebaからもたらされたものかもしれない。ウタ-ナピシュティム(ギルヵ・メシュ叙事詩の人物。聖書のノアに当たる)は妻からシバを分け与えられて、唯一の不死の人間となった。これから見ると、ウタ・ナピシュティムの妻は女神だったのである。この聖なる女族長がギルガメシュにシバを与えたとき、彼はヘビのように古い病んだ皮を脱ぎ捨て、その中から再生して姿を現した[42]。
ペルシア人もまた経血とヘビの長命との象徴的な結びつきを主張した。ミトラ教信者は、不死は生贄に捧げられた雄ウシの血によって与えられるが、ヘビは生贄の場にいて、雄ウシの身体から流れ出る血を集めたのだ、と述べている。そしてこの雄ウシの血は、「月から送られて来た」ものであり、そのため経血に擬せられた[43]。
不死は原初の時代から、脱皮する「ヘビ」と血を与える「女神」がとくに司った分野であった。「大いなるヘビ」のきわめて古い伝承のいくつかは、ヘビを「大地の腸」と同一視した。エジプトのアペプやシュメールのフンババのような古いヘビ神たちは、「腸に似ている」と言われた[44]。この関連から、生誕あるいは再生を表す聖書の語句は、「腸からの分離」であった。クレータ島の神話によれば、ヘビは死者に生命を甦らせる方法を知っていた。クレータ島では、呪術者ポリュイドスがヘビの秘密を学び、死せる王子グラウコスを生き返らせ、ミーノース王の宮廷で大きな栄誉をかち得た[45]。
多くのグノーシス派の伝承はヘビとイエスを同一視した。『ピスティス・ソフィア』(グノーシス派の聖典)では、イエスは、「アダムの楽園にある知識の木と生命の木から」イヴに話しかけたヘビであるとされた。ユダヤのヘビ崇拝者であるナアセン派Naasiansは、ヘビはメシアであると言った。『魔術パピルス写本』はヘビを「世界の支配者、大いなるヘビ、神々の指導者、神の中の神」と呼んだ[46]。一部のキリスト教徒は、ヘビはイエスの父であり、処女マリアのベッドをおおって、人間の姿をした救世主を懐胎させた、と信じていた。
これらの伝承はルネサンス時代にはなおもひそかに残存していた。パルテル・プロインの描いた、グノーシス派を象徴する受胎告知の絵画には、受胎を告げる天使ガプリエルがマリアに差し伸べている笞として、明白にへルメースのヘビの杖(カドケウス)が示されている。杖の先の円光の中にハトが翼を広げており、魔法の杖ウェヌス〔ヴィーナス〕のエンプレム(ハト)で十字のようなしるしを作っている[47]。これは「ヘビとハト」という「男性と女性の神秘」を結合させたシンボルであった。ヘビとハ卜は、『マタイによる福音書』第10章16節では、イエスの言葉となって語られている。
多くの神学者は、十字架にかけられたヘビのネホシタンはイエスを予告するものであると主張した。「そして、ちょうどモーセが荒野でヘビを上げたように、人の子もまた上げられなければならない」 (『ヨハネによる福音書』 3 : 14)。 16世紀にドイツの金細工師は、片面に十字架にかけられたキリストを、もう一面に十字架にかけられたヘビを彫った大型の金貨を作ったが、これはキリストとヘビが同ーの救い主の2つの面であったことを暗示している[48]。
すべての神話には何らかの形で「世界ヘビ」があった。「世界卵」を抱くへルメース・トリスメギストスやグノーシス派のヘビのように、世界ヘビはインド・ヨーロッパの基本的な宗教的シンボルであった。北欧神話はこれを「ミッドガルド-ヘビ」と呼んだ。このヘビは、人間界(ミッドガルド)の周囲をぐるりと取りまいて、口に尻尾をくわえていた[49]。ロシア人は、世界ヘビを冥界を取り巻く者、「不死身のコシチェイ」と呼んだ[50]。これは日本の「潮の竜-コシ」の異形であったように思われる[51]。エジプト人は世界ヘビをサタ(サタン)あるいはトゥア卜と呼び、太陽神は夜ごと、彼の背に乗って冥界を回った。ギリシア人はオケアノスと呼んだ。オケアノスは世界のさいはての大洋に住む海ヘビであった。
「天界の父」はしばしばこのヘビの姿をとり、たとえばゼウス・メイリキオスは紀元前4世紀に巨大なヘビとして崇拝された[52]。彼はヘビの姿をとって冥界に住むペルセポネーの夫となり[53]、また人間の女性に多くの英雄を生ませた。アレクサンダ一大王は神を父とすると称されたが、神はヘビの姿となって彼の母のオリュンピア女王を懐胎させたのである[54]。
ピラミッド・テキストは地下と天界の両方に住む者としてのヘビについて語っている。その天国での相では、ヘビは不死を分かち与える者であった[55]。永久に勃起し続ける神の男根として、彼は「生命の木」あるいは「天界と大地の中心を貫く柱」 axis mundiであり、女神の「中心部」と結合した「天界の父」であった。「天界の父」の目は北極星として天空にかかっていた。紀元前3000年には、北極星は竜座のアルファ星「ヘビの目」であったからである[56]。
『マハーバーラタ』 Mahabharataは、北極星は「至高のヘビ」ヴァースキで、そこに世界の軸が固定されていると述べた。ヴェーダによれば、このヘビは天地創造のときに子宮の深淵をかきまわした男根神であるという[57]。『創世記』の神同様、ヴェーダの神インドラは、「大いなるヘビ」を、天界から、世界を取り巻く外側の大海の深淵に投げ落とした、と主張している[58]。聖書の物語のように、この神話は、降下する豊穣の力を持つ男根という、ヘビの本来の意味を改めて述べたものである。
男根としてのヘビの頭を「ハスの花の中の宝石」として描く性的なイメージは、各地に広がり、やがて初潮に関する神話の多くの変形を生んだ。すなわち月経は超自然的なヘビと交わることによって始まるという考え方がそこに見られる。 ![]() Menstrual Blood. この想像によれば、神である男性のヘビは、その頭の中に「血のように赤い宝石」を得るという。ヒンズー教徒は、すべての大いなるヘビは頭の中に血のように赤いルビーを持っている、と言った[59]。
Menstrual Blood. この想像によれば、神である男性のヘビは、その頭の中に「血のように赤い宝石」を得るという。ヒンズー教徒は、すべての大いなるヘビは頭の中に血のように赤いルビーを持っている、と言った[59]。
ドイツ人はこのアーリア人の伝承を記憶に留めて、魔法の石を頭に持つヘビは、ヤドリギのそばのハシバミの木(魔女の木)の根元で発見できる、と言った。ヘビの頭の宝石は月に捧げられ、そして永遠の生命をもたらす「賢者の石」と同一視された[60]。男根のシンボリズムとしてのヘビの名残りは、中世の呪術のまじないに見られる。「女性の病気」はヘビを殴打した棒を病人にあてがうと治すことができるという根強い考え方などがそれである[61]。
13世紀のフランスでは、復活祭の週間に、拝蛇教徒Ophitesが崇拝するキリストの像のように、柱の上にヘビを乗せて、意気揚々と行列を作り教会の洗礼盤まで運んだ[62]。ときにはこの呪物は、中国の祭りのドラゴンのように、詰め物をした巨大なヘビのこともあった。キリスト教会側の人々は、ヘビは「キリストの受難によってヘビの王国より追い払われた」悪魔であると言って、この風習をキリスト教に取り入れようとした。しかしこれは、キリスト教が新たに起こったときにすでに古くから行なわれていた儀式に対する説明としてはまことに不適切なものであった[63]。
初期キリスト教の一派である拝蛇教徒はヘビ崇拝を取り入れ、モーセが荒野でへどを崇拝せよとユダヤ人に教えたと称して、モーセを自分たちの宗派の創設者であると主張した[64]。さらに、ヘビがアダムとイヴに知識を与えたのは明らかであるから、ヘビは人類の救世主であり、同じく自らのもたらした啓示のために神の御許で苦しんだキリストが、キリストとして出現する以前に、この世に現れた姿であると主張した。拝蛇教の聖なるヘビは聖体拝領の秘跡のパンを取り巻くように置かれ、それから十字架にかけられて、礼賛された。拝蛇教の「教団」は、 5世紀にはまだピシニアに存在していたが、その頃になると司教たちが群衆を率いて拝蛇教の教会を打ち壊す動きが始まった[65]。
ビシニア
マルモラ海、ボスポラス海峡、黒海に接する小アジアの古代の地域。紀元前2000年の終り頃、トラーキア族のビシニ人がこの地域に移住した。
中世のへルメース・トリスメギストスの信奉者はヘビを、魔術の王ウロポロスとして崇拝した。ウロボロスは、拝蛇教のキリスト-オピーオーン、ギリシア人のへルメース、フェニキア人のタアウト、エジプト人のトゥアト、さらに冥界に住む神託を告げるヘビ、ピュートーンなどの、ヘビの尾を待つ古代の神々すべてを融合した存在であった[66]。ウロボロスは、中国の璧龍pi-dragonと結びつけられた。璧龍は、翡翠の円板に自分の尾をくわえたドラゴン、あるいはヘビとして彫られている、宇宙のシンボルである[67]。これがヘビ-ピュートーン、ならびにピュタゴラス学派が崇拝した神秘的な循環数の原理であるパイpiの原型であったのかもしれない。
互いの尾をくわえる2匹のヘビは、陽と陰の曼陀羅とへルメースの杖(カドケウス)を結びつけるものであり、へルメースの両性具有性と、生と死、夏と冬、光と闇などのすべての周期的交替を解き明かしている。ウロボロスは、一部のヨーロッパの地域ではその後も大地の下にいると考えられており、古代の礼拝堂に立つと、足許からウロボロスのゆっくりした動きを感知することができると主張する人々もいた。
Barbara G. Walker : The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets (Harper & Row, 1983)
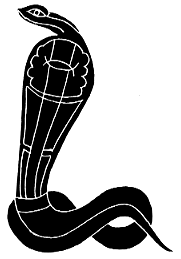 〔人間のライバル〕 人間と同じく、しかし〈逆の意味で〉、ヘビは、あらゆる動物の種と異なる。人間が発生の長い過程の帰結であるなら、この冷血動物、脚も毛も羽もない動物は、同じ過程の初めに位置させざるを得ない。その意味で、《人間》と《ヘビ》は、対立するもの、補完するもの、〈ライバル〉なのだ。またその意味で、人間の中にヘビが潜む。とくに人間の知力のコントロールが及ばない部分がそうである。ある精神分析学者(JUNH、237)がいった。ヘビは「脊椎動物であって、劣った精神や、隠れた心理現象や、稀で理解不能で神秘的な部分を体現する」。ところがヘビほど月並みで単純なものもありはしない。しかしこの単純さのせいで、ヘビほど精神にとって腹立たしいものもおそらく存在しない。
〔人間のライバル〕 人間と同じく、しかし〈逆の意味で〉、ヘビは、あらゆる動物の種と異なる。人間が発生の長い過程の帰結であるなら、この冷血動物、脚も毛も羽もない動物は、同じ過程の初めに位置させざるを得ない。その意味で、《人間》と《ヘビ》は、対立するもの、補完するもの、〈ライバル〉なのだ。またその意味で、人間の中にヘビが潜む。とくに人間の知力のコントロールが及ばない部分がそうである。ある精神分析学者(JUNH、237)がいった。ヘビは「脊椎動物であって、劣った精神や、隠れた心理現象や、稀で理解不能で神秘的な部分を体現する」。ところがヘビほど月並みで単純なものもありはしない。しかしこの単純さのせいで、ヘビほど精神にとって腹立たしいものもおそらく存在しない。
〔1本の線〕 南部カメルーンを旅していて気づいたことだが、ピグミー族は、狩りの言語を用いる際に地面に線を1本描いてヘビを表す。旧石器時代の落書きも、おそらく同じ意味なのだろう。そのような落書きは、ヘビをその最初の表現に還元したといえる。ヘビは、1本の線にすぎない。しかし〈生きた〉線なのだ。抽象化したわけだが、アンドレ・ヴィレルの表現を借りれば〈身体を持つ〉抽象なのである。線には初めも終わりもない。線に生命が与えられると、あらゆる表象、あらゆる変身が可能になる。線で見えるのは、近くに明らかに存在する部分だけだ。しかし、線はこちら側にもあちら側にも伸び、見えない永遠へと続く。ヘビについても同じである。地上で目に映るヘビ、ヘビが姿を現す瞬間というのは、聖なるものの顕現(ヒエロファニー)だ。こちら側にもあちら側にも、ヘビが伸びていくのが「感じ」とれる。原初の未分化にほかならぬ物質的無限の中を伸びていく。目に見える大地の下に潜む、あらゆる可能性の貯蔵庫の中を。目に映るヘビは、〈自然な〉ヒエロファニーである。霊的ではなく物質的な神聖である。昼の世界へ手に触れられる幻影のように突如出現するが、指の中を滑り抜けてしまう。またヘビは、数えられる時間や測量できる空間や理性に基づく規則を滑り抜け、元の地下の世界に避難する。そこは時間がなく、永遠で不動の世界であって、完全が支配する。目に映るヘビは、稲妻のように常に素早く、〈陰の出入り口〉(断層や割れ目)から現れ、死か生を吐き出しては見えない世界に戻る。あるいはそういう雄の外観を捨てて雌になることがある。とぐろを巻き、抱きつき、締めつけ、窒息させ、飲み込み、消化し、眠る。この雌のヘビは、目に見えない原理のヘビであって、意識の深い層や地下の深い層に住む。謎めき神秘的で、どういう決断をするか予知できない。その変身と同じように出し抜けなのだ。ヘビはあらゆる対立物を操るとともに、2つの性を弄ぶ。雌でもあり雄でもある。「自分の中に双子を持つ」。それは多くの偉大な創造主に当てはまり、常に最初の姿は宇宙のヘビであった。だからヘビは元型ではなく、元型の複合体であり、起源の冷たく粘りつく地下の夜と結びつく。「存在しうる限りのヘビはすべて、原初の唯一の多様性を、また原初の分割不能の《もの》を、ともに構成し、それは絶えず自らの皮を剥ぎ、消滅し、再生する」(KEYM、20)。しかしこの「原初のもの」とは、いったい何であろうか。潜在する生、あるいはカイザーリングのいうように、「最も深い生命の層」以外のものではありえない。貯蔵庫であり、潜在性であって、そこからあらゆる顕現が生じる。「深層の生命は、ヘビの形を取って昼の意識に反映されるに違いない」とこの哲学者は付け加える。さらに述べて「カルデア人は〈生命〉と〈ヘビ〉に同一の語を当てた」。ルネ・ゲノンにも同様の指摘がある。「実際ヘビの象徴的意味は生命の観念そのものに結びつき、アラビア語ではヘビはel-hayyahで、生命はel-hayatだ」(GUES、159)。そして付け加える。「とくに重要なのは、神を表す主な名の1つEl-Hayを、「よく行われているように〈生者〉」と訳してはならず、「〈生命を与える者〉と訳すべきである。よみがえらせたり生命の原理そのものである者を指す」。だから目に映るヘビは、《目に見えない大いなるヘビ》の、一時的な体現とみなされ、この、元になるヘビは、非時間的で、生命原理およびあらゆる自然の力の主人なのである。それは最初の「古い神」であり、あらゆる宇宙発生論の冒頭に見出される。精神の崇拝に取って代わられる以前の話である。それは〈生命を吹き込む〉者、〈維持する〉者である。人間についていえば、ヘビは〈魂〉と〈リビドー〉の象徴であり、バシュラールが書くように(BACR、212)、「ヘビは、人間の魂の最も重要な元型の1つである」。タントリズムでは、これは〈クンダリニー〉であって、脊柱の基底に、睡眠状態のチャクラの上にとぐろを巻き、「自分の口でペニスの穴を塞ぐ」(DURS、343)。ヘビが目を覚ますと、しゅうしゅう音を出し、身を固くする。そしてチャクラが次々に上昇を始める。これがリビドーの増大であり、生命の新たな発現なのだ。
〔暗闇の神〕 大宇宙の観点に立てば、〈クンダリニー〉に対応するものとして、ヘビの〈アナンタ〉があり、とぐろを巻いて世界軸を締めつける。アナンタは、ヴイシュヌやシヴァと結びついて、発展と周期的な解消を象徴する。しかし天底の守護者としては、世界を支え、その安定を保証する。インディアンが家を建てる場合に、「家」は必ず世界の〈中心〉にあるべきなので、地下のナーガの頭に杭を打ち込む。その場所は土占い師が前もって決めてある。〈世界を支える者〉がゾウ、雄ウシ、カメ、ワニなどのことも、たまにある。しかしそれらはヘビの第1の役割の代理もしくはヘビという獣神の補完にすぎない。したがってサンスクリット語の〈ナーガ〉は、ヘビとゾウの意味を兼ねる(KRAM、193)。そのことはマヤ・キチェ族の世界観におけるヘビとバクの同一視と関連づけるべきである(GIRP、267以下)。またこれらの「強力な」動物は、ヘビの身体の先端についた〈口〉しか表示されなかったり、あるいは彼ら自身ヘビに支えられたりすることが非常に多い。いずれにしてもそれらの動物は、暗闇の大いなる神と一般にみなされるヘビの地上的側面、つまりこの神の顕現の攻撃性と力を表現する。
〔円運動〕 〈維持する〉には2つの方法がある。創造を支えるのが1つ。または連続した円になって創造を抱き締め、その崩壊を防ぐ。これは同様にヘビが〈ウロボロス〉の形で実行している。自分の尻尾を噛むヘビである。ここで〈円周〉は〈中心〉を補い、ニコラウス・クサメスによれば神の観念そのものを暗示する。〈ウロボロス〉もまた顕現と周期的な解消の象徴である。これは自分自身との性交や、永続的な自己受胎を表す。尻尾を口に突っ込んだ形が示すとおりだ。死から生への絶え間ない変換である。なぜならその毒牙が、自分の体に毒を注入するからであり、またバシュラールの言葉によれば、「生と死の〈物質的弁証法〉であって、生から死が生まれ、死から生が生まれる」からだ。円のイメージを呼び起こすとしても、とりわけ円の〈動力学〉だ。すなわち最初の〈輪〉だ。自転するだけなので、一見動かないように見えるが、その動きは無限に続く。絶えず自らを動かすからである。あまねく生命を与える者としてのウロボロスは、それだけの役割に止まらず、持続を推進する者でもある。自らの中に生だけでなく時間をも造り出す。螺旋状によじれた鎖で表されることが多い。時間の鎖である。天体の運行を引き起こすからには、〈黄道十二宮〉の最初の形象、その〈母〉であるに違いない。ウロボロスは自然の「古い神」の「古い象徴」で、精霊により玉座を追われたわけだが、それでも依然として〈宇宙形状誌〉および〈地理〉上の偉大な神である。そのような神として、世界のあらゆる最初のイメージの周辺に刻み込まれており、その例として、アフリカ黒人の、おそらく最も古い〈世界像〉であるベニンの円盤がある(FROC、147-148頁)。そこでは、対立物やら原初のさまざまな大洋をその曲がりくねった線で締めつけ、その中央には大地の〈正方形〉が浮かぶ。
〔水の精〕 怒ると恐るべき存在であり、ヘブライではリヴァイアサン、『エッグ』によれば「神々よりも古い」スカンジナヴィアのミズガルズ蛇になる。飲めば潮汐を、鼻息を出せば嵐を巻き起こす。さらに宇宙発生の次元では、「大洋」そのものであり、その9つの渦巻は、世界の輪を取り巻き、一方10番目の渦巻は創造物の下に滑り込み、ステュクス川になる。ヘーシオドスの『神統記』に従えばそういうことになる。片方の手が投げたものを、その到着点でもう一方の手が受け取るようなものだ。それが結局、この原初の未分化の発現の意味なのだ。そこからすべてが由来し、そこへすべてが戻って再生する。地獄と大洋、深い大地と原初の水は1つの〈第一質料〉、原初の実体を形成し、それがヘビの実体なのである。最初の水の精であり、あらゆる水の精となる。地下の水であろうと、地表または地上を流れる水であろうと同じことだ。ギリシアや小アジアの無数の川に、〈オフィス〉Ophisとか〈ドラコ〉Dracoといった、ヘビと関連する名がついていると、クラップ(KRAM、205)が強調する。また「父なるライン川」であり、セーヌ川は「セクアナの神Deus Sequana」だし、宗教上の重要性がよく知られた「母なるガンジス川」もある。さらに「母なるヴォルガ川」、「神の川」といった具合だ。獣神としての属性によって、この水の神の地上および天上の役割が明確にされることが多い。たとえばウェルギリウスの「角のティベリス川」において、ヘビはこのイメージの中で角によって表される雄ウシの強さと結びつく。同様に古代ギリシア最大の川アケロオスは、ヘーラクレースに対抗するために、ヘビと雄ウシの姿に変身する。ヘビは、雲と豊餞の雨の神であり、ときに雄ヒツジの力を身につけることがある。これがケルトやとくにガリアの図像に多く見られる、頭が雄ヒツジのヘビだ。また鳥の力を身につけることもある。それが極東の〈翼を持った竜〉であり、中米の万神殿に祭られた同類の神、〈羽を持つヘビ〉である。
〔中国と中米〕 この2大農耕文明において、それらの象徴的イメージが持つ根本的重要性はよく知られている。両文明とも気象現象に対しとくに注意を払う。天の竜は極東において数多くの王朝の神話的な父である。中国の皇帝は軍旗に竜を刺繍して、その王朝が神意に基づくことを示す。メキシコからペルーにいたるアメリカ・インディアンの神話においては、アレキサンダーが強調しているように(ALEC、125以下)、《鳥=ヘビ》の神話は、トウモロコシ栽培地域の最も古い宗教と時期を同じくする。この神話は「湿気と大地の水と関連づけられる……、しかし最も高度な形態において常に結びつくのが空なのだ。《緑色の羽毛のヘビ》、雨のヒゲを持つ《雲のヘビ》であるばかりか、ヘビの息子、《露の家》……《暁の主》でもある。羽のついたヘビはまず雨雲であり、とくに、真夏に現れ銀色に輝く積雲なのだ(そこから〈白い神〉という別の名が由来する)。その黒い腹から雨が汗となって流れる……。ニューメキシコでは、ヘビの身体として表され、その背中に積雲をのせ、舌はぎざぎざの稲妻である。また中国の竜がまったく同様に横雲の波間を泳ぐことも想起されたい」。
〔中米〕 神話的祖先となり、文明化の英雄となったヘビは(その最もよく知られた形態がトルテカ族および後のアステカ族のケツァルコアトル)、人類を体現し人類のために身を犠牲にする。インディアンの図像を見れば、この犠牲の意味が明らかになる。ドレスデンにある絵文書では、「猛禽がヘビの身体に爪を突き刺し、文明化した人間を作るための血を取り出そうとする。神(ヘビ)はここで、自分が太陽の鳥としてそなえる天界の権能を使って、自分自身を攻撃する。人間の土地を豊餞にするためである。なぜならこの神は雲であり、その血は恵みの雨であって、この雨によりトウモロコシが育ち、トウモロコシから人間が創られるだろう」(GIRP、269)。この犠牲について論じればきりがない。雲の犠牲に留まらず、愛の使命を達成した「欲望の死」でもある。もっと厳密に宇宙発生論の観点からいえば(この観点はスーフイー教では神秘神学の根底となる)、原初の単一性(二重性を含んだ一重)が分裂し、2つの構成要素が分かれて人間の次元が実現する。ジャック・スーステルによれば、ケツァルコアトルの犠牲は、死に続く再生という通過儀礼の古典的なパターンの繰り返しである。太陽となって西で死に、東から再生する。一の中に二があり、それ自身が弁証法であって、双子の保護者である。
〔アフリカ〕 同じような象徴的観念複合が、ブラック・アフリカのドゴン族にも見出される。水の神《ノンモ》は、蛇身の形で表され、神話的祖先かつ文明化の英雄であり、人間に対して最も貴重な文化的な富、すなわち鍛冶と穀草をもたらす。やはり「二にして一」であり、新しい人類のために身を犠牲にする。アフリカの伝承からは他にも多くの例を挙げられる。とくにべニン族と、奴隷海岸の偉大な神〈ダン〉あるいは〈ダ〉がそうで、この神はヘビであって、「虹の物神」である(MAUG)。ハイチのヴードゥー教においては〈ダンパッラ・ウェッド〉になり、水源や川を左右する。というのは、その性質が〈運動〉と〈水〉を兼ねるからだ。雷の石が捧げられ、自分に「仕える者」(つまり自分に取りつかれた者)が、善と悪の両方をなす神々に祈願することを容認しない。〈例外は自らに近い双子だけである〉。また稲妻でもあり、とくに力と豊饅の神である(METV)。ところがダホメでは、〈ダン〉は、今日でも「古い自然の神」であり、先に述べたベニンの円盤のウロボロスであって、両性具有者にして自身が双子なのだ(MERF)。アポメの神殿に保存されている聖なる大蛇の崇拝も同じ説明がつく。若い娘たちが捧げられ、種まきの時期に、儀式として、大蛇の神々と「婚約」する。ヨルバ族にとって、ダンは〈オシュマレ〉、つまり虹であって、世界の高所と低所を結びつけ、雨の後にのみ姿を現す。フレイザー(FRAG、66-67)が伝えるボズマンの証言によれば、ギニア湾沿岸の諸民族は、「乾季と雨量の過剰な時期にヘビに祈願する」。
〔起源のヘビ〕 このような例は、すべてヨーロッパ文明とは独立して成立した諸文明から借りてきたものだが、ヘビが気象に 及ぼす影響の源泉を説明するものであり、この役割は、ヨーロッパの民間伝承にも見出される。クラップ(KRAM、181)が述べている。「虹とはヘビであり、海で渇きを癒しているという考えは普遍的に広まっており、フランスで強調され(セビヨ)、またネバダのアメリカ・インディアンにも、南アメリカのボロロ族にも、南アフリカやインドにもある」。このようなヘビの意味づけはどれも、一定の分野において《起源の大いなるヘビ》の神話の適用にすぎず、原初の未分化の表現なのである。このヘビは、あらゆる顕現のアルファであり、またオメガなのだ。それがまた、ヘビの重要な〈終末論上の意義〉を説明する。この意義を踏まえて、ヨーロッパ文明におけるヘビの象徴の実に複雑な変化を論じることにしよう。まず最初にいっておくべきだが、マレーシアのバタク族にとって、宇宙のヘビは地下に住み、世界を破壊するものである(ELIC、259)。ウイチョール族の場合、ヘビは2つの頭を持ち、それは西と東に開けた2つの巨大な顎に他ならず、この顎を用い昇る太陽を「吐き出し」、「沈む」太陽を「飲み込む」。というわけで、地中海世界の最も古い創造主、つまりヘリオポリスのエンネアド(9柱の神々)の父であるヘビ、アトゥム神に行き着く。このヘビは、時の初めに、原初の水から「自分で」浮かび上がると、創造物をすっかり吐き出した。他には誰もいなかったのでこの「吐き出したもの」の源泉について、諸文献の解釈は一定しない。口からでなく、性器から出たとする文献もある。それならアトゥムは自慰をしたことになる。そのようにして、神々の最初のカップル、シュウとテフヌトが生まれ、「彼らはゲプとヌートを生んだ。それぞれ大気と湿気、大地と天を表す」(DAUE)。その後神々が大地と人間の細部を造ったので、すべてが存在するようになった。そこでアトゥムは被創造物の前に立ち、『死者の書』に伝えられているような、次の言葉を述べた。「我は〈留まるものなり〉。……世界は混沌に、未分化に戻るであろう。その際、我はヘビに身を変え、このヘビを知るいかなる人間もなく、これを見るいかなる神もないであろう」(MORR、222-223)。《起源の大いなるヘビ》をこれほど厳しく描写した例はどの神話にもない。アトゥムは太陽を飲み込むような真似はしない。この天体、我々の生が解体し再生するこの「日常的な」地獄が相手ではお手上げなのだ。空間的・時間的な連続体の総体の前と後でだけ、つまり「神々も人間も」近づけない場においてのみヘビになる。まさしく最初の「古い神」であって、その過酷な超越に身を置きながら〈暇な神〉になるのだ。
〔太陽〕 太陽が、自らの再生を果たすために、連日通り抜けねばならない地上の地獄は、それでもエジプトその他の地域で、全面的にヘビの影響を受ける。アトゥムは、このドラマの内部に関与できないとしても、外部から照らし出すのである。ヘビの形を脱ぎ去って、毎晩沈む太陽の神となり、西に深部への通路を示す。次に舟に乗って地面に沈む。この舟には彼のまわりに天体からなる廷臣が控える。
再生の錬金術が行われる大地の腹が、ヘビの影響下にあるという考えは、『死者の書』の綿密な描写の各所に見出される。通るべき道は12の部屋に分かれ、夜の12時間に対応する。太陽の舟は、まず最初に、ヘビの住む砂地を通り過ぎる。まもなく〈舟もヘビに変わる〉。7時に新しいヘビのアポビスが姿を現す。これは地獄の主人の怪物的な化身であり、聖書のサタンの前触れである。「長さ225メートル(450クデ)の丘をその渦巻で満たし、……その声は神々を引き寄せ、神々によってヘビは傷つけられる」。このエピソードはドラマの頂点をなす。11時に〈舟を引くロープがヘビになる〉。最後は12時台に、黄昏の部屋で太陽の舟が〈650メートル(1300クデ)のヘビの中を横切って〉引かれる。そして舟がヘビの口から出ると、昇る太陽が、スカラベの形を取って、母なる大地の胸に現れる。太陽が上昇するために再び生まれたのだ(ERMR、271-272)。要約すれば、太陽は、他のヘビと戦うために、自らヘビとなる必要があり、大地のヘビの形をした腸に「消化され」、追放される。この飲み込むものと飲み込まれるものの複合体については、論じだせばきりがなく、これと比べればヨナの冒険など単純に思える。全体としてヘビは偉大な再生者、秘儀入門の指導者として現れ、「世界の腹」の主人なのである。そしてこの腹も太陽の、したがって光の、したがって人間の霊的な部分の「敵」(弁証法的な意味で)として現れる。
〔悪〕 エジプト人の聖なる書は、原初の象徴的実体の矛盾するさまざまな面をいっそう発展させるために、それらの面を同数のヘビに分ける。しかし際立った役割がアポピスに当てられたことから見て、もともと混在していたヘビのあらゆる特性の中から、敵対する性質が引き出されつつあることがわかる。これは精神の重視や自然の諸力の否定的評価と歩を一にした。この説明不能で危険な自然の諸力によって、《悪》の、本質的な《悪》に関する、物質的ではない精神的な概念が少しずつ形成されていく。アポビスの場合は、まだそこまで行かないが、すでに小径ができ、後に王道になるだろう。というのは、アポビスの意味作用が曖昧だからだ。一方で、7時に〈自分自身で〉自らの身体に神々を引き寄せ、傷つけられる。だから肯定的な役割をすることになり、要するに太陽の再生を完遂させて、エゴイスティックな利益に反するのだ。また他方、ヘリオポリスの神官たちはアポビスを《敵》とみなし、お祓いの儀式の最中に、その像を神殿の地面で踏みつけ踏み潰して、太陽神ラーがこの最初の「闇の王」に打ち勝つよう助力する。「それは朝と正午と晩に行われ、また1年の一定の時期やら、あるいは嵐が吹きすさぶ時やら、大雨が降るときや、日食のときにも行われる」(JAMM、180)。マスペロの説明によれば、「この日食はラーがアポビスとの戦いで負けたことを意味していた」。
〔ギリシア〕 自然の力を挫いて精神の優位を得る意志から出たというより、ここには、存在の2つの根本的な力を均衡させようという配慮を見て取るべきである。一方制御できない力がもう一方の力を圧倒しないようにするのだ。同じ配慮がギリシア神話にも見出される。アポビスの延長であるテューボーンとゼウスの戦いのエピソードがそうだ。ガイア(大地)またはへラの息子テユボンは、もはやヘビでなく、100の頭を持つ竜であり、マムシに取り囲まれ、「それは腰から下にいたり、山よりも大きい竜である」(GRID)。だからこの竜は、精神に反抗した自然の力の〈行き過ぎ〉を体現する。意味深いのは、ゼウスがこの「反逆者」を征服するに当たって、味方として娘のアテナ、つまり《理性》しかいないことである。オリンボスの他の住人はすべてエジプトに避難し(この神話的なエジプトは動物的な自然の象徴になるだろう)、動物に変身してしまう。テユボンの極悪非道の性質は、その子孫によっても確認される。デルフォイのヒュドラ、キマイラ、2匹のイヌ、オルトロスとケルベロスをこしらえる。しかしケルベロス(⇒イヌ)は、それ自身が邪悪なのではない。再生の周期が永続的に繰り返されるこのギリシアの地獄の中で、弁証法的に肯定的な役割を演じるのだ。ギリシア思想は、エジプト思想と同様に、ヘビを攻撃するとしても、ヘビが宇宙を混沌に引き戻そうとする限りにおいてのみである。また逆に、ヘビが精神の不可欠な「もう1つの面」であり、活力と霊感を与えるものであって、そこから根の樹液が葉の茂みにまで昇る限り、許されたり、さらにはたたえられもする。したがって、自然のあらゆる偉大な女神、母なる女神(後のキリスト教においては神の化身の母マリアになる⇒母)は、ヘビを属性として持つ。しかし第2のイヴとしてのキリストの《母》は、ヘビに耳を傾けないでその頭を潰すことになる。ヘビを属性とする女神といえば、まず最初にアセト〔イーシス〕は額に王のしるしのコブラを、純金の聖蛇ウラエウスをつける。至高の権力と知識と生命と神の若さの象徴である。次にキュベレーとデーメーテールが例に挙げられる。そしてあのクレータ島のヘビ女神もまた冥界に住む。アメンホテップニ世の時代に、ウラエウスが〈太陽の円盤を支えるもの〉として表されたことも意味深い(DAUE、PIED、ERMR、GRID)。アテナ女神自身も、その出生は天界ながら、ヘビを属性とする。また理性と自然の力の結合の象徴として、ラオコーンほど明快な神話は他にない。清聖の罪を犯した神官を罰するために海から出たヘビが、次にアテナの立像の下へ行ってとぐろを巻くのだ。
〔アポッローンとディオニューソス〕 霊感を与えるものとしてのヘビの役割は、詩や音楽や医学やとくに〈占い〉における2人の偉大な神アポッローンとディオニューソスの来歴と崇拝にまつわる神話と儀式の中で明確になる。最も太陽に近いアポッローンは、オリンボスの神々の中で最もオリンボス的な神であり、経歴(といって差し支えなかろう)の初めに、デルフォイの神託を、大蛇ビュートーンという、もう1つの自然力の過剰から解放した。それは何もアリストテレースが強調するように、自然の中に「魂」と「知性」があることを否定するものではない(GUTG、219)。逆に、この魂とこの深遠で霊感をもたらす知性を解放するものである。この2つは精神を豊かにし、精神が目指す秩序の確立を保証するはずなのだ。その意味でアポッローンはディオニューソスと対立しはしない。その点で近代の研究者は一致している(GUTG、MAGE、TEAD)。アポッローンは単に存在の反対側の極から出ただけなのだ。そして両極の補完性が、至高の目的である〈調和〉の実現に必要不可欠なことを知っているのである。だから失神と恍惚がどれほどディオニューソス的であろうとも、アポッローンの世界から排除されてはいない。失神状態でのみ予言するビュティアがそのよい例だ。
〔カッサンドラ〕 アポッローンが惚れ込むカッサンドラの話もその点で意味深い。カッサンドラはへレノスとともに双子として生まれたが、両親は誕生を祝って催されたお祭りの後に、アポッローンの神殿に置き忘れる。「翌朝、2人を探しに来ると、眠っていた。2匹のヘビがちょうど舌を感覚器官の上にはわせて〈清める〉最中であった。脅えた両親が大声をあげると、ヘビは神聖なグッケイジュの中に引っ込んだ。後に子供たちは、予見の才能を示すようになった。ヘビの〈浄化〉によって得た才能である」(GRID、80)。この「浄化」は、ピュタゴラスの〈カタルシス〉と類縁があるようで、このカタルシスにアポロンの影響が一致して認められている。グリマルは付け加えていう。「一般的に、カッサンドラは〈霊感を受けた〉女予言者だといわれる。神は彼女を所有し、彼女は神託を錯乱状態で述べる。逆にへレノスは、鳥や外的な徴候から未来を解釈した」。ということは明らかに、予見にそなわるアポッローンとディオニューソスの2つの面が、ヘビを共通の源泉とすることになる。
また意味深いのが、アポッローンと人間の女の間に生まれた息子イアモスの神話である。彼はヘビによって蜜で育てられ、神官となって長い神職の家系の祖となった(GRID)。また占師と医者を兼ねるメラムプスは、ヘビにより耳を清められた。おかげで鳥の言葉を理解できる。彼は〈黒足の男〉と呼ばれ、伝承によれば、誕生時に母は日陰に置いておいたのに、うっかり足を太陽にさらしたせいという(GRID、282)。ここでは、ヘビの英知が陰の王国にも光の王国にも及び、魂と精神を和解させる。魂と精神は、意識の2つの領域であり、「左の」神聖と「右の」神聖に当たる。
〔ディオニューソス〕 だがギリシア世界においていっそう完全に「左の」神聖を体現するのは、ディオニューソスであり、根本的にヘビのイメージと結びつく。ギュトリが明確に述べている(GUTG、169)。ディオニューソス信仰は、ギリシアにおける文学的完成と時期を同じくし、また「ディオニューソスによる最大の贈り物は〈完全に自由な〉感じをもたらした点にある」と。したがって、ディオニューソスという、偉大な解放者が出現したのは、歴史的にいって、成文法の完成に伴い都市国家にギリシア的な《ロゴス》の勝利が実現したときであった。だから集団的恍惚・失神・憑依(人間の内なるヘビの反乱)は、《法》に対する自然の復讐とみなせる。法は理性のみの子供であり、自然を抑圧しがちだからである。要するにそれは、過剰による調和への復帰であり、一時的な狂気による平衡への復帰なのだ。これがヘビの治療法なのである。もちろん、恍惚・失神・憑依は、ディオニューソスの到来よりずっと以前に存在していた。自然宗教や《大地母神》の崇拝とともに誕生したものである。すでに述べたように、このような神々は、すべてヘビを属性としていた。しかしアテーナイで近代的思想と社会が形を取り始めた歴史上の瞬間に、あのような現象が勢いを盛り返したのであった。その激しさは、人間に対する社会の支配がますます厳しくなる世界に、いつまでも痕跡を残すことになるだろう。理性の独裁に対する、執拗な人間性の解放の意志によって、グノーシス派やらデルウイーシュ教団が誕生し、キリスト教世界では、ローマ教会が抑圧に努めることになる、ありとあらゆる種類の異端が生まれたのだった。こうした運動は、それぞれ自分なりの方法でヘビに対する裁判と戦う。「「天界であろうと、地上であろうと、地獄にあろうと、いかなる存在もヘビなしには自己を形成できなかった」と3世紀のグノーシス派であるベラト派は宣言した」(DORL、51)。そしてオフィス派(拝蛇教信徒、この名前からして信仰告白だ)が付け加える。「我々がヘビを崇拝するのは、神がヘビを人類に対するグノーシスの原因となしたからである……。腸のおかげでわれらは栄養を取り生きることができる。この腸はヘビの姿を模したものではなかろうか」(DORL、44)。この類似は、ヘビと迷路の類似を想起させるが、近代の発見になる心理現象の基本構造を驚くほど先取りしている。同時に内臓を調べて未来を予見するやり方の起源を明らかにする。まだ近代世界によって破壊されていないアニミズム的社会は、このような「闇の」思考の流れを依然としてしっかりと保っている。他の社会では不可避的に不毛な秘教主義に追いやられてしまった。この流れが、たとえばアビシニアのザール(Zar)であり、とくにダホメやハイチの〈ヴードゥー教〉なのである(⇒ウマ)。
しかしこうしたことはすべて、ディオニューソス自身の生涯の中に萌芽としてあり、また完全に「イメージとして説明」される。クレータ島や、フリギアや、最終的にはオルフェウス教の伝承によれば、彼はザグレウスまたはサバージオスの名で、ゼウスと〈ペルセポネー〉の結合から生まれた。すなわち魂と精神、天と地の結合である。この結合を実現するため、ゼウスは〈ヘビに変身した〉とされる。ということは、《精神》が神格化されたとはいえ、原初の神が先行したことは認めるわけで、精神はそこから由来し、自ら再生し子種を得るにはそこに戻らねばならない。しかしディオニューソスもまた本質的に《秘儀を伝授された者》であり、再生し行動するには自らを犠牲にする必要がある。だから彼はティタネスたちに引き裂かれねばならない。ゼウスすなわち《精神》が再度示した意志により再生するためである。そのとき初めて、バッコス神の巫女や信者は、アテナと同じように、ヘビを手中にすることができるだろう。このたとえ話の意味は明らかだ。ヘビは、それ自身、善でも悪でもない。双方の特質を持つ……ヤーコプ・ベーメ(BOEM、209)が後に書く。「なぜならヘビというのは……強大な力を所有しており……、自然に詳しい学者はそのことをよく理解している。すなわち、ヘビには素晴らしい術がそなわり、その存在には徳さえあるからだ」。ヘビは医者ではなく、医学なのだ。〈。ヘルメースの杖〉の意味はそう解釈すべきである。杖の部分は〈手中にする〉ためにある。精神はセラピスト(臨床医)であって、まず自分に対して実験を試みるべきで、その活用法を覚えて社会の用に供する。さもなければ治さないで殺し、存在と理性の関係を調和させないで不均衡と性格上の狂気をもたらす。「霊的指導者」の重要性はそこから生まれる。秘儀参入の結社のリーダーである。彼らはいわば魂のセラピスト(ギリシア語の意味において)であって、精神分析医の先駆であり、むしろ降霊術師なのだ。彼らがヘビを体内で殺しよみがえらせなかったとしたら、有害で「野蛮な精神分析」を実行するにすぎない。ディオニューソス的社会の堕落とともに、それが現実になるだろう。この堕落は、近代世界によってそれらの社会が闇に閉じ込められた結果である。近代世界が「古代人」を援用する際に忘れているらしいのが、彼らの神話の全体から引き出される「節制」の教訓である。神話がヘビを扱うときには必ずこの教訓を伴う。あらゆる均衡の条件としての節制は、キリストの語る「ヘビの英知」にいくつかの点で類似する。
〔タロット〕 西欧の最も偉大な秘教の書物もそれから霊感を受けている。タロットがそうで、アルカナの14番、つまり、《死》と《悪魔》の間に置かれた《節制》は、しかし明白な意味を持つ。半分赤、半分自の服を着た天使(地の半分と天の半分)が、1つは赤、もう1つは青の壷の間でく無色でヘビ状の〉液体を交互に注ぎ込む。2つの壷は存在の両極を象徴する。無限に反復される交換の橋渡し役は、「水の神」であるヘビなのだ。タロット史の研究者ヴァン・レインベルクによれば、このカードは錬金術の象徴であり、さらに魂の転生と再生の教義を「明白に」示す(RIJT、249)。また付け加えて、「古典期のギリシア語(metagiosmos)では、1つの壷から他の壷に液体を注ぐ行為は輪廻の同義語とみなされる」。この説は「節制」の液体がヘビを表すとする、レインベルクの仮説を確認してくれる。というのは、ギリシア・ラテンの伝統では、ヘビに再生した事例が絶えず見られるからだ。町を守ってくれるとみなされた、アクロポリスの聖なるヘビに関するアテーナーの信仰がそうであった。このヘビは「ヘビ人間エリクトニオス」の魂を表していた。エリクトニオスは、アテーナイの「古い王」と考えられ、しばしばポセイドーンと同一視された。ある荒唐無稽な伝承によれば文明化の英雄であって、エジプトからコムギをもたらしたとされる(GRID、およびFRAG、4、84?86)。同様にテーバイでは、町の王や女王が、死後ヘビに変身すると信じられた(FRAG、IBID)。ギリシア全土において、民間の習慣では、ヘビに再生した死者の魂のために、墓にミルクを供物として注いだ。プローティーノスが最後の息を引き取ると同時に、1匹のヘビがその口から逃れ出たという。ローマでは守護霊(genius)の象徴はヘビであった。このような例はいくらでも引用できる。現代でも、ニューギニアや、ボルネオや、マダガスカルや、パンツ一族のアフリカなどのアニミズム文化に見出される。
〔ヨーロッパにおける隠蔽〕 こうした比較によって明らかになるのは、それらの文化とヨーロッパ文化との違いが、象徴の信仰を白日下にさらけ出し続けてきたか否かにしかないということである。ヨーロッパの場合、消滅することはないにせよ、歴史的な圧力により隠蔽されてきたのだった。だから「アングラ」の哲学や思想の流れから、ヘビの元型的な機能を見つけ出さねばならない。数世紀にわたって、公式の教育がヘビの多義性を骨抜きにしようと懸命になったにもかかわらず、相変わらずヘビは生命の弁証法を操る巨匠であり、神話的先祖であり、文明化の英雄であり、「女性の主人」ドン・ジュアンであり、したがって歴史の一定の時期に現れたすべての予言者や英雄の父なのだ。たとえば人類を再生するために現れたディオニューソスの父である。だからアウグストウスの母は、アポッローンの神殿でヘビの訪問を受ける夢を見たとされる。同じ伝承によれば、大スキピオとアレクサンドロス大王も「奇跡の」誕生をしたとされる。この伝説がキリスト自身の正典外の伝記に浸透したのも驚くに当たらない。エリアノスによると(『動物の性質について』)、ヘロドトスの時代にユダヤの処女がヘビの訪問を受けた話があったそうで、フレイザー(FRAG、5、81)は処女が聖母マリアなのは確実とみなす。それにヘビとハトが性的象徴体系の中で類縁性があることはよく知られている。そうなるとやはりフレイザーが伝える東アフリカの部族の風習をどう考えればよいのだろうか。それによれば、「ヘビが女のベッドに来ても、殺したりしない。というのはヘビが先祖または亡くなった近親の霊の生まれ変わりとみなされ、次の子供がつつがなく生まれるはずと〈女に教えに〉来たからである」(FRAG、85)。
〔女性の主人〕 ヘビが豊鏡の主であるから「女性の主人」とみなす伝承の普遍性は、エリアーデ(ELIT、150以下)やクラップ(KRAM)によって豊富な例証がなされた。また特定の大陸を専門的に研究する民族学者、たとえばバウマン(BAUA)によっても、それがアフリカにおける母権制社会の特徴であることが明らかにされた。したがってチョクウェ族(アンゴラ)の場合、新婚の床の下に木製のヘビを置き、女性の受胎を確実にする。ヴォルタ系語族においては、「セヌフォ族の女が妊娠すると、ヘビの表象で飾られた家に連れていく。またグゴロのヌルマ族では、ヘビが家屋に入り込むとその家の女は妊娠するといわれる」(BAUA、423)。
インドでは、子供の欲しい女はコプラを養子にする。ブラジルのトウピ・グァラこ族は、不妊の女の腰をヘビで打って妊娠可能にする(METT)。他の民族では、ヘビが子供の霊を保持し、人類の必要に応じてそれを配る。中央オーストラリアでは、2匹の先祖のヘビが絶えず陸をかけめぐり、立ち止まるごとに「子供の霊」(mai?aurli)を譲る。トーゴでは池に住む巨大なヘビが至高の神の手から子供を受け取り、町にもたらす。
〔性的両義性〕 前にヘビの性的両義性について述べた。ヘビの象徴的意味におけるこの側面は、ヘビが子宮と男根の両方を兼ねることによって示される。この事実は多くの図像により証明され、新石器時代のアジアとか、アメリカ・インディアン文化に見出される。後者において、ヘビの身体(全身が男根的)が、うなり板(陰門の象徴)により飾られる。エリアーデ(ELIC、306)は、子宮の象徴的意味をはっきり示すネグリト(東南アジアの小柄な異人種)の神話を伝えている。それによれば、タペルンの宮殿に通じる道に大蛇がいて、タベルンのために自分で作った敷物の下に暮らしている。ヘビの腹の中には大変な美女が30人いて、頭飾りや櫛などもある。「武器シャーマン」と呼ばれるチノイがその背中で暮らし、宝物の番人役である。チノイの誰かがヘビの腹中に入ろうとするなら、魔法の扉に似た2つの試練を受けねばならず、秘儀伝授の性格を帯びる。成功すれば妻を選べるのだ。
〔影〕 女性と豊餞の主人であるヘビは、月経の原因になるとしばしばみなされる。これはヘビが噛んで起こるとされる。クラップはこの信仰の古さを証明し、アーリマンにまつわる前ゾロアスター教起源の伝承がその証拠である。ラビの世界にもこの信仰はあり、月経の起源をイヴとヘビの関係に帰する。サロモン・レナックが明確にしたとおりである。またニューギニアのパプア諸族にもこの信仰は生きている。このような例はすべてヘビと〈影〉の象徴的類縁性を示す。影も「受胎させる魂」とみなされ、結局はドン・ジュアンなのである。これは精神分析学者のランクが、ドン・ジュアンに関する試論で証明したことで、影はヘビの象徴的なイミテーションなのだ。「インドの中央部では、影により妊娠させられる恐れが非常に広まっている。妊娠した女は男の影の上を通ることを避ける。子供がその男に似るのを恐れるからである……。というわけで、影は男の生殖能力の象徴であって、生殖一般を指すだけでなく、子孫にその男が復活することになる」(RANJ、98)。
〔ヨーロッパの民間伝承〕 このような信仰の名残がヨーロッパの民間伝承にもわずかながら見受けられる。フィナモーレ(『アブルツツオ地方の民間伝承』、ELITに引用)によれば、今日でもイタリアのアブルッツオ地方ではヘビが女性と交尾するという話が語られる。フランス、ドイツ、ポルトガルなどでは、特定の地域の女性は睡眠中に、とくに月経の間ヘビが口の中に入るのを強く恐れる。妊娠するからである。
ヘビ裁判
〔キリスト教〕 キリスト教世界が、たいていの場合、ヘビを否定的にとらえ、呪ってきたのに反し、キリスト教の聖なるテキストのほうは、この象徴の2つの面をきちんと示す。『民数記』において、神が地上に送ったヘビにより「イスラエルの民の中から多くの死者が出た」が、選ばれた民はこのヘビにより命を取り戻す。神がモーセに与えた教えによるとそうなる。「主は炎のヘビを民に向かって送られた。ヘビは民をかみ、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。民はモーセのもとに来て言った。「わたしたちは主とあなたを非難して、罪を犯しました。主に祈って、わたしたちからヘビを取り除いてください」。モーセは民のために主に祈った。主はモーセに言われた。「あなたは炎のヘビを造り、旗竿の先に掲げよ。ヘビにかまれた者がそれを見上げれば、命を得る」。モーセは青銅で1つのヘビを造り、旗竿の先に掲げた。ヘビが人をかんでも、その人が青銅のヘビを仰ぐと、命を得た」(民数記』21、6?9)。キリスト教の時代には、人類を「復活させる」キリストは、ときに「十字架の先の青銅のヘビ」として表される。12世紀か13世紀でも同じことで、レミ・ド・グールモンの訳した神秘詩(GOUL、130)がそれに当たる。しかしながら、中世において最も頻繁に出てくるヘビはそれでなく、「這いまわるよう運命づけられた」イヴのヘビであり、またヘビというより宇宙の竜であって、聖ヨハネも『黙示録』の中でその先行性に異議を唱えず、その敗北を宣言した。「この巨大な竜、〈年を経た〉ヘビ、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わす者は、投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちも、もろとも投げ落とされた」(『黙示録』12、9)。そこで惑わす者は嫌悪を催させる者となる。ヘビに能力や知恵があることは異論の余地がないが、それらの起源については異議が唱えられる。盗みの結果とみなされ、非合法のものとなった。ヘビの知恵は「呪われた」知恵となり、我々の中に住むヘビは、悪徳しか生まなくなる。悪徳は命でなく死をもたらす。レミ・ド・グールモンがこの点に関する5世紀の驚くべき文書を翻訳した。サラゴサのアウレリウス・プルデンティウス・クレメンスの『罪悪の創世記』Hamartigensiaである。プルデンティウスが書く。我々の悪徳は我々の子供であるが、子供に命を与えると、子供は我々に死を与える。それはマムシが子供を出産するときと似ている。「マムシは通常の方法によって出産しない。また子宮を拡張させる通常の性交によって妊娠するのではない。しかし性的興奮を感じると、みだらな雌は雄を挑発し、口を大きく開いて雄を飲み込もうとする。雄は相手の喉に、3枚の舌を持つ自分の頭部を差し入れ、夢中になって接吻を浴びせる。この口腔性交により、生殖の毒液を射精する。受胎した雌は快楽の激しさに傷つき、愛の黙契を破って歯で雄の喉をかみ切る。雄が死んでいく間に、自分の唾に注ぎ込まれた精液を飲みこむ。このようにして閉じ込められた精子が母の命取りになる。このか細い微粒子が成長し、生暖かい洞窟の中を這いまわり、その振動で子宮を揺さぶり始めると……、出産のための出口がどこにもないので、光を求める胎児の努力によって母の腹が破れ、破裂した内臓が胎児にドアを開く……ヘビの子供たちは母の死骸のまわりを這い、それを舐める。生まれたばかりで孤児なのだ……。われらの精神の出産も同じである……」(GOUL、49-50)。
〔バロック〕 これでわかるように、バロックという言葉が発明されるずっと以前なのに、この時代はすでにバロックであった。そしてバロックは、数百年の聞この「超自然の転倒」の中で栄え続け、好んで悪魔学にふけった。毒の花に囲まれてヘビが這う。しかしこの呪われた風景の中で、想像世界の再生が準備される。秘められた夢想の中で、クレオパトラの胸にマムシがとぐろを巻き、あるいはバラの茂みの中で自然の「神秘的な傷」が復活する。あるいはまた、神話の中で、すべての宇宙の竜が炎を吐きながら測り知れない闇の中に再び姿を現す。そこで財宝を守っているのだ。最も貴重な宝物とは不死であるが、人間に与えるためでなく、与えないようにするためなのだ。竜=ヘビは悪魔的な存在でありながら、不死なのである。しかしどうやって不死を手に入れたのか。クラップ(KRAM、288以下)が比較検討を試み、人間とヘビの古くからある競合関係の起源を明らかにした。この関係の上にキリスト教世界の神話が築かれているのだ。「バビロニアのギルガメシュ叙事詩においては、ヘビが英雄から神々の贈り物である不死の草を盗んだ。ニューブリテン島(メラネシアにあるビスマーク諸島の1つの島)では、ある善霊が、ヘビを死なせ、また人間が皮膚を替えて永遠に生き延びられるように取り計らおうとした。あいにく悪霊がそれを逆にする手段を発見してしまった。そこでヘビは皮を替えて若返り、人間は死ぬ運命になった……聖書の話の元型では、ヘビがアダム(というよりイヴ)に、死の木が生命の木だと信じ込ませたらしい。ヘビ自身はもちろん生命の木の果実を食べた」。ありとあらゆる罪悪を身につけたヘビは、倣慢でエゴイストでけちだ。ヘビの「よい側面」(ヤーコプ・ベーメの言葉を借りる)はもう存在しない。「倣慢に身を委ねたがる偽りの側面」しか残っていない(BOEM、240)。「保護下にある貧しい人たちが飢えに苦しむのを放置し、心中に現世の富を蓄積する者は、キリスト教徒ではない。ヘビの息子である」(同上、243)。生命力の主人としてのヘビは、もはや豊餞の象徴でなくなり、邪淫の象徴となる。「ヘビはあらゆる動物の中で最も邪悪であり、イヴから処女の恥じらいを奪い、獣的な性交の欲望を吹き込み、また人間のあらゆる猥嚢さ、獣的売春の欲望をもけしかけた」(同上、250)。
〔ダンテ〕 ヘビの「よい面」は、神の裁きを実行する冥界の役割においてのみ見出される。それはラオコーンの神話を思い出させないでもない。ダンテの『地獄篇』がそうで、第25歌の冒頭において、盗賊でありなおかつ漬聖の罪を犯した男が、ヘビに締めつけられるのを見て、詩人は叫ぶ。「これを境に、ヘビが私の味方になった」。なぜなら1匹のヘビが「もうこれ以上はいわせぬぞ」とばかり、彼の首に巻きつき、「さらに1匹のヘビが彼の両腕にからみつき、再び彼を縛し、ぴたりと胸倉に鋲打ちしたので、彼は両腕の貧乏ゆすりもできなくなった」。
その先で、ダンテは、ヘビと亡者の途方もない融合を描写する。両者の凄まじい婚姻は象徴としてのヘビに込められた性的意味合いの両義性を十二分に誇示する。
「さてそれから、まるで熱い蝋の身であるかのよう、
かれらは密着して1つとなり、互いの色をまじえあい、
どちらがどちらか、もとの姿はまったく分らぬ」
〔スーパーマン〕 中世に作られ今日まで残る《英雄》の概念における、ヘビ=竜の意味作用は、G・デュランの言葉(DURS、345)に従えば、「結局のところ」肯定的でもある。《竜》は《聖》の段階に達するために乗り越えるべき障害なのである。よきキリスト教徒なら、聖ゲオルギウスや聖ミカエルにならって、自分の内にあるこの「獣」を殺さねばならない。ジータフリートの異教的な神話は、この意味に「ねじ曲げ」られる。この「新しい英雄」が堕落すると、「超人」やら「スーパーマン」になるのだ。それによりキリスト教文明なるものは、まさしくキリスト教が抑止しようとする行き過ぎに陥るのである。その結果どうなったかはよく知られている。深刻の度合いが甚だしい結果といえば、《善》と《悪》の道徳が単純化され精神的外傷を与えるものとなったことが挙げられる。このような道徳は存在の深い願望や霊感を無意識の領域に抑圧して、人格の統一を破壊する。極端な場合、人間の生命原理そのものが悪影響を受ける。そのせいで「現代文明の危機」が生まれ、その原因についてカイザーリングが適切な説明を与えている。「本源的な生命は、〈自己を確信するにいたった〉昼の意識からすれば、純粋で単純な《悪》に思えるはずである」(KEYM)。今日の私たちが知っていることだが、こういう極端な自信は、「光」を口実にして、新たな蒙昧主義に行き着くほかない。
復権したヘビの象徴に向かって
〔ロマン主義〕 本源的な生命とそれを体現するヘビを否定するのは、ヘビが関係し、精神の糧となる夜の価値を否定することになる。19世紀になって初めて、ロマン主義とともに再検討の動きが生じた。これまた詩人や芸術家がその主唱者となり、彼らのうちの傑出した者は社会から「呪われた者」になった。この社会の解放を企てたのが彼らなのだ。「夜に見たものを明るみに出せ」とドイツの画家C・D・フリードリッヒは書いた。一方フランスでは「写実派」のクールベが応じる。「はっきり見えすぎる。自分で自分の片目を傷つけねばなるまい」。割れ目ができ、そこから20世紀において思想の本物の革命が起こる。その革命でシュールリアリズム運動が決定的な役割を演じる。アンドレ・ブルトンは1924年に第1の『シュールリアリズム宣言』で次のように書いた。「一見実に矛盾していそうな夢と現実という2つの状態が、一種の絶対的な現実、いわば〈超自然性〉に将来合体すると私は信じている」。その間、フロイトは精神分析により、病因性の内的検閲を攻撃することを通じて、人間を自己自身に復帰させることを目指す最初の臨床的方法を創始した。だから精神分析の父に対する裁判が起こったことは驚くに当たらない。ヘビ裁判の延長にすぎないのだから。
〔現代〕 まさしくこの瞬間に西欧思想は、単なるエキゾティシズムを越えた関心を抱いて、いわゆる原始的な文化に顔を向ける。そのような文化はまだ地球上に残っている。主としてアフリカ、アメリカ、オセアニアなど「アニミズム」の地域である。今日の西欧人にとって、ヘビが嫌悪の対象でしかないとしても、それらの地域では依然として完全な元型に止まり、その肯定的な特質が公然と維持されている。インディアンやアフリカの子供は必ずしもヘビを恐れるわけではない。たとえ新しく移植された近代の諸構造がヘビの伝統的な顔を覆い隠す傾向にあるとしてもだ。たとえばペニンでは、すでにその歴史を概説した古い神ダンが、何事にも不意を突かれず、どんな新しい現象が現れても巧みに適応してみせる。エネルギーと動きの主人であるから、列車や蒸気船や自動車や飛行機の守護神になってみせた。一方その代理の〈Ho?Da〉はそのまま変わらない。これはへその緒であり、出産間際の女を年老いた大地母神に結びつける。生まれてくる子供の重みを母から女神が受け取る際にである(MAUG)。すでにエリアーデが述べているように、ときとしてヘビは勝ち誇る首長と戦う民衆の象徴であった。中国では、「竜のよだれ」に女をはらませる力があるが、毛沢東は西欧のジャーナリストに答えたことがある。「竜の真珠について議論したりしない」と。つまり明白な完壁を意味する。
〔結論〕 根源的な元型であり、生命や想像力の源泉と結びついたヘビは、世界中で、見かけはおよそ矛盾したさまざまな象徴的特質を保持してきた。その中で最も肯定的な諸特質は、歴史上の一時期に指弾を受けたとしても、忘却から脱し始め、人間に調和と自由を再び与えようとしている。詩や芸術や医学がそのために尽力しており、どれも常にヘビを標章としてきたのだった。基礎科学もきわめて革命的な発見により寄与する。まさしくアインシュタインの有名な等式、物質とエネルギーの同一性から結論としてそれが導き出せる。
したがって現代のあらゆる混乱にもかかわらず、真の学問の女神アテーナーは手と胸にヘビを持ち続ける。このヘビからディオニューソスと悪魔と中国歴代の皇帝が生まれたのだ。